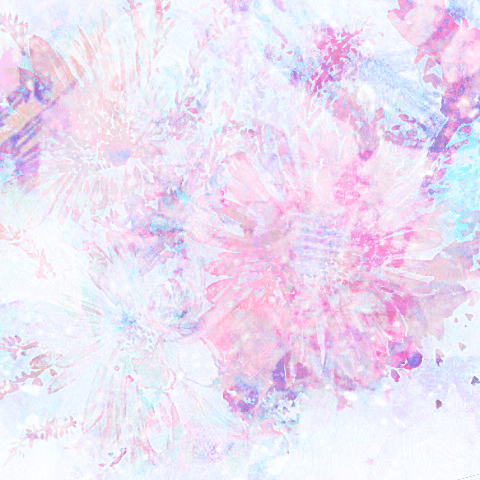Episode.7
どうやら、はとんでもない思い違いをしていたらしい。
幻太郎と小一時間ほどやいのやいのと揉めに揉め、お互いの間で誤解が生まれていることが判明。はてっきり、“契約のことをさっさと話さず、何食わぬ顔でうちにいる神経が信じられない。お前なぞ来月を待たずして解雇だ解雇”と思われていると思っていた。一方の幻太郎は、会社や契約のことは一切知らず、自分が心ない――かはどうかは彼の所感であるが――一言を言ったせいで、が家に来なくなってしまったと思っていたらしい。
正直、そのことに関してははさほどダメージを受けていない。邪魔かあ、邪魔なら仕方ないよなあ、くらいの心持ちである。先生って意外と繊細だったんですね!? といらないことを言おうとした口をなんとか閉じておいて、代わりに「そんな全然気にしてないですよ! 最初の頃も似たようなこと言われてましたし!」と話ごと笑い飛ばそうとした。するとさらに幻太郎の顔が厳しくなったので、あ、失言、とはフリーズしてしまう。もう何を言ってもだめな気がしてきた。
――さて、事が落ち着いたところで、は改めて幻太郎と向き合う。心なしか、先生も疲れたような顔をしていらっしゃる。その気持ちは心から察する他なかった。
「ところで先生、ほんとに代表から倒産のこと聞いてませんかっ?」
「何も」
あの人ほんとにフリーダムすぎる……! はしばらく会っていない代表の顔をぼんやりと思い浮かべる。それでも、てへぺろをした顔しか浮かばなかったので彼のルーズな人格像がさらに浮き彫りになった。各従業員に会社の説明を任せて、あとは書面上の契約だけ綺麗さっぱり白紙に戻しているとみた。現に、の会社都合の退職届は先月のうちに受理されている。
これ、詐欺として訴えられてもおかしくないのでは……? は朝もしくは夕方のニュースに代表の名前が載らないことを祈った。
「ということはなんですか。先月末で自動的にあなたとの契約は切れている、と」
「そういうことになりますね……」
幻太郎には本当に申し訳がないの一言に尽きる。これ、土下座する流れでは? とが座布団の上でじっと固まっていると、なにやら思案していた幻太郎が「少し待っていなさい」と言って、その場からすっと立ち上がった。すると、作業机に向き合った彼は紙に何かを書き始めたではないか。
次は何が起きるんだろう……。というか、エコバッグの中身だけ冷蔵庫に入れてきちゃだめかな……。でも今ってそういう空気じゃないよね……。うん、読める空気はちゃんと読もう。そう思いながら、ほぼ無音の数分を過ごした。じきに、静かにペンを置く音がして、幻太郎はくるりとこちらを振り返り、再び座布団の上に腰を下ろした。そして、の目の前に滑らせた一枚の紙――そこにはまるでパソコンで打たれたような明朝体がびっしりと並んでいた。
「字ぃうまッ!?」
「えー。それでは、邸宅の採用面接を始めます。皆様、A4横書式一枚の書類は行き届きましたか?」
まるで面接官のように振舞っている幻太郎に驚きを隠せない。え? 皆様って、先生、ここには私一人しかいないのですが。状況を把握しきれていないがぽかんとしていると、「おやぁ? 今年の新卒は返事もできない非常識人なんでしょうかねえ? 社会人としてそれはどうかと――」「行き届きましたッ!」地獄のような企業説明を経て、“社会人“”というワードに敏感になったはきびきびと返事をする。よろしい、と言うようにを一瞥した幻太郎はこほん、と咳払いをした。
「では、お手元の書類をご覧ください。邸宅の契約内容は以下の通りです。不明点及び質問があれば、その場で挙手するように」
さっきから言ってる書類ってこれのことだよね……。は達筆な字で書かれている紙を手に取る。大見出しに“夢野幻太郎宅の家政婦業における労働条件”と書かれていた。ものの数分で書いたとは思えないくらい、かなり本格的な書面だ。
雇用期間無期限、週五勤務かつフルタイム八時間で完全週休二日制、残業手当有り、社会保険、福利厚生云々――見慣れない文字の羅列にはぐるぐると目が回ってくる。一通り目を通しても、話の根本は謎のままだ。要領得ない顔で幻太郎を見上げると、「不明点、質問等あればその場で挙手するように」と彼は顔一つ変えずに同じことを言う。がおそるおそる手を挙げると、「はい、若槻さん」と名を呼ばれた。
「こっ、これは一体どういうことでしょうか……?」
「見て分かりませんか?」
「分かりません……」質問があれば手を挙げろと言われたので言ったのに、お前は馬鹿かという目で見られてしまう。理不尽である。はしゅん、と肩を丸めた。
「小生個人で、あなたを家政婦として雇います」
「え゙ッ」
幻太郎と紙を凄まじい速度で見比べる。幻太郎の口から嘘ですよ、という言葉が飛び出すのを待っていたが、いくら待っても彼の口が開かれることはない。どうやら幻太郎は本気のようだ。
は再び紙に目を落とす。勤務地として幻太郎宅の住所が乗っており、業務内容は家事全般――今までやっていた夕食代行に加えて朝昼の調理代行、そして掃除洗濯等が含まれていた。その他項目も目を張るほどの高待遇がつらつらと記されているが、特にが焦点を当てたのは“給与 要相談”の一行である。
「先生、ちなみにここのお賃金は……?」
「いくらがいいですか」
「私の言い値ですかっ!?」
「ああ、それだと契約っぽくないですね。仕方がない、小生が決めますか」
ぽくないって……! 先生はどこまで本気なんだろう。いつもならどこまでが嘘なんだろうと頭を捻るところだが、今回ばかりは全部本当のような気がして逆に怖ろしい。
幻太郎は正座をしていた足をにゅ、と伸ばして、机の引き出しから電卓を取り出した。ふむ、と軽く折った人差し指を唇に添えて、電卓を軽快にカタカタと打っていく。
「そうですねぇ……。まあ、月給制として、月にざっとこんなものですか。今まで誰かを雇ったことがないので、相場は分かりませんが」
「ああ、あなたの希望に応じて日払いもしくは週払い、時給制も考慮しますよ」そう言われながら、差し出された電卓に表示された金額にはぎょっと目を張った。
「前頂いてたお給料の倍以上なんですがッ!?」
「おや、そうなんですか。私があなたに渡していた額の何割貰っていたかは知りませんが、小生がこの二年と半月の間、あなたの仕事の出来を鑑みてこれくらいなら出してもいいと判断した額です」
とんでもないことをさらりと言われて、は心臓がぎゅっと痛くなった。い、今褒められた? 先生に褒められた? 状況が状況なので手放しで喜べないが、はじぃんと心が暖かくなる。自分がしてきたことがこうして目に見える数値で表れるなんて……これが社会貢献、いや先生貢献というやつだろうか。は今非常に感激している。
しかし、それとこれとは話が別だ。今後の生活がかかっていることをこんな数分の間で決めていいものか。否だ。まずは信用のおける人間の意見も聞かなければ。
「せ、先生~……」
「なんでしょうか」
「私にとってはすーごくありがたいお話なんですけども……。私一人じゃ決めかねるので、これ、一度家に持ち帰っても――」
「ええ、検討はご自由にどうぞ。ただし、あなたがこの部屋を出た瞬間にこの紙は破り捨てますのでそのつもりで」
「えッ!?」破り捨てる? いきなり野蛮な言葉が出てきては声を上げる。そ、それは遠回しに“今ここで決めろ”と言っているようなものでは……? わたわたと震えるを他所に、幻太郎は分厚い紙袋を一瞥した。
「それは企業のパンフレットでしょう。転職活動向けの説明会にでも参加してきたんですか?」
「へ? あ、はい。そうですっ」
「その調子だと、再就職先はまだ決まっていないようですね」
「そ、そのとおりです……」
「白か黒かも分からぬ企業に就職するのがあなたの希望なんですか? 今のご時世、説明会では甘いことばかり言って、社内の真の闇を見せないようにする会社が多いです。下手をすれば猛烈なパワハラ、もしくは会社で寝泊まりすることを強いられますよ」
「会社で寝泊まり!?」
「それに比べて、小生の家での勤務は純白そのものです。慣れた職場、自分の得意なことでお金を稼ぐことに何のデメリットがあると? そもそも一度家に持ち帰るほどの検討が必要ですか?」
用意されていた選択肢をごりごりに塗りつぶされてしまい、は言葉を失う。大切な選択をする時は一言相談をしろ、と父親に口酸っぱく言われていたが、この状況では相談も何もない。電話なら大丈夫かなっ? あ、だめだ、お父さん今仕事中だ。ならばルームメイトに――あ、だめだ、今日は大事な撮影があるって言ってた。“詰み”の二文字が頭を過ぎった。ゴゴゴ、と目の前からかなりの圧を感じて、焦燥が選択を急かす。
これがいわゆる圧迫面接……? いや、なんか違う気がするぞ。それはそうと、幻太郎が言っていることはごもっともだ。派遣や契約社員の労働条件は厳しいところが多いと聞くし、なによりもの好きな家事をしてお金が稼げるという、最後までチョコたっぷりのお菓子のように甘い話だ。これに乗らない手はない。
それに、は夢野幻太郎という人間をよく知っている。少し茶目っ気があって嘘話が好きな小説家だが、決して人を陥れるようなことは言わないし、しない人だ。
……いい、よね? うん、多分、大丈夫だ。今この瞬間、の道はたった一つに絞られた。
「ぜひ、御社に就職したく思いますっ!」
「邸宅は会社じゃないのですが……まあいいでしょう」
「はい、採用」紙をぴっと取り上げられ、右下の余白部分に幻太郎の印鑑がぽん、と軽く押される。続いて朱肉を差し出されて、空気を読んだは親指にインクを付けてぎゅっと拇印を押した。すると今度はウェットティッシュをすす、と手前に滑らされる。ここまでが幻太郎が書いたシナリオのように用意周到だ。さすがは小説家……は親指についたインクを取りながらふむふむと感心する。前提として、そこに流されやすい自分がいることについては見ないふりをした。
「さて……あなたをうちで働かせるにあたっての諸々の手続きはこちらで済ませます。必要なことがあればあなたに都度確認するのでそのつもりで」
「かしこまりましたッ」
「それではこれにて面接は終わりです。採用された方はさっそく業務に励むように願います~」
朱肉を引き出しに仕舞った幻太郎。それからはこちらを見ることもなく、彼は机と向き合った。先ほどの言葉のまま、持ち場に散れということだろう。丸く膨らんでいるエコバッグを一目見たは、幻太郎の背中にそうっと問いかけた。
「あのう~」
「なんですか」
「夕ご飯なんですけど……ほんとに、LINEで送ってくれたものだけでいいですか? スープとか前菜とか、他にも何か作りましょうか?」
幻太郎が所望したものはたった一品。それも、夕食には少し似合わないものだ。人によっては物足りないと感じるかもしれない。
良かれと思って言ったけど、余計なことって思われたらどうしよう……。無言の時間が続くにつれて、ここに居づらくなってきた。すると、少し目を逸らされながらもこちらを振り向いた幻太郎。目が合う頃には、どこかもの欲しげな色が彼の視線から滲み出ていた。
夢野先生宅での久々の夕食――とはいっても、品目は幻太郎ご所望のエッグベネディクト、牛乳と缶コーンで作ったコンスープとカット野菜を洗って盛っただけの彩りサラダである。どこからどう見てもモーニングメニュー、それも洋食だ。この家で和食以外のものを振る舞うのは初めてではないだろうか。
冷蔵庫の中に何かはあるだろうと踏んでいたは余裕綽々であんな提案をしたものの、いざ冷蔵庫を開けてみてびっくり。まるで電器屋に置かれているダミー冷蔵庫並に空っぽだった。「先生、こんな中身で今までどうやって生きてたんですか!?」「失敬ですね。最近は家にいたままでも外食さながらのご飯が食べれるんですよ」「うぐ……っ。調理代行業殺しの新サービス……っ!」自分の気がきけば何か買ってきたのに。まだまだ成長しなければいけないようだ。
本来であれば、メインのエッグベネディクトも真っ白なお皿に盛り付けた方が映えるものだが、あいにく食器棚には和柄の陶器しかなかった。というかなんでエッグベネディクト? お昼にいたお店で食べたのでは? あ、でもあの騒ぎを収めてくれたから食べ損ねたとか? ということは私のせい!? うわああぁぁ絶対そうだ……っ! はとても申し訳なく思いながら、エッグベネディクトの作り方を検索し、幻太郎の舌に合うように自己流アレンジも含め、なんとか即席で作ってみたのだった。
ベーコンは塩分が多く油が出るので薄切りハムで代用。ソースはさっぱりとしたものに仕上がるようにレモン果汁をきもち多めに、代わりにバターを少量にしてみた。イングリッシュマフィンは香ばしさを重視して、ライ麦入りのものをセレクトした。卵はちょうど安売りされていた赤卵を使用。さすがに本場の店のものを食べた後では味が落ちている気がして何度も味見しては首を傾げてしまったが、時間は一秒も待ってくれない。ニューヨーク風モーニングのフルコースを並べて、ええいままよ! と幻太郎に出した。彼はナイフとフォークを使って黙々と食べ進めている。
食べてくれてるってことは、まずくはないってことだよね……。ついでに言うと、「あなたの分も作りなさい」と言われた時は耳を疑ってしまったが、断る理由も思いつかなかったので、自分も賄いとして夕食にあやかっている。完全に幻太郎の分しか考えていなかったために盲点だった。あー危ない危ない。イングリッシュマフィンが二人分でよかっ――
「おいしいです」
……いま、なにか聞こえた。
は半分に切った卵から卵黄がとろりと滲み出たのを他所に、彼女は「先生、いま、おいしいって言いました?」とストレートに尋ねてしまう。一方、幻太郎は何も言ってませんと言わんばかりに無言で食べ進めている。それでも、聞き間違いじゃないと思う。思いたい。言っていないなら言っていないときちんと言ってくれるはずだから。否定しないあたり、きっとそうだ。
先生が……先生が、おいしいって言った。先生がおいしいって言った! 初めて、ちゃんと、お茶目な演技なしで、おいしいって!! テンションが上がったは卓袱台に乗る勢いで前のめりになった。
「これ味薄くないですかっ? 普段の味付けもこれくらいさっぱりしたもので大丈夫ですっ? あっ、ちなみにそのソース、レモン果汁ちょっと多めにしたんですけどくどくないですかっ? あとイングリッシュマフィンもっ――」
「煩いしつこい黙って食べるッ」
「はいすみませんッ!!」
叩きつけられるように叱られてしまい、びゃッと体を跳ねさせたは元の体制に戻る。それでも隠しきれない歓喜で体がうずうずしてしまうが、こればかりはご容赦願いたい。とても嬉しい。首を傾げながら味見をしたエッグベネディクトが、今はすごく美味しく感じられた。
「先生っ」
「なんです」
「これからもお世話になります!」
かなり緩んだ顔で言ってしまったと思う。案の定、幻太郎は苦しげな、何かに耐えているような顔をした後、「……こちらこそ、よろしくお願いします」とぼそりと言った。目こそ合わなかったが、そういうところが彼らしいと思って、の口からえへへ、と小さな笑みが溢れたのだった。