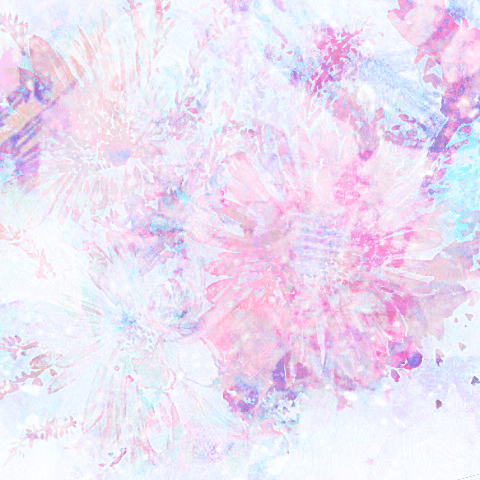Episode.8
彼女と過ごす、四度目の春がやってきた。
遠くから聞こえる鶯の声。生き物の目覚めを報せに訪れた花信風が、ほんの僅かに開けた窓から部屋の中へ流れてくる。ここまで“春爛漫”の三文字が似合う日もそうそうない。溜息をつきたくなるほどの、穏やかな小春日和だ。
そんな静けさの中、インターホンが家に鳴り響く。せっかく、自然がつくりだした空気感を味わいながら創作活動に浸っていたというのに、人為的な機械音に、幻太郎はむ、と眉を顰める。
しかし、あちらも仕事の一環故に致し方なし。やれやれ、と幻太郎が腰を上げようとした、その時。
「はあーい!」
家のどこかから聞こえてきた彼女の声によって、幻太郎の腰が座布団の上に再び落ち着いた。立ち上がる代わりに、幻太郎は耳を澄ます。忙しない駆け足が紙の上を走るペンのように、瞼の上で世界を創造させる。彼女が玄関に行き、引き戸を開くまでの情景を、幻太郎は事細かに思い浮かべた。
「お疲れ様でした~っ」
じきに、引き戸がぴしゃんと締められる。すると、「先生ー! 夢野先生~! お荷物届きましたよー!」とすぐさま声が飛んでくる。いつもならば玄関か部屋の前にでも置いておけと指示をするが、今回は届いたらすぐ声をかけろと言ってあった。ここまで思い描いていたシナリオ通りに事が進むと、逆に拍子抜けだ。茶の間を温める意味で、どうか廊下で軽く転んでやくれないだろうか。
「先生っ! お荷物っ――」
「聞こえています。適当に置いておいてください」
「分かりました~」部屋の襖を開けるやいなや、すぐに部屋の隅へどさっと段ボールを置いた。最近は、部屋に入る前の声かけがない時もちらほらとあり、遠慮の“え”の字もなくなってきたように思う。しかし、機嫌が悪い時や修羅場の時は何かを受信したように部屋に近づきすらしないので、そういう、察する能力は伸びたようにも思う。
……まあ、この家以外の社会に通用するかと問われれば、謎なところだが。自分の役目を終えてさて帰ろうと踵を返したに向かって、「少し待ちなさい」と声をかける。幻太郎は筆立てにささっていた鋏を片手に、彼女が置いた段ボールを手元に手繰り寄せる。中身を傷つけないように封を開けると、そこには中いっぱいに敷きつめられた単行本がどっしりと眠っていた。ちなみに、全て同じ表紙のものである。
五冊でいいと言ったのにこの大盤振る舞い――どうやらここの出版社の担当も話を聞かない愚かな人間らしい。もしくは、“良かれと思って”という言葉を盾にして気が利く人間と鼻高になっているのか……どちらにしろ迷惑なことだ。
というかこの娘、この重量のものを一人で運んだのか――幻太郎は部屋に留まっているを訝しげに見ると、何処吹く風の彼女は、段ボールの中身を見下ろしながらはて、と首を傾げていた。
「先生。これ、全部同じ本です?」
「ええ。来月に出版される新刊の見本本です」
「えっ! 先生のですかっ?」
他に誰がいる。幻太郎は頷くと、の目が太陽が反射した水面のようにきらきらと輝く。ここだ、と思ったところで、幻太郎は内一冊を手に取った。彼女に差し出すか差し出さないかの手前のところで、こほん、と咳払いをして、声高らかに言う。
「あなたがど~しても欲しいと言うのなら、一冊くらい差し上げても――」
「いいんですか!?」
「わーい! 大事に読みますっ!」すぐさま本を両手に取ったは、本を表と裏をちらちらと引っくり返してはわあわあと歓声を上げている。「表紙の絵すごくきれい!」「カバーさらさらしてる!」「タイトルのところだけちょっと立体になっててすごい!」などなど……本の装丁ばかり褒めていないで中身を読め中身を、というのが本音である。
……まあ、受け取ったのなら上々。あとは自分用と乱数と帝統と兄さんと――数少ない、知り合い以上の人間の分を取っておいて、幻太郎はたっぷりと残った在庫を段ボールごと部屋の隅に置く。これは、きちんと冊数を言ったのに余分に寄越した担当へ着払いで返すことにする。
「そういえば、このあいだは直接家まで担当さんが届けてくださいましたよね。えぇっと……」
「見本本です。あれはまた別の出版社の人間ですよ。郵送でいいと言ったのにわざわざ家にまで押しかけてきて……かなり迷惑でした」
「だから先生、あの時ちょっとご機嫌ななめだったんですねー」そう言ったは、その時のことを懐古するように宙を見上げた。
「でも、ふつうに良い人でしたよー? ああやって、時たまお客さんが来ると、私も接待しがいがあるので楽しいんですけど……」
「勘弁してください。小生は他人を家に上がらせたくないんです」
「でも、担当さんですよ?」
「それが? 他人には変わりないでしょう」
自分が一方的に観察する分にはいいが、人との過度な接触は避けたい。家に上げるなど以ての外だ。おまけに、仕事中だというのにその担当がこの娘に言い寄るものだから早々に原稿を叩きつけてお帰り願った記憶がある。もう二度とあの出版社では書かないと誓った。
言い寄られたことすらも、“良い人”ということで片付ける鈍感娘。思わせぶりな態度をする彼女にも非があると幻太郎は思う。そんなははて、とひとり首を捻った。
「先生」
「なんです」
「私は、先生にとって他人じゃないんでしょうか……?」
……最近、ほんの少し頭が回るようになってきたらしい。面倒なことだ。そのまま疑うという感覚を持たずに生きていればいいものを。さて、どう言って踊ってもらおうか。幻太郎はしばらく思案した後、ゆるゆると口を開いた。
「あなたは小生の家政婦でしょう?」
「そ、そうですね……。あれ? でもあの人も先生の担当さんだから――」
「小生の首を絞めるように原稿を急かす担当か、小生の身の回りのことをするあなた……他人というカテゴリーの中でもどちらの方が上だと思いますか?」
そう言うと、あれ? あれ? 目をぐるぐると回す。そしてじきに、「わ、私、ですかねぇ?」と疑問形になりつつも想像通りの回答が出た。「そうですよねえ」幻太郎は深く頷いて、もうこの話は終わりだと言わんばかりに、「ところで、」と話を変えた。
「あなた、資格勉強はいいんですか。今日は一度もテキストを開いている姿を見ていないんですが」
「あはは……。実は今日、テキストをうちに忘れちゃって……。今日は単語カードオンリーで頑張ります」
は、仕事着と化している割烹着のポケットから単語カードを取り出す。仕事の合間に休憩時間として好きなことをしていいことにしているが、まさか資格勉強をするとは思っておらず、テキストと向き合っている彼女を初めて見た時は、思わず二度見をしたものだ。
曰く、数ヶ月前から、は調理師免許を取るべく週に何回か夜間学校に通っているらしい。「興味があることってこんなにも集中して勉強できるものなんですね!?」と目を輝かせながら感動していた。学生の頃の彼女は勉強ができなかったと言っていたので、まあまあ納得のできる回答だ。
「そもそも、わざわざ調理師免許など取らなくてもいいのではないですか」
「なんちゃって就活を通して、資格がないと何もできないんだな~っていうことに気づいたので」
「それに、先生のところにずっといられるわけでもないですし」苦笑いをしながら、はそう言う。彼女の都合ならさておき、こちらから手放す気など更々ないが? 目を細めた幻太郎はそう思うが、それは表に出ないものとして早々に泡になって消えた。「それにですよ!」
「今までよりも凝ったご飯が作れるので、先生にも満足していただけるかと!」
ぐ、と顔を顰めそうになった幻太郎はすくっと立ち上がる。「お腹が空きました。何か軽く摘めるものはありますか」涼やかな声色でそう言うと、はぱっと顔を明るくさせた。「実はおやつに出そうと思ってたおからクッキーがあるんですよ~!」とスキップをする勢いで、彼女は自分の隣に並んだ。
――「なッ、んですか急に……!」
――「こっち、こっちです! 先生に見ていただきたいものがあるんです!」
部屋を出て、春の陽射しを吸い込んだ廊下を歩く。終始続いているのおから談義を右から左へ流していると、ふと、縁側の庭が目に入った。
いつからか、庭師を雇うのも面倒になり、娘が庭いじりをしなくなってからは、幻太郎自らが庭に手を加えている。といっても、毎日草花の世話をできるわけではないので、あまり植物は植えていない。定期的に雑草を抜いているおかげか見栄えはそこそこ良い、という程度だ。それに、自分がどんな花を植えたところで、二度目に訪れた春の、あの極彩色の景色は二度と見られないと思った。
「そういえば私、長らくお庭いじってないんですけど、結構持つものなんですねえ」
同じく目に映していたらしいがほのぼのと言う。いくら、こちらが忘れ得ぬ記憶として体の中に残っていても、人脈も多く細かいことは気にしない彼女にとっては、ただの日常の一部にしか過ぎないだろう。
――「去年の夏頃に植えたんです! 今日見たらみんな綺麗に咲いてたので、いてもたってもいられなくてですねっ!」
……予想はしていたことだが、溜息を一つ吐くことくらいは許してほしい。
「何を言っているんですか。あなたが整備したおかげで、あれ以来小生が手ずから毎日手入れをしているんですよ」
「えっ!? そうなんですかっ!? 言ってくだされば私がやったのに……!」
「今までのあなたの仕事に含まれていなかったので、小生も言わなかったんですよ」
「うう……。すみません……。資格試験に受かったら自分できちんとやりますので……!」
「おやおやあ? それは来年の話でしょうか? それとも再来年ですかねえ。あなたが合格通知を受け取るまでにいくつ季節を巡るやら……」
「こっ、今年中に受かるように頑張りますよう!」
本当に……あとどれだけの季節を、この場所で、彼女と
いつか、別離の時は来る。それは人と戯れる上での約束事で、それを避けて通るということは、世界へ不死の薬を探しに行くような、途方もないことだ。だから、その時が来るまでは、果てを見ないようにして、途中にある景色だけを、この目に映しておきたい。
幻太郎は庭から視線を外して、足袋を滑らすように廊下を進んでいく。その後を、忙しない足音がぱたぱたとついてきた。
「お気になさらず。小生が所有している庭ですから。責任もってこちらで管理しますよ」
「そんなこと言わずに……! したいです庭いじり! やらせてください庭いじり!」
掃除炊事洗濯……やることがたくさんあるのことを思っての言葉を跳ね除けられて、幻太郎はどうも腑に落ちない。
ぴた、とその場で立ち止まる。同様に、彼女の足音も止んだ。幻太郎がゆっくりと振り返り、無感情な目でを見下ろすも、彼女はにこにこと笑っている。
「なんといっても、今は夢野先生専属の家政婦なので! 先生に頼まれたことならなんでもやりますよー!」
曲げた腕を胸の前に持ってきて、ぐっと両拳を握る。頭の悪そうな言動が目立つのに、頼もしいと思えてしまうのが、どこか不思議な感覚だ。それに、“夢野先生専属”というのも中々に悪くない響きだと思った。……特に深い意味はないが。
口の形が変に歪みそうになるのを抑えて、幻太郎は再び正面を向いて、すたすたと早歩きをする。「え!? スルーですか!?」ばたばたと追いかけてくる彼女に顔を見られないよう、わざとらしく息を吐いた。
「あぁ~寒い寒い。そんな恥ずかしいことを言えるなんて、若いっていいですねえ~」
「私、今そんなに寒いこと言いました!? 先生の影響受けすぎましたかね!?」
「小生が日頃から寒いことばかり言っている人間のように言わないで頂けます? それはさておき、クッキーのお供に温かいほうじ茶が飲みたいです。誰かさんのおかげで体が冷えたので」
「ほうじ茶ですね! あとですぐにお持ちします――って先生やっぱりそれ嘘じゃないじゃないですか!?」
「せんせ~ッ!」後ろから飛んでくる声に、ひとり薄ら笑みを浮かべる。今はまだ……このままでいい。変化を望むよりも、出会った頃から変わらぬ彼女を見ている方が、何倍も心穏やかになる。
はてさて……来年はどんな色の時を刻むのやら。たとえば、娘と過ごす何度目かの春は……そう、彼女がこれから育てるであろう花咲き誇る庭の中で、ふたたび、あの瞬間のように、笑う彼女が見れたらいい、なんて――
「……まあ、嘘ですけどね」