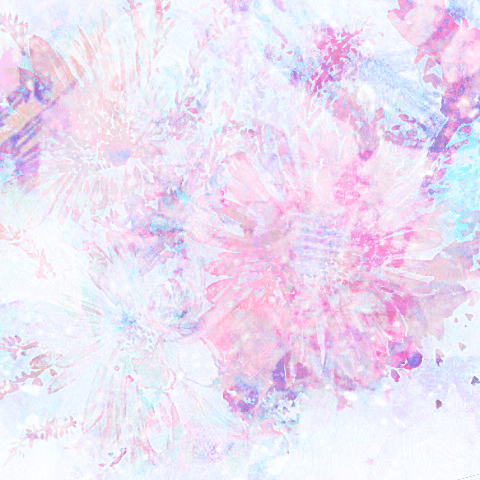Episode.6
小麦色をしたイングリッシュマフィンの上に、分厚いベーコンとポーチドエッグが乗せられ、見た目鮮やかなオランデーズソースがアートのようにかかっている。噂に聞いていただけの流行りの軽食が今自分の目の前にあるわけだが、中々現実味を帯びない。乱数と出会わなければ、こうして対面することも叶わなかっただろう。
ほう、と幻太郎はしげしげと料理を観察する。乱数はインスタに載せるための写真を撮っており、昨日から何も食べていないと言っていた帝統は料理が届いて早々、イングリッシュマフィンの中心をフォークで突き刺して豪快にかぶりついた。この統一性のなさよ。これがJKのグループならば誰か一人はハブられている事態だ。いや、元々はみ出しものが集まって出来たグループと思えば少しは納得がいくだろうか。そうだ、次回作はJK三人組を主軸にした学園ミステリーものに――
「幻太郎~? ゲンタロー? おーいっ」
「早く食べねーと冷めちまうぞ」
「聞こえていますよ」これが職業病というものか。構想を練ろうとした思考は二人の声によって消えた。映える写真を撮らず、かぶりつくこともせず、幻太郎はナイフとフォークを手に取って、ちまちまとそれを食べ始める。うん、まあ、中々の味だ。「エッグベネディクトといえばこのお店みたいだよ~っ!」と乱数が言うだけある。
――エッグベネディクト。聞くところによると、ニューヨーク発祥のモーニングメニューらしいが、どんな因果か、ここ最近の日本で若い女性を中心に名を馳せている。そう……若い女性に。ならば、あの娘も一度は口にしたことがあるのだろうか。彼女ならば、これをどう作るだろう。あの娘の場合、店で食べるよりも自分の手で作った方が時間もお金も節約になるだろう。もしも、うちの代行業として作るのだとしたら、ソースはもっとこう……さっぱりとして口説くはなく、脂っこいベーコンではなく薄いハムを採用してくれるはず。もちろん、彩りのことも考慮して葉物も添えてくれるだろう。頭は緩いが、人の嗜好を見る目が長けている、あの娘ならば――
「幻太郎、本当にいいのかよ」
「なにがです」
「のことだよ」帝統だけでなく、乱数もこちらを見ている。まるでこちらの頭を覗きこんだようなタイミングで話題に出されて、話を流す暇がなかった。仕方なし、と幻太郎は息をついて、ナイフとフォークを皿の端に置いた。
――邪魔と言った。先日、確かに、この口はあの娘にそう言った。そしてなぜか、その日以降彼女はばったりうちに来なくなった。代行業がある曜日が来ても、あの耳につく声が玄関から聞こえてくることもなく、欠勤する旨の連絡すらない。少し言いすぎたと思ってほんのちょっとの謝罪の言葉を用意していた身としては“は?”である。あの娘のことについて悶々と考えていた一日が無駄に終わった。おかけで一つの連載の締切を伸ばす羽目になった。若槻、許すまじ。
こうして月を跨いでも彼女がうちに来る気配はなく、無色になった時間だけが過ぎていく。邪魔と言っただけで本当に来ない奴があるか。こちらから連絡しようか、という最終手段を考えつくほどにらしくもなく思い詰めていたが、自分がこうしている間に、彼女があのヒモ男とひとつ屋根の下にいると思うと、自分の中の糸がプツンと切れた。彼女がそういうつもりならば、といつの日からか気にするのを止めたのだった。
「このあいだも言ったでしょう。彼女とはもう赤の他人です。今頃、同居人という名の同棲相手といちゃついているんじゃないですか」
「オネーさん、彼氏いないって言ってたけどなあ~?」
「乱数がこう言ってるんだぜ。つか、ちゃんとと話したのかよ。幻太郎の早とちりなんじゃねーの?」
帝統のその一言で心が揺らぐくらいには、今回の件は性急だったのではと思っている。それでも、胸の奥から沸き起こってきたものについてはどうしようもなかったのだ。今冷静な頭で考えても、あの時の自分は誰にも止められなかったと自信をもって言える。
「彼女自ら言ったんですよ。同居人が工場勤務からモデルかっこ笑いへ転職。職を変えたら『すっかり頼もしくなっちゃって~』と猫なで声で言っていましたが、どうせ帝統のように定職に就いていないろくでも……こほん、そういう男に決まっています」
「なんでわざわざ俺に例えた? つか今ろくでもねえ男って言おうとしただろ!?」
「他意はありません」目を伏せて、幻太郎は食事を再開する。最初はそうでもなかったが、一口、二口と食べ進めていくうちに舌が拒否反応を起こし始める。なんだこれは。オランデーズソースは過剰に甘ったるいし、ジューシーに仕上げたらしいベーコンは異様に脂っこく、とても塩辛く感じる。卵の色も人工的に色素でも入れたかのような真っ黄色で気持ちが悪い。ああ、もう食べる気が失せてしまった。これはあとで乱数に食べさせるとしよう。
――「これにかぼすを絞ったらルームメイトにすごく好評だったので、先生もお好みでぜひ――」
……嫌なことを思い出してしまった。他の男に食べさせていたものをそのままうちの食卓に出していた、という事実が胸の中をじわじわと汚濁していく。挙句の果てに、ヒモ男が好む味付けを勧めるなどと。かぼすの単語が出てきたときに、確かにかぼすは合いそうだ、と先読みしてしまった自分がとても憎い。顔も名前も知らぬ男と自分が同じ嗜好をしているだなんて、不愉快にも程がある。
怒りを吐き出すように、深く、長く、息をつく。この三年間、彼女がのこした“余計なもの”は多い。無駄に肥えてしまった舌と胃袋、彼女が蒔いた種で色豊かになった中庭、作り置き用に増えた空のタッパー……ごみ箱に捨てられないものばかりで困った。同じ時間、もしくはそれ以上の時間をかけて、じっくり、跡形もなく焼却しなければいけない。その労力は気が遠くなるほど果てしない。他人では到底理解できないものだろう。
……これだから、人と関わるとろくなことがない。だんだん、あの娘のことを考えていたら気分が悪くなってきた。それもこれもすべて若槻のせいだ。幻太郎はフォークとナイフを置いて、外の空気でも吸ってこようかと静かに席を立った。
「――この人、私の友達なんですけどもッ!」
……刹那、不穏な音が流れてくる。
はたとして周りを見渡すと、女性客二人と一人の男が何やら揉めている。どうやら、女性らが男に絡まれているらしい。おまけに、その女性らのうち一人が見覚えのあるこじんまりとした女子で、幻太郎は目を見開いた。
「あれってオネーさんじゃない?」
「おい、なんかやばい空気じゃねえか?」
もう一人の高身長の女性を庇うように、は男と対峙している。なぜ力で適うはずもない男に歯向かうのか。頭が回るならまだしも、口で負かすことができるほど頭がよろしくないのはあの小娘自身が一番分かっているはずだ。頭の隅々まで脳筋なのか。本当に馬鹿じゃないのか。
……いや。もう、知らない。彼女とは無関係だ。赤の他人に施すものなど何もない。もう少し大きな騒ぎになれば、じきに店員がやって来るだろう。自分が何かするまでもない。そう、なにも。金輪際、自分の人生において彼女の存在が介入することはないのだ。
「そっ、そういうのは間に合ってますのでっ!」
苛立ちげに、幻太郎は目を閉じる。あの活発な声が聞こえるだけで煩わしい。視界の端でちょこまかと動いて、頼んでもいない作り置きも勝手に作っては冷蔵庫にぎゅうぎゅうに詰めていく。人の心に土足でずかずかと入り込んだと思ったら、邪魔と言っただけで本当に来なくなった。
――そういうところが、気に食わないのだ。始めから、それはずっと変わりがない。ああ、そうさ。そうだとも。認めてやる。若槻に取り巻くものすべてが気に食わない。彼女に対して素の言葉を紡げない自分自身、察してほしいと願うばかりでいっこうにこちらを見ない。もう、自分の生活の一部として、若槻の存在は深く刻み込まれている。“彼女”がすっぽり抜けた穴からは乾いた風がびゅうびゅうと入ってきて、寒くて敵わない。穴を無視することもできず、同じ形の代用品もない。どんなものでも埋められないのに、分かっているのに……この胸に棲まう臆病者はまた自ら他人を突き放す。
……もしも、もう一度。彼女と言葉を交わせる機会があるのなら。今まさに、娘の纏う空気に触れるが巡ってきているのを見過ごさないだろう。同じ味の過ちは、一度賞味すれば十分だ。着物の袖を翻し、幻太郎は一歩を踏み出す。自身のブーツの音が顕著に聞こえてきて、頭の中がぼうっと靄がかる。そんな中でも、春爛漫と言わんばかりに笑う彼女が桜吹雪のようにちらつくものだから、ああ、これはもう手放せないものなのだと思い知らされた。
「――騒がしいですねえ。あなた、ここがオシャンティーなカフェテラスだということをご存知でないようで」
――それがつい、数時間前のこと。
幻太郎は時計を仰ぎ見て、読みかけの本をぱたん、と閉じる。そして、今しがたインターホンが鳴った玄関へと向かった。訪問者は考えなくとも分かる。時間は指定していないが、偶然にも“いつもの時間”だった。
引き戸を開けると、まるで捨て犬のような佇まいでそこに立っていた。預けている鍵で開ければいいのではと思うだろう。しかしこの娘、あの日のうちにうちの鍵を律儀に机の上に置いていったのだ。それを見た瞬間、頭の神経がブツッと切れたような衝撃が走ったものだが……まあ、それも今となっては過去の話だ。
はこちらの顔を見上げるやいなや、唇をきゅっと結んで、“緊張”の二文字を顔面に貼り付けている。とても分かりやすい。彼女のこういうところが、名も知れぬ情に変わったのはいつの頃だったか。
「……材料は買ってきましたか」
「はいッ」
エコバッグを肩にかけながら、は強く頷く。そしてその右手には、有名求人広告及び人材派遣会社のロゴが大きく印刷された紙袋を携えていた。その中に大量の冊子が入っているのが見て取れる。今日一日の彼女の予定が手に取るように分かってしまい、幻太郎はつきそうになった溜息を寸のところで飲み込んだ。二人の言う通り、彼女が仕事を探しているのは真実らしい。
幻太郎はを家の中に招き入れ、玄関の鍵を閉める。しかし、未だ靴を履いたままぼけっと立ち尽くしている彼女を見て、幻太郎は眉を顰めた。「何やっているんですか。さっさと上がりなさい」そう言うと、「は、はいっ。失礼しますっ」とは裏返った声で返事をし、ようやく靴を脱ぎ始めた。その動作はどことなくぎこちない。
「あ、あのう~……」
「なんです」
「台所、お借りしてもよろしいでしょうか……?」
幻太郎はさらに眉間に皺を寄せる。いつも台所に行く際にわざわざ許可など取らなかっただろう。基本的に自分は自室にいるため、彼女は勝手に家に入り、勝手に台所で作業を始めるのが常だ。……ああ、そういえば、彼女が来たばかりの頃はこうしていちいち聞かれていただろうか。
……すべて、死んでいくのか。この三年間で生まれたものが、あんな、たった一言で。
幻太郎は先程飲み込んだ溜息をついについてしまう。「……その前に、こちらへ」と力なく呟くと、幻太郎は自室に向かって足を伸ばした。控えめな足音が後ろからついてくるのが分かって、じりっと頭の隅が焼け切るような痺れが襲った。未知の感覚だったが、嫌なものではないことは確かだった。
「中へどうぞ」
幻太郎がを自室に招き入れると、彼女は地雷でも埋まっているかのようにそうっと部屋の敷居を跨ぐ。そして、こちらが用意した座布団に正座をして、エコバッグと紙袋を隣に置いた。ああ、あの中にすぐに冷蔵庫に入れなければいけない食材はあっただろうか。まあ、彼女のことだからある時は最初に言うはず。いや、今は状況的に言えるような心持ちではないだろうか――ああもう、考えるのはもう懲り懲りだ。手っ取り早く終わらせよう。
「……このあいだは、少し、言いすぎたところがあります」
「えっ?」
彼女の口から素っ頓狂な声が漏れる。さらには「い、言いすぎたとは……?」と首を傾げる始末。この小娘……人がここまで歩み寄ろうとしているというのにどこまで阿呆なのか。
「邪魔じゃ……ない、です」
「へ?」
「二度は言いません。小生は伝えましたからね」
首から上にかけてひどく熱い。早口で言った後は顔を背けて、視線だけちらりと彼女の方を向ける。すると、さらに首を傾げるが窺えて、ぷちんときた幻太郎は声を張った。
「“夢野先生は若槻のことをいろんな意味で何とも思っていない”ッ! はい復唱!」
「へっ!? ゆっ、夢野先生は若槻のことをいろんな意味で何とも思っていないっ!」
「よろしい」「ええぇぇ……っ?」全く世話のかかる娘である。ひとまず蟠りが解けた(自己解釈)ところで、幻太郎はこほん、と咳払いをした。
「……それで本題ですが。先月から一度も代行に来ないとはどういう了見ですか」
「ど、どういう了見といいますと……?」
「確かに、小生はあなたに対して心ないことは言いました。が、それ以上にあなたは小生と交わした契約があるはずです。一般企業で言うならば無断欠勤ですよ」
「むっ、無断欠勤っ?」
「小生があなたの上司ならば即刻クビにしています」
自らの首に対して、手を垂直に構えてそのまま横に滑らせると「ひえぇッ……!」と声を漏らす。オーバーリアクションなところやこちらの言葉をすぐに真に受ける彼女を見て、少し心が踊る自分がいた。
「……百歩譲って、日数は前よりかは減らして差し上げます。ただし、明日からはきちんと来るように。いいですね」
「えッ!? そっ、それはちょっと難しいです先生ッ!」
立ち膝気味になったがそう物申した。はあ? 人がこれだけ言っているのに何が“難しい”だ。ふざけるな。どうしてここまで伝わらないのか。自分自身も大概上手く言えないことがあるが、ここまで来ると彼女の理解力のなさも原因の一つではないか。
おまけに、「え……? 先生、うちの会社のことご存知でない……?」などと意味の分からないことを言っている。小娘の会社など存じ上げるわけがないだろう。元より、今はもう外れた担当者が勝手に契約した代行会社。幻太郎は若槻という人間性と彼女が作るご飯にしか興味がない。
「……あなたがいなくては、困るんですよ」
「へ」
彼女がうちに来る時間に合わせて執筆のタイムスケジュールを立てている。ライフサイクルも彼女の彼女の代行に合わせてできているし、そもそも、今更自分で夕食の支度をしようと思わない。面倒だ。とても面倒だ。自身で用意できたとしても舌が受けつけない未来が見える。結果的にそうなるくらいなら、彼女が来る前のように、空腹に悶えて廊下で倒れる日々を過ごす方がマシだ。
「あなたのせいで大概のものを食べても“普通”以上の感想を抱かなくなりました。これは一種の味覚障害です。どうしてくれるんですか」
「どっ、どうしてくれると言われましても……。というか先生、私のご飯も大体“普通”とかしか言ってない気が……。言われたとしても茶化しながらしか言われたこと――」
「あなたが作ったものの中に美味しいもの以外ありませんが? なんですかあの至れり尽くせりの家庭料理は。あんなの食べずとも美味しいに決まってるじゃないですか」
「えぇッ!?」
これはバグだ。脳がバグっている。自分のせいじゃない。よって、あとで後悔する必要はない。これはバグなのだから。
それでもはぶるぶると首を横に振る。「そっ、それはぜひとも契約中に言って頂きたかったです……っ」と嬉しいような切ないような微妙な顔をした。だから勝手に契約を切るな。日数は減らすことは許可したものの、こちらは彼女との契約を切った覚えはない。幻太郎の中で、理性の糸が一本焼き切れた。
「何でもかんでも一人で完結しないで頂けますか。迷惑を被っているのは小生なんですが」
「と言われても、もう私にはどうすることもできなくてですねっ――」
「今まで通りあなたがうちに来て夕食と作り置きを作る。これ以外に何かありますか?」
「それがもうできない状況でしてッ」
すす、と心なしかが座布団ごと後退しているように見える。させるものか。幻太郎は咄嗟にの手を掴んだ。「ひっ!?」と彼女が悲鳴を上げる。不審者のような目で僕を見るな。そして逃げようとするな。話はまだ終わっていない。
「小生はあなたに伝えることは伝えましたし、日数も減らしてあげました。これ以上あなたとの契約に対して譲歩するつもりはありません」
「こッ、困ります先生っ! 私もう先生の家政婦じゃないんですよッ!」
「だから勝手に決めるなと言ってるでしょうが! 僕はあなたのことが――ッ」
「会社が倒産したからもう先生のお宅で働けないんですっ!!」
……嫌な沈黙が部屋を満たす。「……はい?」と口から漏れたのは、芯のない声。一方、目の前の彼女は「やっぱり知らなかったんですねぇ……ッ」と絶望的な顔をして見せた。