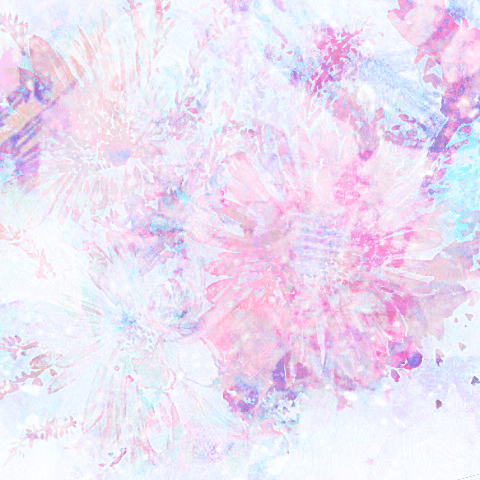Episode.5
日本で古くから伝わる食前の挨拶、箸の使い方、三角食べの所作……すべてがお手本のように整っていて、見ているだけで心洗われる気分だ。
今回の主役である豚肉と白菜の味噌炒めを箸で摘まれた時、は自身の箸を止めて、目の前の摂食行動にじっと見入る。口に運び、ゆっくりと咀嚼してから、こくんと飲み込むまでを見届けた後、目を見開いた彼女がふっと顔を上げた。
「好吃」
「ほんと!?」
「うん」再び主菜に箸を伸ばして、一口食べるルームメイト。お米も一緒に含んで、音を立てずに静かに噛み締めている。ハオチー、だって。やったっ。思わず母国語が出るほど美味と受け取ったは、嬉々として自分の箸も動かす。市販の赤味噌に少し調味料を加えたおかげでさほど口説くない味噌の味に仕上がり、さっと炒めただけの白菜はきちんと食感が残っていて、噛むたびに素材本来の味が豚肉の油と絡み合う。
初めて作ったものだが、なかなかの自信作だ。もご飯が進む。今度の代行の日から作ってみようかな。あっ、そうだ! 赤味噌じゃなくて白味噌使ってちょっとピリ辛に味付けしたら、薄味が好きな先生も食べてくれ――
「(……あ、)」
……そっか。もう、代行業ないんだった
今月から無職の肩書きを背負っている。代行業最終日は、各ご家庭の方々から感謝の気持ちを伝えられ、長くも短かった家政婦業に幕を下ろしたのだった(一人を除く)。
「」しかし結局のところ、契約終了まで職は見つからず、ほぼ一日中家にいて、家事をこなす日々を送っている。代表からは、「会社都合の退職って形になるからねえ~。ま、退職金はこんなもんかな~」と言われ、指定の口座に振り込まれた金額は中々のもので、はATMの前で通帳片手に倒れそうになった。半年くらいは優雅なニート生活をしても問題ない額だ。
「……」それでも、現状に甘えてはいない。仕事は引き続き探しているものの、の掲げる条件に当てはまるものはなかった。長期勤務、シフト制、交通費全額支給――あわよくば調理業がいいが、調理師や栄養管理師の免許がなければ勤務できないところがほとんどで、肩身が狭い思いをしている。
こういった職探しも大事な経験。何もなければ代表の傘下にある事業にお世話になろうと思っていたが、資料を見る限りだと、案の定IT企業や電子系を扱う事務仕事ばかりで、体育会系のは目眩がした。とてもじゃないが、そういう系の会社に勤めるにはハードルが高すぎる。
「」
「へっ!? なにっ? 呼んだっ?」
「呼んでる。ずっと」
「こういうこと、最近多い」なにかあったか、とまで言われてしまい、「えぇ~……?」とは言葉を濁す。ご飯の途中で仕事の……特に、暗くなる話はしたくない。できるだけ美味しく食べてもらいたいからだ。
職探しに対する不安は、ある。それを抜きにしても、の胸中は先日から曇り空のようにどんよりとしている。おまけに、今回の件は完全に自業自得なので、自責の念ももれなく付いていた。
――「……あなたの、言いたいことは分かっています」
……まさか、先生が倒産のこと知ってただなんて
厳密には事業撤退なのだが、代行業ができなくなる意味合いは変わらない。「うぅ~ッ……」幻太郎の発言を思い出して、は呻きながら先日のやり取りを鮮明に思い出す。それもこれも、幻太郎の(の独断と偏見で決めた)好きなものを沢山作り、それを“好むものばかり”だと言われて調子に乗ってしまったのがいけなかったのだろうか。マシンガントークしてしまった自分が自分で恥ずかしくなってしまい、は頭痛がしたように頭を抱えた。
「(もっと、早く言えればよかったなぁ……)」
自分の口から言えたら、何か変わっていたかもしれない。幻太郎が塩対応だったのも、伝えることも伝えず、暢気に代行業を遂行していたのが理由だろう。彼の大切な生活習慣に関わることだったというのに、一体何をしていたのか。代表は、顧客に対する事業撤退についての説明は各従業員に任せると言っていたが、幻太郎が知っているということは、なんだかんだで一部の人間には代表からメールか何かで知らせていたのかもしれない。
「し、仕事のことについてだよ~……」徐々に語尾を小さくしながら、はルームメイトにそう言う。苦し紛れにはぐらかした後、はチェストの上に置いてあるアナログ時計を見た。もう昼過ぎだ。
「……企業説明会、行ってこようかなあ」
「セツメーカイ?」
「うん。大きいホールを貸し切って、そこにいろんな企業さんが集まって、一斉に会社の説明会をやるんだって」
企業説明会――駅中の壁広告に貼られていたのを見て、はなんとなく詳細を調べていた。概要は今言った通りで、百何社の企業があるならば、一つくらいは自分に合う会社があるのではないかと思った。どちらにしろ、家にいても特にやることがないので、人生経験として足を伸ばしてみるのも損ではないだろう。
ああいうところって、スーツで行かないとだめかなあ。ヒールがある靴って、かかと痛くなるからあんまり履きたくないんだよなあ。こんな心持ちで一般企業に就職できるのだろうか。いや無理かな。幸先は不安しかない。
「ご飯食べて、洗い物終わったらすぐ出るよー」そう言って、なんとか話を逸らすことにも成功した。すると、ルームメイトが何か考えるように視線を落とす。そして、何か決意したように顔を上げて、強い眼差しでを見つめた。
「私も行く」
「えっ! 一緒に行ってくれるのっ?」
ルームメイトは静かに頷いた。正直、初めての試みで心細かったので同行者がいてくれるととても心強い。でも、大丈夫かな。人多そうだし疲れないかな。それでも、彼女の好意はとても嬉しいものだ。きっと、落ち込んでいる雰囲気を醸し出す自分を見かねての言葉――
「今のだけだと、心配。変な人にひっかかる。怪しい勧誘、しつこいキャッチー。相手にするの、許さない」
「あぁ~……そっちかぁ~……」
――結果だけ言うと、不作だった。
企業説明会を終えて。紙袋に入った大量のパンフレットを携え、はルームメイトと共にカフェテラスにて小休憩をとっていた。お互いに飲み物と軽食を目の前に置いて、湯気を立てているエッグベネディクトをナイフで切りながら、は深く溜息をついた。
「(めちゃくちゃ人多かった……。難しい話ばっかでほとんどの説明よく分からなかった……)」
目の前にいるルームメイトの顔からも、“疲れた”というメッセージが受け取れる。見目の問題か、本命の自分よりも隣にいる彼女の方が話しかける回数は多かった気がする。途中から面倒になったらしく、「ワタシ、ニホンゴ、ワカリマセン」とわざと片言で話して厄介払いしていた時は、笑いを堪えるのが大変だった。
元々、ああいう場所は社会人としての心得がしっかりしている人が行くようなところなのだと思い知った。皆、企業の担当者が話しているのを熱心に聞いて、メモを取ったり質問をしたりと、とても積極的だった。代行業――しかも、あの緩い代表の下で働いてきたので、余計にギャップが凄まじかった。どうやら、自分が生きていた世界とはまるで違ったようだ。
こうなったら、バイト求人アプリで仕事をひたすら探すしかない。仕事に飽きることのない、色々な人と出会える短期の派遣でもよし、責任に縛られることのない契約でもよし。これ以上の贅沢は言っていられない。は本日、また一つ大人になった気分だ。目に見える収穫はなかったものの、行って損はなかったと胸を張って言える。
「私、水取ってくるけどいるー?」
「うん。ありがとう」
空になった自分のコップとルームメイトのコップを手に取って、は席を立つ。水はセルフで汲んでくるらしいお店のルールに則って、店の中心にあるウォーターサーバーへと向かった。テラスから店内に入ると、入店した時よりも程々に混んできていて、自分くらいの年代の女の子達で満席になっている。出入口前にも、席が空くのを待っているお客さんがたくさんいた。ゆっくり雑談するなら別のお店探さないとな~、と考えながら、はコップをカウンターの上に置いて、レバーを軽く押した。
コップが冷水で満たされる様を眺めながら、は再び思考に浸る。仕事探しはもちろんだが、幻太郎のことがどうしても頭を占める。お世話になった代行先のほとんどは快く別れの挨拶を済ませることができたものの、夢野先生宅だけは喧嘩別れのようになってしまった。数日経った今でも忘れられない。いくら食べて寝ても、幻太郎のことが頭から離れない。
謝るべきだよね……。でも、もう家入れてくれなさそう……。というかもう他人みたいなものだし、思いっきり邪魔って言われちゃったし……。あ、お手紙書こうかな? いや、読む前に破られる気がする。下手したら訴えられそう。でも謝りたいし……うう~ん……。
そうこうしているうちに、二つのコップに水を次ぎ終わってしまった。とりあえず、乱数君と帝統君に相談してみよう。うん……よし、先生のことはひとまず置いておく! 今からはエッグベネディクトの頭にしよう! かちっ、とスイッチを切り替える。並々になったコップを慎重に運びながら、テラスへと移動する。ルームメイトの横顔をさっそく目の前に捉えると、の足も自然と早歩きになった。
「遅くなってごめんね~っ。お水お待た――」
ん?
はぴたりとその場で制止する。見れば、ルームメイトが一人の男と話しているではないか。それにしても珍しい。人付き合いを好まない彼女の知り合いが数少ないのはも知っている。さらによーく見れば、本人の顔の色が“面倒”、“迷惑”、“鬱陶しい”の三コンボときた。さらにさらによく見れば、話しているのは男だけであって、彼女は口を開かずにつん、と顔を逸らしている。
あ、これだめなやつだ。ピンときたは慌ててルームメイトの元へ小走りする。そして、テーブルの前に着くやいなや、ことんッ、わざと音を立てて水を置いた。少し零れてしまったが些細なことだ。
「この人、私の友達なんですけどもッ!」
こういうのは勢いが大事だ。自分はすごく気が強いんだぞ、という暗示をかけながら男に退散願おうとした。すると、「あ、お友達? じゃあ一緒に話聞く? 今彼女に最近流行りの美容系モニターの話をしてて――」となぜか先ほどよりもヒートアップして話し始めた。しかも、座って座って、と言わんばかりに椅子を引かれる。そんな紳士な対応をしてくれるのなら潔く立ち去って頂きたいところであった。
こっ、この人日本語通じないタイプだ……っ! 「そっ、そういうのは間に合ってますのでっ!」が必死にお帰り願おうとしても、男のマシンガントークは止まらない。「あなたと話すことはない。どっか行って」と、ルームメイトがツンドラ気候並の冷徹な眼差しで男を睨みつけても彼は何処吹く風。ちょっとメンタル強すぎるのでは? 周りのお客からの視線も痛くなってきた。
だっ、誰か店員さん呼んで来て~っ! とが心の中で泣きながら訴えた時、どこからか上品な音がこつこつと聞こえてきた。
「――騒がしいですねえ。あなた、ここがオシャンティーなカフェテラスだということをご存知でないようで」
それが靴の音だと分かって、は勢いよく後ろを向く。シブヤの街で、ただ一人しかいないであろう書生の服を着こなす男性。が今会いたい人トップワンに輝く夢野幻太郎先生である。
せっ、先生ぇ!? どうしてここに!? と声を出したかった。願望だけで終わっているのも、今この空気がかなりの修羅場だったためだ。「あなた、どちらさん?」「あそこの席で食事を摂っていた者ですが」傍から見れば冷静かつ大人な対応だが、普段の幻太郎を知っているからすれば、「ひぇ……っ」と声が漏れてしまうほどの気迫である。これはかなりお怒りモードだ。
それから二言三言やり取りを交わすが、どっこいどっこいの攻防戦。ついに相手の男が「あなたには関係ないことですよ」と幻太郎のことを鼻でせせら笑ってしまう。ゆっ、勇気あるなあこの人……!! は見ているだけで胃に穴が開きそうだ。
「無関係ではありません。小生は彼女の雇用主なので」
「へ?」
はぽかんとして幻太郎を見上げる。厳密にはもう先月で契約が切れているので、幻太郎とは知り合いに近い赤の他人のはずである。すると、頭が真っ白になっているに、幻太郎の鋭い眼光が突き刺さった。
「小生は、あなたの、雇用主ですが、なにか?」
「はいッ! 私は彼に雇われていますッ!」
話を合わせろ小娘、と言わんばかりに単語ごとに圧をかけられては即答してしまう。怖いっ! は背筋をぴんと伸ばした。
よろしい、と言わんばかりに幻太郎はこちらを一瞥した後、「そういうことです。怪しげな副業紹介でしたら他を当たっていただけますか」以降、相手の言葉を待たずして、幻太郎の口から言葉の弾丸が撃たれていく。頭の中で国語辞典でも捲っているような凄まじい語彙力……ただ聞いているだけのも身が縮こまる思いだ。
いつの間にか、席を立って隣に逃げてきていたルームメイトが、「この人、だれ」とにこそりと呟く。「代行先の人だよ……」としか現状説明が出来ないため、詳しいことは後にしよう。とりあえず今は、男とバトっている幻太郎に対して、脳内でチアガールのごとくポンポンを振って応援したい気持ちでいっぱいだった。
「オネーさんっ!」
「わあッ!?」
そんな時、後ろからに覆い被さるように抱きついてきたのは乱数だった。そして、その後ろから帝統が「よう!」と陽気に片手を上げて歩いてくる。幻太郎がいる時点でもしかして、とは思っていたが、こんな不意打ちは予想していなかった。
「だ、帝統君も……。もしかして、ここで三人でご飯食べてたの?」
「うんっ。ボクの知り合いのオネーさんが、ここのエッグベネディクトがす~っごくおいしいよって言ってたから、みんなで食べに来たんだ~っ」
「まあ、普通に美味かったけどよ。量が少なかったからあんま食った気しなかったな」
帝統の元も子もない発言に、さすがのは苦笑いをするしかない。一方、男と口論を続けている幻太郎の声が顕著に聞こえてきて、は我に返ったようにあわあわと慌てだした。
「先生、あのままでいいのかなっ? やっぱり店員さん呼んできた方が――っ」
「ん~。だいじょーぶじゃないかなあ? ていうかぁ、ゲンタロー相手に口喧嘩するなんて、あの男の人もおバカさんだねっ★」
「確かに。言えてるわ」
そう言って、顔を見合せた二人が笑い合う。えぇ~……? そんなルーズな感じ……? なんだか一人騒いでいる自分がアウェイな感じだ。さすがは先生のお友達。彼のことをよく分かっている。
少し経って、ようやく男が去っていった(去り際、心配になるくらい顔が真っ青になっていた。一体どんなことを言ったのか)。「気ぃ済んだかよ幻太郎」「ええ」その一方で、夏風を感じるがごとく涼しい顔をしてこちらをすっと見つめる幻太郎。目を合わせようとしたら、これ見よがしにぷいっと顔を逸らされてしまった。や、やっぱり、まだ怒っていらっしゃる……。
「それじゃあっ、ジャマな人もいなくなったことだし~、せっかくだからみんなでご飯食べよっ」
「みんなって……。は明らかにダチ連れだろ」
「えぇ~っ。ダメかなあ? ボク、このきれいなオネーさんともお話したいな~っ」
「あぁッ。乱数ちゃん、この人は――」
いつものノリで乱数が抱きつこうとした時、の後ろにさっ、と身を引いたルームメイト。「あれ~?」と首を傾げる乱数を、彼女はじっと睨みつけている。さっきのこともあってか、警戒心でいっぱいだ。場の空気が冷たい。ま、まずい。なんとかフォローしなきゃっ……!
「この人ねっ、私のルームメイトなのっ。すごーく良い人なんだけどすごーく人見知りだから、抱きつくのはちょっと遠慮してもらえると――っ」
「は?」
声を上げたのはなぜか幻太郎だった。え? とが幻太郎を見るやいなや、乱数と帝統が驚いたように目を見開いた。
「ええ~っ? オネーさんのルームメイトってお――」
「乱数」
「俺みたいに定職就いてねえおと――」
「帝統」
二人の声を遮った幻太郎は口元で裾で押さえ、苦しげに視線を落としている。見るからに戸惑っている様子だ。こんな先生の顔、初めて見た。がぼんやりと幻太郎を見つめていると、現実に戻ってきたらしい彼は唐突にスマホを取り出して、すっ、すっ、とスクリーンに指を滑らせた。
なんだろう……。先生にしては珍行動が多い気がする。「でもでも、ほんとびっくりしたよ~! オネーさんが幻太郎の家政婦さん辞めちゃうなんて~っ」「もう幻太郎の家で飯作んねーのか?」が固唾を呑んで幻太郎を見守っている中、とてもデリケートなことになっている件について、二人にズバズバと突っ込まれてしまう。幻太郎がスマホに集中していることを切に願って、「あ、あはは~……」とは笑って誤魔化した。
すると、「。スマホ、光ってる」とルームメイトに耳打ちをされる。あ、ほんとだ。乱数と帝統がわいのわいのと話しているうちに、はこそっとスマホを手に取った。どうやら、普段あまり使わないSMSの新規メッセージの通知のようだ。
「えッ」
「どうかしたか?」
「なっ、なんでもないよ~っ」帝統の問いかけをはぐらかして、はメッセージの送り主を一瞥するも、彼はつん、と明後日の方を向いている。……その手にスマホを持ちながら。
そ、そっか。先生、私の電話番号知ってるからSMSでもやり取りできるよね。びっくりしたぁ~……。それにしても、こんなに近くにいるのになぜメッセージを送るのだろうか。誤送信であることを祈りながらがおそるおそる画面を開くと、絵文字も何もない短文が目の前に飛び込んできた。
――今夜、一食分作れる食材を持ってうちに来なさい。品目は後で送ります。食材を買った分のお金もお支払いします
ん!? は無言で目を見開く。メッセージと幻太郎を交互に見ても、彼は相変わらず涼しい顔をしている。さらに、幻太郎は再びスマホを操作し始めたかと思えば、手を止めて、またそっぽを向く。するとじきに、のSMSの画面に新しいメッセージが追加された。
――来なければあなたの秘密をこの場でバラします
「(ひッ、秘密っ!?)」
な、なんだろう。先生に何か話したつもりはないのに、“何かあるのでは”と疑ってしまうこの気持ち
今ここで聞いてしまいたいが、なにせ秘密の事柄。ルームメイトもいる前でどんな秘密を暴露されるのか……考えただけで鳥肌が立ってしまう。もはや脅迫に近いが、背に腹はかえられぬというやつである。それにご飯を作るだけでこの危機を逃れられるなら安いものだ。
迷うことなく、は“了解しました”と打って、送信。すると、画面をちらりと見ただけの幻太郎は、どことなく満足気な表情をして、スマホをそのまま懐に仕舞いこんだ。
「……さて、二人とも。そろそろお暇しましょうか。女人らの会合を邪魔してはいけませんよ」
「え~っ。ボク、まだまだお話したいのに~っ」
「俺も追加して何か食いてえー」
「乱数はあとで適当に女性とお話しするなりナンパするなりしてください。帝統も、ここではあなたの胃袋に見合うものはないので、他の店に入りましょう」
「ほら、行きますよ」先陣を切って店内へと戻って行った幻太郎を追うように、二人がその後に続く。「またねオネーさんっ」「じゃーなー~」二人に向かって力なく手を振りながら、は幻太郎が握っているらしい自身の秘密の正体について考えていた。
「ねーねー……」
「なに?」
「私の秘密って、なんだと思う……?」
突然問いかけられたルームメイトは一考して、「……最近、体重が増えたこと」と言う。それは代行業が終わってからのバカ食いのせいである。それに、それは彼女にしか言っていないことだ。やはり、幻太郎本人に聞くしかない。
せっかく幻太郎と会える機会が巡ってきたというのに、さらに不安要素が増えてしまった。献立を考える必要がないのが唯一の救いだろうか。幻太郎から品目が送られてくるその時まで、彼に自身の秘密を話す自分がいなかったか、は追憶の旅に没頭したのだった。