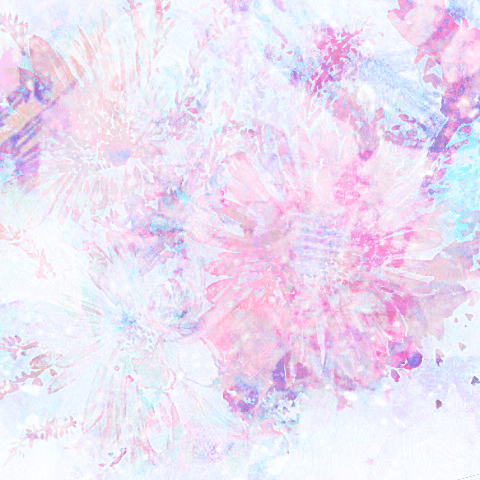Episode.4
「(……遅い)」
かれこれ数時間近く、原稿と壁時計を行き来している目線。この空腹を我慢するにもそろそろ限度があるというもの。時刻はすでに十八時を回っている。この時間ならば、この部屋まで夕ご飯の匂いがしてくる頃合だというのに、うちの家政婦は台所に踏み入れるどころか玄関の戸すら未だ開けていなかった。
一体どこで油を売っている。彼女が時間通りに来ない日など今まで一度もなかった。家に来る前に買い物を済ませてくるので、もしや買い出し先で何か厄介事に――と、そう思ったところで、幻太郎ははたと思い出す。
「(今日は……来ない曜日か)」
すとん、と胸に落ちてきた事実を飲み込むと、体から力が抜けていく。先々週に契約内容を変更したというのに未だ慣れない。なにが厄介事だ。馬鹿馬鹿しい。厄介事どころか、今頃彼女は同居人である駄目男と同じ食卓を囲んで、楽しく――
「(……くそ)」
邪念を振り払うように、幻太郎は自室を出た。一人のときならば適当に外食をするか家にあるものを適当に摘む程度で済ませるが、この口はすでにの手料理の口になっている。あの小娘め……家にいない時でさえ人の心にズケズケと入り込んで図々しい。自業自得と分かっていても、怒りの矛先が彼女へいってしまうのも必然である。理不尽です先生! と訴えるの間抜け顔を思い浮かべると、幾分と怒りも収まった。
……いや、彼女のことはもういい。忘れよう。それよりも、今はこの空腹をなんとかしなければ。たしか、彼女が作り置いてくれていたものがあったはずだ。そう思って台所に向かうと、ちょうどいいタイミングでインターホンが鳴った。
「やっほ~ゲンタロ~っ! オネーさんのご飯食べに来たよ~っ!」
「天かすでもなんでもいいから何か食わせてくれ~ッ!」
――忘れよう、と思った矢先にこれだ。
玄関にて迎えたのは、きゃぴるんっ、と満面の笑顔を貼りつけている乱数。その隣にいるのは、割と本気で死相が現れている不健康そうな帝統。おおよそ、腹を空かせた帝統が乱数のところに転がり込んで、さらに乱数が邸宅に行こうと誘ったのだろう。……彼女の手料理目当てに。
ないことはない……だが、家にある作り置きは一人分。自分とて空腹な上に“なんでもいい”と言った帝統に分けてやる手料理はない。そんな彼にはあとでお金を握らせることにしよう。
「あいにくですが、本日彼女はお休みです」
「げッ。マジかよ! 一昨日の夜から何も食ってなかったからだけが頼りだったってのに~ッ」
「おや、この間は小生達に焼肉を奢ってくれたくらい珍しく羽振りがよかったじゃないですか。もう使い切ってしまったんですか」
「ご名答」
そんな決め顔をされても何もかっこよくですよ。幻太郎は冷ややかな眼差しで帝統を見つめる。「なーなー。何か作り置きとかもねえのかよ~」「今朝のうちに食べ切りました」嘘である。悪いが帝統に食べさせるほどの余裕はこちらにないのだ。つーん、と顔を逸らした幻太郎が財布を出そうと懐に手を伸ばしたその時。今まで傍観していた乱数がこてん、とあざとく首を傾げた。
「じゃあ、みんなでマック行く?」
すでに三個目のハンバーガーに齧りついている帝統を正面に、乱数の横でポテトを摘む幻太郎。本来であれば、カロリーと脂質の塊であるファストフードではなく、頭の緩そうな彼女なりに栄養バランスを考えた食事を口に入れる予定だった。この舌も不服そうにポテトの味を噛み締めている。そのわりに、ポテトに伸びる手はまるで止まらないのだから不本意極まりない。
「ええ~っ! オネーさんって、幻太郎の家に毎日来てるんじゃないのっ?」
「違いますよ」
「ボクらが行く時はいつもいたよー?」
「たまたまでしょう。帝統、バンズの下からソースが零れそうですよ」
「んぐッ」子供のようにハンバーガーを食べる帝統を窘めながら、幻太郎は淡々と言う。そもそも、そのことに関しては、以前に帝統から同じ質問を受けた気がするのだが。乱数は両手の上に顎を乗せながら、「ふぅ~ん?」と分かっているような分かっていないような声を漏らした。そして時折、その金魚のような小さな手でチキンナゲットを摘んではぱくぱくと食べている。
「そーいえば、お仕事だいじょーぶだった?」
「今は比較的落ち着いていますけど、なぜですか」
「このあいだ、オネーさんと会ったとき、幻太郎がぴりぴりしてる~って言ってたから、いそがしいのかな~って思っただけだよ★」
ぴりぴり――あの彼女が使いそうな緩い語彙だ。乱数が言っていることも偽りでないことが分かる。というかいつ会った。最初に彼女と出会ったのは自分だというのに、いつの間にか乱数と帝統とも打ち解けているのがなんとも解せない気分だ。……いや、乱数はフェミニストなところがあるし、帝統とも同年ということで接点があるので、仲が良くなるまでの時間が短いのも理解できないこともない。しかし、それに比べて自分はどうだ。三年以上の付き合いになるのに、心の内を明かすほどの仲ではない。あくまで、あちらのビジネスの上で成り立っている関係だ。
……まあ、別に、どうでもいいことですけど。沼にはまりそうになった思考を軽くあしらって、幻太郎もチキンナゲットをひとつ摘んだ。
「わたくしはぴりぴりなどしておりませぬ。前世では自由が許されなかった囚われの姫……。本日も、心穏やかに第二の生を謳歌しておりますわ」
「ふぁ~ふぁふぃふぃふぁふぁんへーほほひーははっへ」
「帝統様~。お口の中が何もなくなってからお話ししましょうね~」
「“まーた意味分かんねえこといいやがって”、だって★」
いやなぜ分かる。幻太郎は、帝統が口の中のものを飲み込んだのをじっとりとした目で見届ける。「すげえな乱数!」「だーってポッセだもんっ」私もあなた方のポッセなんですが――そう言いそうになった口に、ポテトをさっさと放った。「そういやあ」
「のやつ、なんか仕事探してるって言ってなかったか?」
「あ~! 言ってた言ってた~! だからボク、ゲンタローにお給料上げてもらえば? って言ったんだけど、お金のことは会社が決めてるからって断られちゃったんだよね~」
「はい?」幻太郎は訝しげな顔をして首を微かに傾ける。それは初耳だ。しかし、連日見られたあの憂いた表情はお金のことを考えていたと言われれば納得がいく。
お金の工面に困っている、と。それはそうだ。自分以外に同居――いや、もう同棲でいい。同棲しているヒモ男を養っているのだから、困るのは当然だ。モデルの仕事を始めたと言っていたが、本当かも分からない。仮に真実だったとしても、駆け出しのモデルなどそうすぐにまとまったお金は入らないだろう。笑顔と料理と元気しか取り柄のない小娘のお荷物にしかならない存在……これを機にさっさと別れてしまえばいい。
「オネーさん、ゲンタローの家政婦さん、やめちゃうのかなあ? えーんっ、そしたらオネーさんに会えなくなっちゃうよぉ~っ」
「がいなくなったら、幻太郎の家行ってもの飯食えねえなー」
「あなたたち、小生の家をキャバクラもしくは定食屋か何かと勘違いしていませんか」
ただ、乱数の言ったことは一理ある。お金に困っているのならば、職を変えるというのが手っ取り早い。代行業を辞める可能性もあるだろう。自分が彼女へ支払っている額の何割が彼女自身の賃金になるかは知らないが、さほど多くはないはず。シブヤは広い。彼女に見合った、もっと稼ぎの良い職場があるにちがいない。
「幻太郎はさみしくないの?」
「何がですか」
「オネーさんがいなくなっちゃったら」
「困りはしますね。生活習慣が乱れるので。しかしまあ、それも最初だけでしょう。慣れてしまえばどうということはありません」
「お前に人の心はねえのかよッ」
「ワタクシ、ツイ数年前マデはロボットだったモノデ」片言で話してはぐらかそうとすると、帝統は両腕を組んで、なにやら悶々と考え出した。ここまで神妙な顔をする彼は賭け事をしている時くらいしか見ない。正直似合わない。どうせ今も、取るに足らないことを考えているのだろう。
「俺が思うに……」
「いいですよ思わなくて。帝統が言うことなどろくなこと――」
「幻太郎はに対する日頃の感謝が足りねえ!」
ぎくりと肩が震えそうになるのを耐える。幸いにも、そんな幻太郎の様子に気づいていない帝統は言葉を続けた。
「飯の有り難さは俺もよく分かる。腹が減って仕方ねえ時、米一粒貰えるだけで天からの恵みなんじゃねえかと思う。週に二回くらいのペースで、俺はそれを身をもって知っている」
「有難みを感じる場面はもっと多いのでは?」
「むしろ週に二回ご飯が食べれるって感じだよね~っ」
「話の腰を折るんじゃねえよっ!」
わっと言ううちの末子にはいはい、と幻太郎は軽くあしらった。「まあ要するにだ」
「が辞めちまうかもしれねえなら、自分が思ってることは素直に伝えた方がいいだろ? あんな美味い飯作ってもらっといてよ。ありがとうとか美味いとか、なんでもいいから言ってみろよ。もきっと喜ぶぜ」
「アリガトゥー? ウマーイ?」
「日本語覚えたばっかの外人みたいになってんぞ」
「演技です」そう誤魔化して、幻太郎は動揺を隠す。実際は、帝統にごもっともなことを言われて言葉が詰まっていた。「さっすがだいすぅ~! 感謝の気持ちは大切だよねっ」乱数に至っては便乗しているだけで本当にそう思っているかは怪しいところだが――まあ、今は置いておく。幻太郎とて非情な人間ではない。お金を払っているとはいえ、彼女に対する感謝の気持ちはある。しかし、あちらは仕事できているのだからそんなものを押し付けられても面倒ではないか。「まーたややこしいこと考えてそうだな」「あっはは~★」
……まあ、食材に対して、という意味なら、言ってやらないことは、なくもないですけど。
台所から聞こえてくる音が煩わしいと思わなくなったのはいつからだろう。気がついたら、慣れ親しんだ生活音の一部となっていて、ひとたび耳に入れたら集中力が穏やかにふつんと切れて、空腹を自覚する。おかげで、彼女が来てから廊下に倒れる日は少なくなった。
台所と廊下を繋ぐ暖簾の向こう側から、調理音と混じって家政婦の溜息が聞こえる。そして本日からは「うぅ~ん……」という唸り声も増えている。幻太郎は、そんな家政婦の奏でる音を暖簾越しに耳を澄ませていた。
――「ありがとうとか美味いとか、なんでもいいから言ってみろよ」
が喜ぶ――いや、それはいい。あの帝統にああまで言われては、幻太郎も重い腰を上げるというもの。あれからも、「今まで素で飯の感想言ったことねえのかよ……」と帝統に幻滅されるなどして、幻太郎の評価は右肩下がりである。そもそも、彼女への印象はマイナスからのスタートだったのだ。茶化さずに感謝の気持ちなど伝えるタイミングがあったら教えてほしい。そう思っていたら、「この“ボク”でも、オネーさんのご飯は美味しいって分かるのになあ~」と、クローンである乱数にそんなことを言われて、幻太郎の心に深く刺さった。悪意がないのを分かっているからこその痛みである。
さて、そんなマックでのやり取り後。本日は最初の代行日――午後から執筆が手につかず、彼女が来るなり部屋から出て、こうして台所の前で作業音を立ち聞きするくらいには、幻太郎の思考はの平和ボケした顔で満たされている。……というのは嘘で、少し根詰めすぎたので、冷やかしにきただけだ。そう思って数十分経とうとする頃だが、幻太郎は未だ台所の敷居を跨いでいない。
そもそも、ここ最近は彼女の顔すらろくに見れていない。会話もしていない。代行業が終わればとっとと帰らせる日が続いていた。そんなよそ行きの態度をしておいて、今更何を言えと――
「わあッ!?」
そんな、刹那のことだ。パリンッ! と甲高い音が聞こえて、はっとした幻太郎は性急に暖簾を潜った。見れば、床に落ちた陶器の破片と、その前に跪いている。彼女は絶望の眼差しで割れた食器を見下ろしていた。
「やっ、やっちゃったぁ~……ッ」苦しげな声を漏らしながら、素手で破片を拾い集めようとする。馬鹿か。幻太郎がその手を掴むと、ばっと顔を上げたと目が合う。自分を視界に捉えるやいなや、みるみるうちに彼女は破顔していった。
「せっ、先生ッ……」
「掃除機を持ってきます」
「大丈夫ですよっ! 私が――ッ」
「そこにゴム手袋があるので、あなたは大きな破片だけ拾っておいてください」
の言葉を無視して、幻太郎は物置に置いてあった掃除機を引っ張って来る。台所に戻ってきた頃には、ゴム手袋を装着したが大きな破片を拾い集めた後だった。幻太郎も彼女に続いて割れた陶器の後処理をし終えると、すっかりしおらしくなってしまったがこちらを見上げた。
「先生、すみませんでした……」
「お気になさらず。同じような食器はまだありますから」
彼女の手元を見ながら幻太郎は答える。ひとまず怪我がないことを確認してから、机の上を見る。するとそこには、出来上がったばかりで湯気を立てている料理が所狭しと並んでいて、その量の多さに思わず目を見開いた。
肉じゃが、生姜焼き、ししゃもの天ぷら、ほうれん草の胡麻和え、茄子の煮浸し、金平ごぼう――この三年間の総結集と言わんばかりに、今まで食卓に出た料理がずらりと並んでいる。それも、幻太郎の舌を躍らせたものばかり。もちろん、作り置き用のタッパーも机の隅に山積みになって置かれている。これで三、四日は持つのではないかと思えるほどの量だ。
これらを、この短時間で作ったというのか。切って焼いて煮て揚げる音は確かにしていたが、それよりも溜息をついたり呻いたりする回数の方が多かったではないか。僕の心配を返せ。
「今夜は、随分と豪勢ですね」
「あ、あはは……。考え事してたら手が勝手に動いちゃって……」
ちらほらと視線が動いている。何か思うことがあってのことだろうが――でなければあんな露骨な態度には出ない――今はそんなことはどうでもよかった。
「……小生が、好んでいるものばかりです」
ほら、これでいいんだろう
言ってやった、と満足気に息をつく幻太郎。“好んでいる”と“美味しい”はほぼ同意義だろう。こちらとて子供ではない。その気になれば食事の感想くらいぽんと言えるのだ。舐めないで頂きたい。
一方、(幻太郎としては大告白のつもりで言った)その言葉を聞いて、ノーコメントでただぽかんとしている。なんだその顔は、と突っ込んでやろうと思ったその時、彼女の纏う雰囲気にぱちぱちっと火花が散っていっているのが分かった。これはまずい。幻太郎は、爆弾処理の際に間違った配線を切ってしまった人のような気持ちになった。
「ほんとですかッ!?」
「うッ……るさ……」
「よかったです~っ! 先生がお好きかどうか全然分からなかったんですけど、見た感じ箸の進みがよかったものばっかなので、わたしが勝手に先生の好きなものリストに入れてたんですよ~っ!」
幻太郎は片耳を抑えながら、の口から弾丸のように向かってくる言葉を受け止める。工作で作ったものを褒められた子供のようにはしゃいでいるを一瞥して、ぐぬ、と幻太郎は密かに顔を顰めた。
先生の好きなもの、せんせいのすきなもの、すきなもの――ええいうるさいうるさい。いつまでも木霊している声を振り払って、幻太郎はふん、とそっぽを向く。それでもスイッチの入ったの口ははわいのわいのと止まることを知らない。久々にこんなにも彼女の声を聞く。笑っているのを見る。先程まで空腹だったというのに、あと一時間くらいなら我慢できるまでには胸が満たされた。
……煩い。が、まあ、もうしばらくは、このままでいいか。ふと、幻太郎が机を見ると、中央から逸れたところに、見たことのない料理が置かれていることに気づく。それをじっと見ていると、「それはれんこんの磯辺揚げですよ~!」と視線に気づいたが言った。なぜこういうところだけ聡いんですかあなたは。
「食べてみてお口に合ったら、作り置き用にも取っておきますねっ」
「……ええ。お願いします」
「あっ! あと、これにかぼすを絞ったらルームメイトにすごく好評だったので、先生もお好みでぜひ――」
ぴく、と指先が震える。の声が徐々に遠ざかっていって、晴れやかになりつつあった心が一瞬で荒んでいく。にこにこと話している彼女の顔は、梅雨の日の太陽のように焦がれていたはずだったのに、その笑顔の先にいる見知らぬ男のことを思うと――なんだろう、この、途方もない不快感は。
――「オネーさん、ゲンタローの家政婦さん、やめちゃうのかなあ? えーんっ、そしたらオネーさんに会えなくなっちゃうよぉ~っ」
――「がいなくなったら、幻太郎の家行ってもの飯食えねえなー」
ぐるぐるぐるぐる。二人の言葉が頭の中で回ると同時に、彼女の不可解な言動の数々を思い出す。
――「作家さんって、部類的にはやっぱり自営業になるんですかねっ?」
――「最近すっかり頼もしくなっちゃって、今まで色々と教えてた私も頭が上がらないんですー」
――「こッ、今月から少し日数を減らして頂けないかと……っ!!」
――「これにかぼすを絞ったらルームメイトにすごく好評だったので、先生もお好みでぜひ――」
……るーむ、めいと
途端に、吐き気が込み上げてきて、幻太郎は口元を抑える。目の前に広がる料理に目が痛くなって、匂いを嗅ぐだけで胃がむかむかとしてきた。
「せ、先生っ?」不安げな声を漏らすをきっと睨みつけると、彼女が声を詰まらせたのが分かった。自分の一言動にいちいち反応する彼女が至極愉快だった時期もあったが、今後、そんなこともないだろう。
「……あなたの、言いたいことは分かっています」
一日もの間、水分を取っていないような掠れ声で幻太郎は言う。はたとしたは察しがついたように、表情がぼろりと崩れていった。
「せ、先生、もしかして……ご存知だったんですか……?」
「これだけ匂わせるような言動が目立てば、馬鹿でも分かります」
「これが、最後の晩餐ということでしょう」吐き捨てるようにそう言うと、は勢いよく首を横にぶんぶんと振った。「まっ、まだっ、まだ大丈夫ですッ」
「今まで言えなくてすみませんでした……ッ。今月いっぱいまでは代行業も続けられますしっ、月末になったら代表から詳しいお話ができると思うのでッ」
「いいです。結構です。今夜で家事代行は最後にしましょう」
もう声すら聞きたくなくて、幻太郎はを無理矢理押しやって台所を出ようとする。これだけ作ったんだ。もう仕事は終わっただろう。早く自分の家に帰ればいい。女に縋ってしか生きることができない、どうしようもない男がいる家に、さっさと帰るがいい。そしてその男に自分が食べたものと同じ料理を出してやるんだろう。心底不愉快極まりない。
に背を向けると、「まっ、待ってください先生ッ」と彼女の足音ともに必死めいた声が聞こえる。彼女のすべてが煩わしいと思うのに、自分を引き止める声になけなしの欲が顔を出してしまい、幻太郎は僅かに振り返ってしまった。
「わたしっ、まだ先生にして差しあげたいことが――っ!」
「ああ、鈍感なあなたには分かりませんか」
その欲を握り潰すように、幻太郎は彼女の声を打ち消した。どいつもこいつも、無作法で、非常識で、身勝手だ。人の中に土足で入り込んできて、頼んでもいないのにやいのやいのと構ってきて、ようやくこちらが茶を出そうかと腰を上げたところで、目の前から去っていく。結局、自分は“そういう”星の下で生まれたのだ。いくら味わっても学習しない自分に嫌気がさした。
「邪魔だと言ってるんですよ。あなたが」
心許した者が目の前から去っていく痛みを味わうのは……もう御免だ。