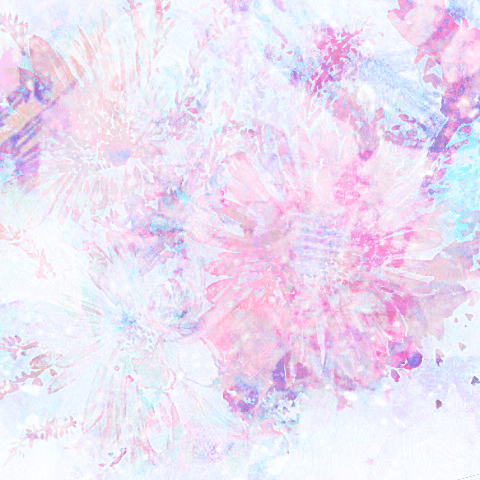Episode.3
シブヤの街を転々としてから早数時間。求人情報が載っている掲示板やハローワークを見て回ったり、興味がてら調理専門学校のオープンキャンパスに参加したりと、ほどほどに充実した一日だったが、これといっての直感にぴんとくるものはなかった。
「(どうしようかなあ……)」
は街中のベンチに座りながら、ワゴン販売していたタピオカミルクティーをじゅッと飲む。うぅ~ん、おいしい。最近、タピオカの流行も落ち着いてきたのか、ようやく買いやすくなってきたこの頃。手軽にタピオカを味わうことができて、も満足している。嗜好品をあまり持たないルームメイトの口にも合うようで、今度家でも作ってみようかと思うほどだ。
流行りものはちょっと遅れて乗ったくらいがちょうどいいなあ――タピオカをもぐもぐと咀嚼しながら、は太口ストローから口を離す。事前に計画していた予定はすべて消化しきったので、これからどうしようかなあ、と考える。すると不意に、の頭上に濃い人影が生まれた。
「オネーさんっ」
「わあッ!?」
後ろから何者かの手が両肩に置かれ、思わず体が飛び跳ねた。タピオカを口に含んでいなくてよかった。
驚いた勢いのまま後ろを振り向くと、馴染み深いゆめかわカラーが目の前に飛び込んできて、はほっと胸を撫で下ろした。
「な、なあんだ~。乱数君かあ~っ」
「あっはは~★ ボクだよっ」
偶然ここを通りがかったらしい乱数はにっこり笑う。そして、口に含んでいたキャンディーをいったん取り出して、の隣にすとんっと座った。
「なんだか後ろ姿が元気なさそうだったから、声かけてみたんだよね~っ」という的を射すぎた彼の言葉に、の肩がぎくりと震えた。
実はうちの会社が近々倒産するから、代わりのお仕事探してるんだよね~――なんてヘビーなことを言えるわけもなく。「えっ、えーっと~……そのぅ……」しどろもどろになりながらも、は当たり障りのない言葉を懸命に選んだ。
「ふっ、副職を探してて……」
「副職? オネーさん、お金足りないの?」
「足りないというか、将来的に足りなくなるというか……」
あはは、とは愛想笑いをして、場の空気を濁す。乱数の、ただでさえくりっとした丸い目がさらに丸くなったかと思えば、ふむふむ、と彼は両腕を組んで何かを思案し始めた。えっ、急にどうしちゃったの。
「ら、らむだくーん……?」がおそるおそる呼びかけてみると、じきに乱数がこちらに向かってにっこりと笑んだ。「ちょうどよかった~!」えっ、なにごと。
「ねえねえオネーさんっ。今から時間あるかなあ?」
「え? う、うん。すごくあるけど……どうして?」
「えへへ~。まだヒミツだよっ★」
しぃっ、と唇の前に人差し指を立てて、ぱちんとウインクをする乱数はまるでアイドルだ。かっ、かわいい~っ! 完全にハートを射抜かれてしまったは、乱数に見惚れながら再びストローに口つける。甘さは“ふつう”にしたはずなのに、先ほど飲んだよりも味が濃厚なくらい甘くなっているような気がした。
到着した先は、乱数の事務所だった。事務所の中にある一つ一つの物に統一感はないが、それがむしろ乱数らしさを醸し出していて、インテリアのバランスとしてはほど良い塩梅になっていた。
さすがはデザイナーだあ~――はそんなことをぼんやりと思いながら、部屋の中心にあるソファーに目をやる。あっ、とが声を上げるよりも早く、そこに座っていた深緑のコートの主がふっと顔を上げた。「おっ!」
「じゃねーか!」
「帝統君~!」
「いぇーい!」「うぇーい!」はソファーの傍に駆け寄るなり、帝統と軽快なハイタッチをする。同い年のノリがすっかり定着してしまって、今ではこれが彼との恒例挨拶となっていた。もちろん、幻太郎の目がないところに限るが。
「も乱数のところで日雇いバイトしにきたのか?」
「バイト?」
「あ~っ! 帝統ダメだよ~っ。ここに来るまでヒミツにしておいたのに~っ」
ぷんぷん、と怒ったように両手を腰に当てる乱数。はて、とが首を傾げていると、彼はその場でくるくると回りながらこう言った。
「近いうちにボクの個展があるんだよっ」
「へえ~! すごいね乱数君!」
「えっへんっ」胸を張る乱数を見て、可愛いなあ、とは再度思う。「それでぇ」
「オネーさんにもその準備を手伝ってほしいなあって思ったんだ~! もちろんお金はちゃんと払うよ!」
「なるほどー。だからバイトかあ~」
「そーそ~! それで今、帝統にも同じようなことしてもらってるんだよね~っ」
「乱数の助っ人になれて、オレも賭場代を稼げる……これぞまさしく一石二鳥ってな!」
こちらに向かって親指を立て、満面の笑みを浮かべる帝統。彼の前には、英字のタグがびっしりと並んでいる大判の紙が大量に積まれている。おそらく、乱数が所有しているメーカの名前が印字されているのだろう。それを切り取り線に沿って、ハサミで地道に切っているようだ。賭場という言葉がなければ最高にかっこいい台詞なのだが、どうも締まらないところがまた彼らしい。
お金が関わらずとも、貸す手はいくらでもある。そういうことであれば! とがさっそくソファーに座ろうとすると、「オネーさんはこっちこっちっ」と乱数に手を引っ張られた。あれれ、あれれえ……?
乱数に導かれるがまま通されたのは、先程いた部屋の隣。乱数のアトリエらしきそこで、は一人ぽつんと立たされている。その横では、鼻歌を歌っている乱数が小型メジャーを手に取っていた。
「オネーさんの体のサイズ、ちょっとだけ図らせてねっ」
「えッ!?」
「そんな固くならなくてもだいじょーぶ! 服の下からでオッケーだよ★」
いやそういうことではなく――が口を開く前に、乱数の持つメジャーがしゅッと鋭い音を立てた。「モデルを頼んでたオネーさんが急に来れなくなっちゃってね~。オネーさんがちょーど同じスタイルで良かったよ~っ」なるほどなるほどそういうことかあ――じゃなくて私の昨日の夕ご飯焼肉だったんですが!? こんなことならうどんとか煮麺とかにしておけばよかった。は背筋をぴんと伸ばして、お腹にきゅッと力を込めた。せいぜい足掻きにしかならなくても、やらないよりはマシだと祈って。
乱数はメジャーを器用に操りながら、の胴や腕、その他の部位の長さを測っていく。腕を上げて、足を上げて、と彼に指示をされるがまま、は四肢を動かしていく。一つの部位を測り終えた後、乱数は手元のスマホでその数値を黙々と打っていく。うぅん、さすがは乱数君。お仕事モードはすごく真剣だ。「というかぁ、」
「お金が足りないならゲンタローに相談したら?」
「へ?」
突如振られた話題に、の頭が真っ白になる。目の前の乱数は依然としてにこにこと笑んでいた。
「だって、オネーさんはゲンタローに雇われてるんだよね? お金増やして~っておねがいすればいいんじゃない?」
「そ、そんな簡単には……。料金形態はうちの会社が決めてることだから、そういうのは勝手に変えちゃだめなんだよー……」
「えー。そうなのー?」手の動きを緩めずに応答する乱数に向かって、は小さく頷いた。「それに……」
「先生、今ちょっとぴりぴりしてるから……」
「ぴりぴり? 書いてる原稿の締切が近いとか?」
「うーん。どうなんだろうねえ……」
いつからだろう。いつにも増して幻太郎の無表情が増えたのは。それに、食後の雑談タイムもなくなった。それどころか、後片付けが終わるやいなや、「家に帰らなくていいんですか」と彼から言われる始末だ。
採寸されながら、はもやもやと考える。自分の知らないところで失言をしてしまっただろうか、何か口に合わないものがあっただろうか――いくら時を遡って言動を振り返っても、に心当たりのある節はない。あったらとっくに謝罪している。業務は通常通りこなせているので、表面上問題はないが、ここまで態度があからさまだと、さすがに気になって夜も眠れない。
……いや、そもそもの問題として。
「(早いとこ、先生に契約解除のこと言わないとなあ……)」
来月まで時間がない。このままずるずると引きずってしまっては、月末なんてあっという間に来てしまう。幻太郎が塩対応に戻ってしまったことはいったん頭の隅に置いておいて、今は自分がやらなければならないことに目を向けなければ。
……まあ、それができるのであれば、こんなにも苦労はしていないのだが。溜息をついたらなんとやら。はそれを寸のところで飲み込むと、ちょうど足の長さを測っていた乱数とぱちんと目が合った。上目遣いでにこっと微笑まれて、の体がぴしりと固まる。ううっ、か、可愛い……。
「早くお仕事見つかるといいねっ」
「え? あ、う、うんっ」
「いいお仕事があったら、オネーさんに紹介してあげるから、ボクのことはいつでも頼ってくれていーからね★」
「はいっ。採寸おーわりっ」メジャーを仕舞う乱数を横目に捉えて、は体の力をふっと抜く。息を吸って、数秒止めて、はあっと吐き出す。考えてばかりじゃダメだ。この手足も、口も、ちゃんと動かさないと。
今日こそは、ちゃんと言おう。先生の好物(と勝手に思っているもの)をたくさん作ろう。それで彼のご機嫌が取れるとは思っていないが、少しは話しやすくなるための舞台準備だ。なにせ、たった数秒でK.O.してしまいそうは絶対零度の眼差しを直に浴びるのだ。それくらいは盾として構えておきたい。は打たれ強いがそれなりにチキンなのである。
「よしっ」が拳をつくって心意気込むと、「オネーさんがんばって~!」と乱数の応援の声が届く。おそらく彼が思っていることと意味は異なっているが、それでも嬉しいものは嬉しいので、「うんっ! 頑張る!」とは活気よく応えたのだった。
現在、幻太郎との契約は週四ということだけあって、彼と会うスパンはとても短い。言うことを頭で整理する時間はなかったが、為せば成る――時には勢いだけで突っ込んで吉と出る時もあるだろう。
現在、は机を挟んで、幻太郎の正面で箸を握っている。ここ最近はお通夜のような晩御飯の時間を過ごしていたが、今日は手によりをかけてご飯を作ったおかげで、幻太郎の表情も幾分か穏やか――のように見えるだけかもしれないが、それでも、話すチャンスは今しかないと思った。
「あっ、あのッ!」
幻太郎の箸の動きが僅かに止まる。一瞬だけ目をこちらに配ってくれたが、彼はすぐに食事に戻ってしまった。さも興味ないです、と言わんばかりの対応に、の心はさっそく折れそうだ。うぐぐ、めげるな私……!
「いっ、いまお話してもいいでしょうかっ!」
「手短にお願いします」
返事してくれた! よかった! 目は相変わらず合わないままだが、それでもは言葉を続けた。
「私の契約のことなんですけど――」
「なにか」
ようやく幻太郎と目が合ったが、思っていた以上に彼の視線が冷たいものだったので、の体は瞬時に萎縮した。ひ、ひええぇッ……! 見ているだけで凍ってしまいそうだ。
……いや、ここで逃げちゃだめだ。言え、言うんだ私。今月末で契約解除になるのでご承知おき願います、と……! あわよくば、本日の秋刀魚のにしん焼きのお味はいかがでしょうか、と……!!
「こっ……」
「こ?」
「こッ、今月から少し日数を減らして頂けないかと……っ!!」
言えない! 言えるわけがない!!
だってめちゃくちゃ不機嫌そうなんだもん! というかよく考えてみたら先生は食べ物で機嫌が左右されるようなお人じゃないよ! 言えたとしても、幻太郎の口から不平不満が飛び出すのは必至。お小言パラダイスならまだ耐えられるが、“そんな身勝手な理由で小生の生活リズムを変えろと?”などとごもっともなことを言われてしまっては、も畳の上に額を擦りつけて謝ることしかできない。
まあ、今も似たようなことを言ってしまったが。あっちゃあ~、と頭を抱えたくなる失態だ。案の定、幻太郎の眉がこれでもかと顰められて、は二重の意味でやってしまったと後悔する。しばらく沈黙がその場を支配したが、幻太郎は俯きながらぼそりと言った。
「……まぁ、ほぼ毎日来ていますしね。あなた」
「あ、あはは~……」
はもう愛想笑いしかできない。しかし、意外にも幻太郎は「……分かりました。それで、減らす曜日は」と尋ねてきたのでは目を見開いて驚いた。い、いいんですか? と聞きたくなってしまったが、早く言え、と幻太郎の眼差しがびしびしと訴えていたので、は言われたがままに適当な曜日を口にする。すると、了承、と言わんばかりに押し黙ってしまい、幻太郎は静かに手を合わせた。
「あ、あれ? 先生、もういいんですか?」
「ええ。ご馳走様でした。残りは朝に食べるので冷蔵庫に入れておいてください」
は机に置かれた皿達を見る。おかずも副菜も半分くらい残っている。なんだかんだでいつも完食してくれるので気づかなかったが、残されることはこれが初めてかもしれない。じくり、と胸の中に黒いシミのようなものが生まれて、は本能的に見て見ぬふりをした。作りすぎたんだ、きっとそうだ、とポジティブな思考に切り替えた。
「ああ、そうだ」自室に向かう幻太郎の足が止まり、こちらを振り向く。なんでもいいから、彼の言葉が欲しい。そんな期待に胸を膨らませたが、彼の眼差しの色は先程と何も変わっていなかった。
「家の錠はそのままで結構です。やることが終わったら勝手に出ていって構いませんので」
業務、お疲れ様でした
そう言って、幻太郎は居間を後にすた。残されたのはと湯気を立てなくなった夕ご飯。これは、まるで、最初に会った頃のようだ。塩対応以上のやり取りのこれが、前までは普通だった。数年前に戻っただけなのに、なんだろう。この胸は、とても、もやもやしている。
は、残り僅かになった白米をなんとか口に含んで、手を合わせた。お米の甘みがまったく感じられなくて、とてもかなしくなる。ラップ、かけておかなきゃ。かちゃかちゃ、と虚しく聞こえる食器の音が部屋に溶けて、は唇をきゅっと結んだ。