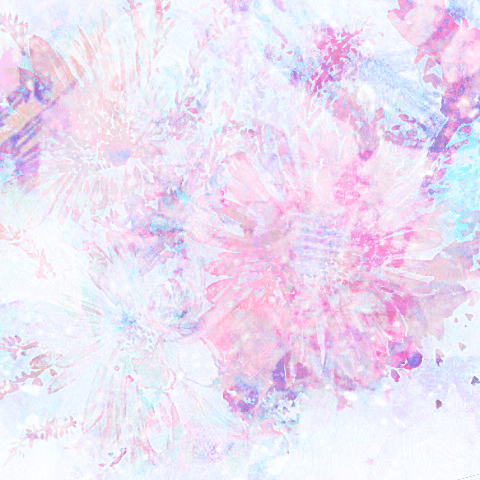Episode.2
最近、うちの家政婦の様子がおかしい。
溜息をついたり、ぼーっとしたり――それでも、労働のための手足はいつも通りしゃかしゃかと動いている。違和感しかない彼女の挙動に、さすがの幻太郎も自らが創作している世界から戻ってこざるを得なかった。オブラートに包まないで言うのなら、“気味が悪い”の一言に尽きる。
それでもまあ、家政婦らしく仕事はしっかりこなしているので、自分が生活する上で特に問題はない――ないのだが。
「(……あぁ、またか)」
ペン先を長いこと一点に置いていたせいで、紙の上にインク溜まりができてしまった。幻太郎は溜息をついて、もう使えなくなってしまった原稿用紙を机の上から下ろした。今日一日で原稿用紙を駄目にした枚数など数えきれない。それもこれも、すべてはあの小娘のせいだ。
他の人間ならば無視を決め込むところだが、今回はこちらの締切がかかっている。特例として、幻太郎は効率を重視することにした。原稿用紙代と自分の手間賃諸々を考慮しても、天秤が傾くのは前者。あの脳天気な彼女のことだ。どうせ、溜息をつく理由も大したことではないのだろう。となれば、早急に片をつけるのが得策だ。
さて、幻太郎は仕事場である自室を離れ、今しがた来訪した家政婦のいる台所へ向かった。
「はあぁぁ……」
ほら、今まさに
幻太郎は家の柱に背を預けて、の重々しい溜息を聞く。今年の春でかれこれ三年の付き合いになったが、彼女がこれほど肩を落としているところなど、今まで一度も見たことがなかった。
そもそも、「先生は秋といえばなんの秋ですかー?」「そんな分かりきった質問よりも、私は食欲以外のあなたの秋を是非聞きたいですね」「うっ……」などという会話を、つい先日にしたばかりだ。まさか憂いの秋か。あの活発系元気っこ娘が? ないない。
ふむ、と幻太郎は一考する。聞こえてくる包丁さばきはいつもと変わらず。ただ、溜息の頻度がひどい。この数日の間、彼女の身の回りで何かが起こったことは明白だった。
「――もし。そこな娘」
ついに、幻太郎は動く。暖簾をめくって姿を現すと、の視線がこちらに刺さった。まな板から目を離した彼女は目を丸くして、大層驚いている様子だ。
そういえば、自分がこうして台所に顔を出すことは少ない……いや、そもそもなかったか。まあ、そんなことも今は些事だ。幻太郎は先ほどと同じく柱に背を預けながら、に向かって淡々と言葉を紡いだ。
「そんな大きな溜息をつかないでくれますか」
「えッ。もしかして、聞こえてました……?」
とりあえず、溜息をついている自覚はあるらしい。本当に世話の焼ける、と幻太郎は続けて口を開いた。
「聞こえているも何も、この家に来てから数分おきにしているじゃないですか。耳に入ってくるこっちの身としては不愉快なのでやめて頂きたいのですが」
すらすらと動く口。語尾まで言ってから、舌先が痺れたように動かなくなった。なんとなく思い描いていたものと違うことを言っている気がして、幻太郎は一人眉を顰める。なんなんだこれは。
「すっ、すみませんッ」思考に耽ろうとする前に、の口から謝罪の言葉が飛び出した。謝らせたいわけじゃない。こちらはただ、溜息をついている理由を言えと言っているだけだ。どうやら、ありもしないことばかり言ってきたこの口は、幻太郎が思っているよりも扱いづらくなっているらしい。
……何を、どう言えば伝わる。言葉はいっこうに思いつかないのに、元の場所に引き返すほどの度量も残っていない。にっちもさっちも、というやつで、の口が再び開くまで、幻太郎は足の裏に根っこが生えたようにその場から動けずにいた。
いつもよりも量の少ない白米と巻繊汁。それらをちまちまと食べているは、食欲も失せてしまっているらしい。幻太郎は箸を動かしつつ、本人に気づかれないように彼女を観察しながら、悶々と考え事をする。
「(なんなんだ)」
どれだけ考えても答えは見つからないまま。実は、とそちらから切り出してくれたらいいものの、先刻の小娘ときたら、「せっ、先生って作家さんですよねっ?」などと、この期に及んで意味不明なことを尋ねる始末。さらにこちらが問いつめても、彼女は焦ったように視線を泳がせて――
――「なっ、なんでもないですよ~! 本当にただ聞いてみたかっただけなので!」
……若槻のくせに、生意気な
幻太郎は器に入っていた巻繊汁を空にして、静かに手を合わせる。「あっ、おそまつさまでしたっ」正面から聞こえてくる声を他所にぽいっと放って、幻太郎は明後日の方を見ながらこほん、とわざとらしく咳払いをした。
「わらわは今、無性に面白い話が聞きたいのでおじゃる~」
「へ?」
が首を傾げる。「お話なら、先生の方が得意なのでは……?」と言う彼女の言葉は最もだ。しかし、幻太郎の狙いはそこではない。
「たまにはそちからの話を聞きたいのでおじゃ~」
「ええっ。私、先生がこのあいだ話してくれた『サルカニ合戦のもうひとつの物語』、楽しみにしてたんですが……! 実はサルをマインドコントロールしていたおばあちゃんが真の悪者で、カニとその仲間たちが力を合わせてサルを助けるっていうお話は――」
「続きを考えるのに飽きたので未完結ということで」
「一番気になる終わり方!!」
「ほれほれ~。早く話すがよい~」
「ええぇっ」と焦燥帯びた声を漏らす。一方、幻太郎は頭を悩ませ始めた彼女をじっと見つめる。若槻がこの夢野幻太郎に隠し事をするなど一万年早いのだ。三度生まれ直してから出直してくるがいい。「あっ!」
「最近、私のルームメイトが転職したんですよ!」
「ルームメイト?」
思いもしなかった単語に、今度は幻太郎が首を傾げる番だった。
「あなた、そんな人がいたんですね」
「あれ? 話してませんでしたっけ?」
「ええ」
思えば、とプライベートな話はあまりしない。あくまで彼女は契約者なので、そこのところの線切りはしているのだろうか。会話そのものはプライバシーも何もない距離感で、むしろこちらから身を引いているくらいだが。しかし、彼女の方がこちらのプライベート空間に踏み込んでいるのだから、それはそれで不公平ではないだろうか、と今更なことを思った。
「それでですねっ」の溌剌とした声に、幻太郎は我に返る。今まで神妙な顔だったが、ようやく笑いながら嬉々と話し始めた。とくん、と強く脈打った心臓は不整脈として片付けた。
「私のルームメイト、今まであまり環境がよろしくないところで働いてたんですけど、すごーく良いお仕事を変えたら雰囲気もがらっと変わって――あっ、元々スタイルも顔も整ってる人なんですけどっ」
幻太郎は彼女の……見知らぬ同居人の像を思い浮かべる。今のところ、見目が整っている人間としか情報がなく、全体像はモザイクがかかったままだ。
「それで……その同居人とやらは元々どこで働いていたんですか」
「工場です!」
「転職後は?」
「モデルです!」
「職種が違いすぎませんか」
「道でスカウトされたみたいなんですよ~」そう言って、にこにこと誇らしげに笑う。下手をすれば、その同居人は騙されている可能性も無きにしも非ずでは――幻太郎ならばそう不審がるところだが、彼女の辞書に疑う、もしくは類似した言葉は基本的に載っていないのだろう。よくもまあ、そんな価値観で今まで生きてこられたものだ。幻太郎は感服する他ない。
「それでですね~。最近すっかり頼もしくなっちゃって、今まで色々と教えてた私も頭が上がらないんですー」
「へぇ……。それで?」
「え? それだけですけど……。あんまり面白くなかったですかね?」
“ですかね?”じゃない。そんな嬉しい話があるはずのお前はなんで溜息をつくんだ
全くもって意味が分からない。ここまできたら、溜息を耐えることの方が大した労力にならないのではと幻太郎は思った。時間だけを浪費してしまい、今度は自分の中に悩みの種ができてしまいそうだ。
それにしても――
「(頼もしい……ねぇ)」
ルームメイト、元工場勤務――どうしても、ほんの少し社会的にまともになった帝統のような人物しか思い浮かばない。悠長な彼女のことだ。そんな人間でも、今まで許容していたのだろう。同居人というくらいなのだから生活費諸々も折半と思っていたが、その職歴からすると彼女の方が多く払っていたのかもしれない。要は、ヒモ男に近い身分なわけで。
――ヒモ“男”?
「(……ああ、)」
成程。すとん、と胸に落ちてきたものがあって、幻太郎はゆっくりと息を吐く。が溜息をつく理由――他人と、ましてや異性と同じ屋根の下で暮らしているのなら……それは、そうだ。誰かと生活をしていく中で、楽しさの他にも憂うことだって、多々あるだろう。
「先生? もう食器片しちゃって大丈夫ですか? せんせー?」彼女の声が遠ざかっていく。そもそも、なぜその可能性を今まで考えなかったのか。週の内の半分以上、夕食時に同じ食卓を囲んでいることを驕っていたのか、それとも、知らず知らずのうちに彼女の有り様にこちらが溺れすぎていたのか。
……彼女の業務終了まで、あと数十分。この家から出て、が帰るべき場所に戻った後。彼女が、自分には見せたことのない一面を他の男に見せているのかと思うと、毒すら吐きたくなるような嫌悪感で全身が満たされた。