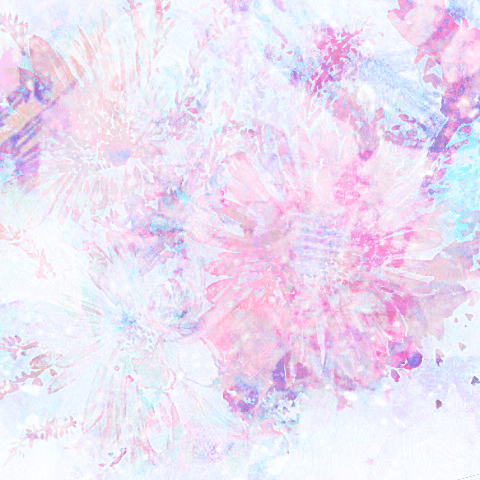Episode.1
とある日の昼下がり。小さなアパートの一室にて、の声が盛大に響き渡った。
「えぇッ!? 倒産ですかっ!?」
コーヒーを飲んでいたルームメイトがこちらを振り向いたことにも気づかないくらい、は電話の奥の相手に集中していた。相手は、が勤めている家事代行会社の代表である。
《いやあ~。あはは~。やっちゃったぜ☆》
「いややっちゃったぜじゃないですよッ」
「これからどうするんですかっ? 代表、たしかお子さん生まれたばっかりですよねっ?」比較的若手の部類に入る彼には、新婚の奥さんと生後何ヶ月かの子供がいたはず。そんな幸せ絶頂期になりつつある時に倒産などと――家庭崩壊待ったなしの修羅場がの脳裏に過ぎった。
《僕はだいじょぶだいじょぶ~。倒産っていうのも半分ジョークだし。なくなるのはちゃんが勤めてる事業所だけ。僕、他にも色々やってるところあるから会社自体は存続するよ。だからまあ、今回の場合は事業撤退とも言うかなー》
「は、はあ……」
《てか、ちゃんこそどうするの? 来月から職なしだよ?》
「あっ」は思わず声を漏らす。そうだ、問題はそこだ。とりあえず、メンタル的にも問題なさそうな代表のことは置いておいて、はこの数秒でお先真っ暗になってしまった自身の将来について考えた。
元より、社会的に大層な地位に就かなくてもいいと思っているので、職に対しては寛容に探すつもりだ。ただ、収入ゼロの月があっては困るので、倒産……否、事業撤退する来月までには、働き口を探さなくてはいけない。
うわあぁ~……と身の毛がよだつ不安がを襲う。そこに、《まあ、そこも心配しなくておっけ~》と代表の軽い口調が聞こえてきて、は我に返った。
《今回の件は僕の責任だし、スタッフのアフターケアもちゃんとするよ~。ほとんどの人は僕が今展開してる事業に中途で入ってもらうことになってるけど……ちゃんはどうする? 僕のとこに来る?》
はい、と言ってしまいそうになった衝動をは飲み込んだ。代表の甘い言葉に上手く頷けない自分がいたのだ。時間に猶予はないものの、脇目も振らずに決めなければいけないほど切羽詰まってもいない。それに、代表の言う事業というのがどういうものか分からない以上、二つ返事でほいほいついていくわけにもいかないのだ。IT系や事務系であれば、は白旗を上げざるを得ない。日常生活で使わない横文字にはとことん弱いのである。
よって、今この電話で今後の選択肢を狭めることもない。ふう、と心を落ち着けたは穏やかな声色でこう言った。
「ちょっとだけ、一人で考えてみます」
《りょーかーい。とりあえず、ちゃんの家に他の事業所の資料だけは送っとくね~。話聞いてみたいとかあったら電話ちょーだい》
「はい。ありがとうございます」そう言って、最後まで軽いノリだった代表との通話を切る。は深い溜息と共に、先ほどルームメイトが淹れてくれたコーヒーを一口飲む。ぬるい。すっかり冷めてしまったそれを温めようと、は重くなった足で電子レンジの前までとぼとぼと向かった。
「。どうかしたの」
同じリビングにいたルームメイトの優しい声に、はうぅっ、と緩みそうになった涙腺をぐっと締めた。
「私、来月から職なしになっちゃう……」
「ショク……ナシ?」
おそらく、今まで聞いたことのない言葉だろう。しかし、しばらく一考した彼女はすぐさま意味を理解したらしく、「仕事、辞めるの? トーサンって?」と尋ねてきた。
はコーヒーを温めている間、ルームメイトに先ほどの電話の内容を簡潔に説明する。すると、彼女は「そう、」とだけ言って、目を伏せた。
「は、やりたい仕事はないの」
「そうなんだよ~……。私、バカだから事務仕事とかできないし、料理と掃除くらいしか取り柄ないし……」
自分で言っていて恥ずかしいのだが事実だ。学校の授業でも、体育や家庭科などの副教科以外の科目で下の中以上になったことはない。生きてさえいれば万事オッケーな精神で今までもこれからも生きていくつもりだった。
やっぱり資格とか取った方がいいのかなあ。でも、そういう学校とか行くのにもたくさんお金かかるよなあ……。そんなことを悶々と考えていると、「、」とルームメイトから再度声がかかった。
「急がなくても、ゆっくり考えればいいと思う」
「ありがとう~。でも、来月までにはなんとか決めるようにするねっ。生活費とか全部折半だし――」
「いざとなったら、私がのことを養うから安心していい」
ルームメイトはさらりととんでもない発言をしてから、二杯目のコーヒーを淹れるためにシンクへ向かった。が目をまん丸にして見つめても、彼女は涼しい顔をして、ドリッパーを片手にてきぱきとコーヒーの粉を入れていく。
転職してからというもの、ルームメイトがとても頼もしく見える。というか、養うなんて難しい言葉、どこで覚えてくるんだろう……。
ピピッ、と鳴った電子レンジからはコーヒーを取り出して、湯気の立ったそれを一口含む。「あっつぅ!」熱しすぎたらしく、さっそく舌の先端を火傷してしまう。幸先は不穏な気配しかしなかった。
「はあぁぁ……」
代表との通話から数日後。は癖になってしまった溜息を今日も吐く。ここまで自分の将来のことを考えたことがあっただろうか。高校の進路調査でさえ、ものの数分で書いて提出したというのに。
ここしばらく、仕事について寝る間も惜しんで頭を回しているものの、あまり良い考えは浮かばなかった。父に相談しようかとも思ったが、あまり心配をかけたくない欲求が勝って、結局言えずじまいだ。
……はあ。玉ねぎをザクザクと切りながらも、将来のことで頭はいっぱいだ。ちなみに、本日のメインはスタミナたっぷりの豚丼。ひじきの煮物とけんちん汁を添えて、この家の主に召し上がって頂く献立だ。
「――もし。そこな小娘」
はたとする。玉ねぎを切り終えたが顔を上げると、そこには暖簾を捲り、家の柱にもたれかかっている家の主こと幻太郎がいた。文庫本を片手に、こちらをじっとりとした目で見つめている。
「そんな大きな溜息をつかないでくれますか」
「えッ。もしかして、聞こえてました……?」
「聞こえているも何も、この家に来てから数分おきにしているじゃないですか。耳に入ってくるこっちの身としては不愉快なのでやめて頂きたいのですが」
「すっ、すみませんッ」
やってしまった。そうだ、今の自分は業務中。仕事はしっかりしないと。これからのことは後回し。は気分を入れ替えて、今目の前にある調理に集中する。
……ただ、横から気配を感じる。いつもなら台所を横切るだけの幻太郎がなかなか立ち去らない。な、何か用でもあるのかな。先生って、今晩のご飯はあらかじめ知っておきたい人だったっけ? でも今の今まで言ったことないし、出したものはちゃんと完食してくれるし……。
気まずさが頂点に達した時、は幻太郎の方に首をぎゅんっと傾けた。
「せっ、先生って作家さんですよねっ?」
「は?」
幻太郎の顔と声色で、とりあえず言葉を間違えたということは分かった。
怪訝そうな顔をした幻太郎は「……そうですが」と冷たく言う。よかった答えてくれたああぁぁ……。それだけでもの心は救われる。彼の機嫌がよくて助かった。その調子で、は差し障りのない言葉で会話を続ける。
「作家さんって、部類的にはやっぱり自営業になるんですかねっ?」
「まあ……そうですね。ただ、小生のようにフリーで執筆している人間の他に、一つの出版社に属している人もいますよ」
「そういう人は社員扱いになるところもありますので、一概には言えませんが」とも付け足す。「へえ~っ」今まで知らなかった世界に、思わず感嘆の声が漏れた。と同時に、はさらに頭を悩ませる。一瞬、フリー家政婦というものをやってみようかと思ったが、手続きが難しそうなのはもちろん、こんな子供同然の歳の人間に一般家庭から依頼が入るとは思えなかった。
「……それで?」
「へ?」
「突然小生に変なことを聞いて、何の訳も話さないというのも不公平では?」
ぎくぅっ、と肩を震わせる。「えっ、え~っとぉ……」は視線を泳がせて、誤魔化すための言葉を生み出す時間を稼ぐ。このたび事業撤退のために来月から事実上退職となります――雇い主である幻太郎にもいつかは言わなければならないことだが、まだ心の準備ができていない。それに、みるみるうちに幻太郎の目が厳しいものになっていくので、言うのならもう少しご機嫌な時に言いたいというのが本音だった。
「なっ、なんでもないですよ~! 本当にただ聞いてみたかっただけなので!」
誰の目から見ても嘘だと分かる。しかし、にできることといえばこのくらいしかなかった。はあはは~、と乾いた笑いで誤魔化して、彼から視線を離し、手元に集中する。問い詰められたらどうしようかと思ったが、しばらくここに留まっていた幻太郎は、足袋を滑らせて台所を去っていった。
た、たすかったぁ~……。はほっと胸を撫で下ろす。しかし、ボロが出るのも時間の問題。早いところ次の仕事を決めて、彼の生活に支障をきたさないようにしなければいけない。は今現在、週四で夢野宅の夕食の調理代行を担っている。それができなくなった時、彼の生活習慣に少なからず変化はあるだろうから。
ひとまず、プライベートな考え事はここまで。指を切ったらまた先生にご迷惑がかかってしまう。そう思ったは、けんちん汁の具材を無心でざくざくと切っていった。