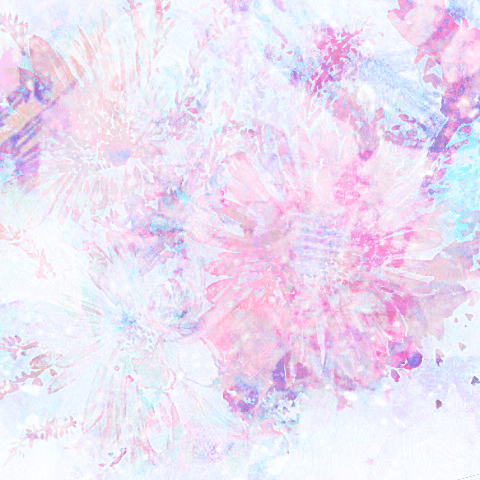Episode.7
卯月をしらせる鳥の声。年度始め早々、夢野先生宅で早朝の家事代行を臨時で任された。アラームよりも早く起床し、清々しい朝を迎えた。幻太郎のお宅にお邪魔するのは日常のはずだが、時間帯が少し変わっただけで、の心は新しくできたスーパーに行く時のように浮き足立っていた。
太陽が登ったばかりの頃に幻太郎宅に訪問するのは久々だった。あれはそう、いつぞやの冬に幻太郎が風邪を引いた時以来だろうか。あの時は、大作を脱稿して気が抜けたらしく、インフルではなかったものの、布団と一体化している幻太郎の姿は見ているだけで辛そうだった。
数週間前に大胆な絡み酒をしてしまい、次の訪問日には身構えて出勤したものの、寛容な幻太郎は(小言が数割増す以外は)いつも通りで、の土下座も受け入れてくれた。どれだけ酔っ払っていないと思っていても、お酒は二杯までとは心に固く誓った。
さて、本日は昼からメディアの取材があるとかで家を出る幻太郎のために、は朝食に精のつくものを振舞おうと思っていた。
――「お昼のお弁当はいりますか?」
――「そんなもの、先方から出るに決まってるでしょう」
――「そうですかぁ……」
――「……でもまあ、どうしても作りたいと言うのなら食べてあげてもよろしくてよ?」
せっかくだから作って差し上げたかったのになあ――そう思っていたら、結果的に夢野姫から許可を頂いて、は嬉々として頷いたのだった。
幻太郎の好物(と勝手に思っているもの)を意識するとどうしても野菜に偏るので、は思索に思索を重ねる。たしか、豚ひき肉があったからいり卵と一緒に二色丼にして、おまけにミニハンバーグでも作ろうか。お弁当入るかなあ、と思いつつ、の手はてきぱきと動いている。
そして出来たのが重箱サイズのランチフルコース。外見はおせち料理であるが、中身は幻太郎のお気に入り(と勝手に思っているもの)しか入れていない。宝石箱や~とか言ってくれるかな。いやないかな。ちなみに重箱はが持参したものである。
余ったものはそのまま朝ごはんに回すのが定石だが、それだとネタバレになって面白くない。朝ごはんは朝ごはんで作ってしまおう。今の時刻は七時過ぎ。朝ごはんは八時からとのことだったので、今からフライパンを振るえば二、三品くらいは作れるだろう。
品目は質素だが、味噌汁と目玉焼き、そこに沢庵を添えることにした。幻太郎に聞くところによると、朝はあまり胃にものが入らないらしい。重たいものは控えつつ、栄養バランス重視した献立だ。
は味噌汁の具を素早く切って、沸騰した水に投入。具材が煮える間に卵焼きに取りかかろうとして、あれボウルってどこにあったっけ、とは首を傾げる。そして、台所の上にある棚に目がいった。普段使わないものは、大体あの中に眠っている。
「よい、しょっ……と」
がたがたッ、と忙しなく椅子を持ってきたは、その上にひょいと乗ってふんぬと棚を開ける。つま先がぷるぷると震える中、不幸なことに、それは一番奥に仕舞ってあった。なんということだ。
は背伸びをしながら、銀色フォルムに懸命に手を伸ばす。しかし届かない。低身長はこれだから。この際適当なお皿でもいいかと思ったが、ここまで来て妥協をするのもなんだか悲しい。普段は皆無に近いのプライドは、かなりどうでもいいところで発揮される。
全身の筋という筋がボウルを求めて伸びきっていると、背後からひたひたと足音が聞こえてきた。
「……何やってるんですか」
もう冬は過ぎたというのに、聞き覚えのある声はかなりひややかだった。ひえっ、との背筋に霜が降りる。
はいったん背伸びを止めて、萎んだ花のようにしなしなと椅子の上で膝を抱えた。振り向くと、案の定、書生姿の幻太郎がいた。
「お、おはようございます先生っ。もしかして起こしちゃいましたか?」
「いえ、あなたが来る前に起きていたので。……それで、何をやってるかと聞いてるんですが」
「あ……。えっと、棚の上にあるボウルを取りたくて……」
「あらあら~。おチビさんにはちょっと難しかったかしらねえ~」
「うぐ……」
「……そこ、いったん退いてくれますか」「えっ」椅子の前まで来た幻太郎が、しゃがんだをじっとを見下ろす。幻太郎の言う通りにして、はいそいそと椅子から降りると、幻太郎は袴をちょいと摘んで椅子の上に乗り、お目当てのボウルをひょいと取った。それをそのままぽん、との手のひらの上に置く。鏡のようにボウルの底に自分の顔が映るのを見たは、ぱあっと顔を綻ばせた。
「ありがとうございます先生……!!」
「今度から、上のものを取るときは呼んでくれます? あなたが無理して取ろうとすればどうせ転倒するでしょうし、その度に小生が救急車を呼ばなくてはならなくなるじゃないですか」
「そ、そんなことは……っ。というか先生、だいたいお部屋に篭ってますし、お仕事の邪魔してしまったら申し訳ないし――」
「仕事なんてしてませんよ。合間休憩ばかりで本を読んでいます」
「そうなんですか!?」
じゃあどうして締切間近になると缶詰になるのだろうか。もしかして先生、優等生に見えて夏休みの宿題は後半に一気にやるタイプだったのかな。も三日前でひいひい言うタイプだった。
完全無欠だと思っていた幻太郎に少しだけ親近感が湧いて、むふ、と笑う。しかし、すぐさま幻太郎生に絶対零度の眼差しできっと睨まれたのですぐ真顔に戻った。
それにしても――相性を考えると、幻太郎にとってのような人間は天敵の部類に入りそうだが、まさかこうして契約三年目を迎えるとは思わなかった。
最初の頃は、幻太郎に話しかけてもつんとした態度ばかりで一時はどうなることかと思ったが、去年の春くらいから幻太郎とのコミュニケーションが取りやすくなった。
その理由も含めて、未だ、幻太郎については謎が多い。口を開けば嘘ですよと語尾につくことが多いので、彼の言葉はどこまで信じていいのか、線引きが難しい。長くも短い時間の中で、が見てきた夢野幻太郎はまだほんの一部分に過ぎないということなのだろう。
感慨深いとはまさにこのこと。がくふ、と再び笑うと、幻太郎は怪訝そうに顔をしかめた。
「さっきから人の顔を見て笑う失礼な顔はこれですか?」
「いッ、ふぁッ……!?」
幻太郎の細い指でぐでーん、と両頬を摘まれる。ほ、頬の肉ついてるのがバレてしまう……!!「お~お~。餅のようによく伸びるお肉じゃの~」「ふぐううぅぅ……ッ!」幻太郎はおそらく手加減という言葉を知らない。止めようにも、この期に及んで幻太郎の両腕に触れていいか迷ってしまい、の手は幻太郎の腕付近でうろうろと彷徨うしかなかった。地味に強い力で左右に引っ張られ、は涙目になりながら、拙い言葉で許しを乞うた。
幻太郎の指から解放される頃には、両頬はひりひりと痺れて痛かった。愛の鞭だとポジティブに受け取るにしても痛い。おまけに、幻太郎はふん、と顔を逸らしてしまう。あ、なんだろう。胸も痛い。がえぐえぐと半泣き状態になって両頬をさすっていると、幻太郎は机に置いた重箱に気づいて、すっと目を細めた。
「……こんなもの、うちにありましたか」
「え? あ、いえっ。重箱は私の家から持参しました」
「なぜ重箱なんですか。一人でこんなにも食べられませんよ」
「あれ? 今回は帝統君と乱数君はいないんですか?」
ディビジョンラップバトルの取材ではなく本職の取材だっただろうか。でも乱数君から『今日はポッセのみんなとインタビュー受けるんだあ~ε٩(๑>ω<)۶з 雑誌が発売されたらオネーサンも読んでくれたら、ボクとっても嬉しいなっ(っ*’ω`с)☆☆』ってLINEきたし……。三人でシェアしてくれたら嬉しいなという思いもあってこの量にしたのだが、勘違いだったのだろうか。
があれえ、と眉をひそめると、明らかに幻太郎の態度が変わって、むすっとした顔になる。あ、これ不機嫌な時によくする顔だ。
「重箱なんて持っていくのに手間じゃないですか。これをお昼まで小生が持ち歩けと言うんですか」
「あ……。そっ、そうですよねっ。すみません気が利かなくて……! 先生の好きなもの……というか、私の独断と偏見で決めたんですけど、思いついたおかずばかり詰めてたら多くなっちゃって……。これは私が持って帰って家で食べますので――ッ」
「誰も食べないとは言ってないです」
「えぇー……?」は首どころか上半身を傾けて、どこからか持ってきた風呂敷に重箱を丁寧に包み始める幻太郎を凝視する。やはり、彼の言うことはいまいちよく分からない。今回もからかわれただけなのだろうか。にしては、さっきまで重箱を溝に捨てると言わんばかりのお顔でいらっしゃった。今はもう桜に攫われたように消えてなくなっているが。
幻太郎と話していたらあっという間に八時を回り、いつもの卓袱台を囲んで朝食を食べる。珍しく、配膳は幻太郎も手伝ってくれた。普段は天井の照明がこの部屋を照らしてくれるが、今日は違う。こんなにも清々しい日光が入り込む居間で手を合わせるなんて、なんだか新鮮な気分だった。
それでも、の口はいつもと相変わらずよく回る。軽度の花粉症であるは、そろそろ鼻がむずむずとしてきたところだったので、「もうすっかり春ですねえ」となんとなしに言う。「そうですね」幻太郎の返事は変わらず素っ気ないが、は彼にあれやこれやと会話に種を植えてはぽんぽんと花を咲かせる。先生、私、今年はたくさんやりたいことがあるんですよ。
「やりたいこと、ねえ」
「はい! まずは近所のお花見で出店して、夏には最近行けてなかった花火大会にも行こうと思ってて! あ、近所の秋祭りで紅葉狩りが催されるんですけど、そこでも一つ屋台出したいんですよ~!」
「祭り事ばかりじゃないですか」
「えへへ。趣味とプチお小遣い稼ぎです」
花見は団子の出店で、レシピは考案中だが、もうすでに場所は押さえてある。夏祭りは全出店食べ歩いて制覇しようかとか、秋祭りは五平餅を作ろうかとか、考えるだけでも今から胸が踊る。
は作ることはもちろん食べることも大好きである。ここ数年は仕事のことで手一杯だったが、それも今では慣れたもの。そろそろ自分のやりたいことに手をつけたいと思っていたのだ。
「だから、その……先生も、もしよかったら出店に遊びに来てくれたら、う、うれしいなー……」
「いいですよ」
「いいですよーなんてそんな――。……え?」
はて。先生今なんと。お忙しいのにご無理言えるわけないと笑い飛ばそうと思っていたのに、はしばらくぽかんと口を開けたままだった。
しばらく間が空いて、我に返ったは「ほ、本当ですか!?」と前のめりになって卓袱台越しに幻太郎に詰め寄る。「ええ」
「花見でも、花火でも、紅葉狩りでも……あなたの好きなところなら、小生はどこでも構いません」
不意に合わさった幻太郎の瞳は、森林の奥深くにある湖のように穏やかに揺蕩いていた。卓袱台を隔てて、その距離が縮まることはないのに、なぜだかその視線に絡み取られている気がして、は金縛りにあったように動けなくなった。
「あなたのいない家の中……舞い込んだ桜の花弁は白黒の紙吹雪に映り、夏は蝉の鳴き声すら趣なく聞こえる。紅葉の色の移ろいにも気づかず、冬は目の前が一面銀色世界に覆われても、雪に埋もれたように、僕の心の琴線には響かない」
もう、あなたがいない四季など……僕にとっては意味のないものになってしまった
こんな沈黙の春なんて、あるはずがない。は口から心臓が飛び出しそうだった。幻太郎の言っていることは大概難しいが、雰囲気で、なんとなく、恋愛漫画に出てくるようなそれだった。つまり、いまのは、どういう……? その薄い唇から嘘ですよ、という言葉が出てくるのを待つが、いっこうに聞こえてこない。
こんなにも長い数十秒があっただろうか。は手に汗を握って、耐えきれなくなった空気に亀裂を入れた。
「せ、せんせ――ッ」
「なーんてにゃっ」
鼓膜を揺らした、可愛らしい声。たとえるならば、夢野姫さまとおじいちゃんの声を足して二で割った感じの。
は目にゴミでも入ったかというくらいぱちぱちと瞬きをする。その間に、幻太郎は猫にでも取り憑かれたように猫の手になっていて、唇も猫のようにつんと尖っていた。
「にゃ、にゃー、って……?」
「次作は探偵の野良猫が街を駆け巡るミステリーストーリーなのにゃ! 今の台詞は病弱な飼い主の最期の言葉なのにゃ~!」
そう言いながら、幻太郎は猫の手でにゃんにゃんと招いている。か、かわいい……。ではなく、このときめきの落とし所を完全に見失ったは、途方もない熱量を全身から出すしかなかった。胸が、頬が、頭の中が、大噴火を起こしたように蒸気を発する。いつもなら笑って流すところだが、こればかりは心臓がどくどくと鳴り止まなかった。
「……ご馳走様でした」
「えっ……。あ、はいっ、お、お粗末、さまでした……」
茶番はこれくらいにして、と付け足すが如く。朝食を食べ終えた幻太郎は涼しい顔ですたすたと玄関に向かい、もその後をとてとてとついていく。なんだろう、この風邪すら引きそうな温度差。いつものことだが今日ばかりは凄まじい。
は両手で胸を抑える。ああ、耳まで熱い。ああいうのはちゃんと、好きな人とか、大事な人に言うべきだ。冗談でも、こんなちんちくりんの家政婦に言うことじゃない。
「せ……先生っ!」
でなければ……そうではないと思っていても……錯覚してしまう。
「さっき、どこにでも行くって言ってくれて、すごく、すごく……うれしかったです……!!」
いつから、こんなことを言えるようになったのか思い出せなかった。は幻太郎の気持ちを中々汲めないし、知らない間に彼を不機嫌にさせている。そのたびには落ち込んで、仕事で本領発揮することができない。
しかし、とんがった石も擦り合わせれば角をなくす。お互いに……いや、きっと、幻太郎がかなり譲ってくれたのだろう。そんな幻太郎の下で仕事をできることが、はとても嬉しかった。たとえ嘘でも、幻太郎の中でそういう発想が湧いてくるくらいには、好意的に思われているのではないかと、独り善がっていたかった。
「で、でもですねっ、急にあんなこと言われたら、どっ……どきどきするので、ああいう冗談は程々にして頂きたいといいますか……! わ、私も家事代行人としてまだまだ未熟者ですが、ご飯も季節物とか取り入れて、先生の暮らしがよりよくなるよう尽力――」
不意に、目の前が真っ暗になる。なんだか鼻の上からインクの匂いがするなと思って、幻太郎の手のひらが視界を覆っているのだと分かった。動いていたの口も思わずぴたりと止まる。「えっ?」
「せ、先生……? あの、何も見えないのですが――」
「うるさい」
「え? う、うるさい?」
「メーデーメーデー……。今、あなたの脳に直接語りかけています……。目を閉じ、口を閉じ、なんなら鼻も摘んで五感という五感をいっさいシャットダウンするのです……」
「それは遠回しな死刑宣告ではっ!?」
お、怒ってる……! 先生が怒ってるううぅぅ……!! 生意気言ってごめんなさい! ちょっと……いやかなり調子に乗ってしまいましたっ! はあたふたとして言い訳を並べると、幻太郎はすぐに手を離してくれた。しなし、振り返りざまにふん、と蔑まされてしまい、はしゅんと肩を落とす。
玄関先で靴を履き終えた幻太郎に、無言で手を出される。視線の先にあるのはの抱える重箱。おそるおそる差し出すと、すっと片手で持ってくれた。食べてくれるかな……。でもやっぱり中身だけ溝に捨てられそうだ……。次回、ご馳走様という言葉とともに重箱が返ってくることを祈っていると、「……あなたの素直さも、ここまでくると病気ですね」と、幻太郎がはあ、とため息をついた。それは褒めているのだろうか。いや、さすがにちがうかな。
「……いって、きます」
耳に届いたのは、とても小さな声だった。まるで、小人が話したような。しかし、それは姫様でも三下マフィアでもない。正真正銘の夢野幻太郎の言葉だった。が顔を上げると、引き戸を開けて今にも家を出るところの幻太郎がいる。おそらく、もうこちらを振り向いてはくれないだろう。
だから、はぱあっと花咲いた笑顔で、「いってらっしゃいませ!」と大きな声で返す。すると、驚いた鳥が羽ばたくように、幻太郎はすぐにぴしゃんと玄関を閉めた。声の余韻は玄関の壁に吸い込まれていく。それがなんとなく心地良くて、はへへ、とひとりでに笑った。
誰もいなくなった家の中で、はスキップをしながら廊下を進む。そしてふと、視界の端で目新しい彩りがちらついたことに気づいて、は縁側の庭に視線をやった。そこでは、紫、赤、黄……名前も知らない花々が一枚の絵になるように咲き誇っていた。そういえば、随分前によくこのお庭の手入れしていた。素人の整地でここまで長く綺麗に保ってるなんてすごいなあ。
えへへ、とはまたわらう。ここに来る前は音も色もなく、すこしだけ寂しかったこの家も、今は四季など関係なく、春らしい極彩色に色付いているように見えた。