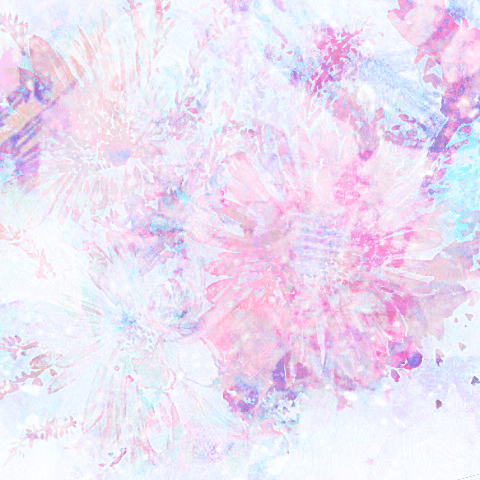Episode.6
その家政婦は、春の嵐のごとく自分の目の前に突然現れた。
「本日から、夢野さんのお宅で雇われた若槻というものですがっ」
外から聞こえてきたのは、溌剌とした女の声だった。おかげで、彼女の声で集中力もぷっつんと切れてしまい、週に一度舞い降りるかどうか分からない筆の神はそそくさと逃げてしまった。次々に溢れていた言葉の噴水がぴたりと止まって、幻太郎は苛立ちげに舌打ちをする。どうしてくれる。また締切前に起きるあの負のスパイラルに陥ってしまうではないか。
いつもなら見も知らぬ訪問者など相手にせずスルーするところだが、今回は乗っていた執筆の波がかなり大きかったため、その怒りは中々治まらなかった。一人では抱えきれないそれを少しでも緩和したいと、幻太郎は自室がある離れから外の様子をちらりと伺う。
すると、玄関前には見た目二十歳そこそこの娘が良い姿勢で棒のようにぴしっと立っていた。誰だ。幻太郎にはあんな小娘の知り合いなどいない。あんな人間がうちを訪問する理由として推測できるのは三つ。夢野幻太郎のファンか、宗教の勧誘か、はたまた担当編集者の回し者か……。
最後のものは冗談で言ったが、あながち間違いでもなかった。ちょうど担当から一通の電子メールが届いていることに気づいて読んでみれば、そこには、多忙ゆえに私生活が乱れている幻太郎を見兼ねて、家事代行サービスの人間を雇ったと書かれていた。語尾についた“てへぺろ”の顔文字に、幻太郎の怒りは頂点に達した。もうお前のところでは一文字も書いてやるものか。
とにもかくにも、面倒なことになった。幻太郎は外にいる娘を再度見る。部活帰りのJKが持っているような大きなボストンバッグを小さな体に引っさげて、家主が出てくるのを大人しく待っていた。
そこで、幻太郎は閃いた。お世辞にも娘は頭が良さそうに見えなかったので、息抜きがてら少し遊んでやろうと思ったのだ。
「はて……。この家にはユメノという人間はおらんがのう」
いったん部屋から出た幻太郎は、インターホンのマイクに向かってしゃがれた声を吹き込む。すると、想像以上に娘の顔はさあっと青ざめていき、「しっ、失礼しましたっ!」と手にあるスマホを見比べながら、家の前から早々に姿を消した。
暇つぶしにもならなかったが、リアクションは満点をあげてもいいだろう。まあこんなものか、と幻太郎は鼻でせせら笑い、離れに戻る。あとで担当を恫喝しつつ、家事代行というよく分からないサービスは解約してもらおう。なぜ好き好んで自宅に他人を招き入れ、他人の手で作られたものを食べさせられ、おまけに金を払わなければならないのか。新手の詐欺か。やれやれ、と肩をおとした幻太郎は再び筆を握った。
――それから一時間後。ちょこちょこと外から聞こえてくる独り言に、幻太郎はまたもや手を止める。
「ここで合ってるよね……? でもさっき違うって言われたし……」「電柱の番地消えてて見えないよー……」「ど、どうしよう……。約束の時間とっくに過ぎてるのに……!」焦燥に駆られた声が幻太郎の集中をごりごりと削ぐ。ああくそ、と原稿用紙をぐしゃぐしゃにして丸めたのは、これでもう何度目か。怒り心頭の幻太郎は先ほどと同じように外を覗き見た。
「……あの小娘はなにやってるんだ」
さっき消えたはずの娘が、未だ家の前できょろきょろとしていた。まさか、追い払ってからずっと目的の家を捜し求めていたというのか。誰かに教えられた住所を何度も確認しながら、それに該当する我が家の周囲をぐるぐると回っていたと。さっきの老人が嘘をついていたとも疑わず。なるほど、幻太郎の目に狂いはなかったようだ。この娘は正真正銘の馬鹿である。
しかし、これ以上は万事休すと言わんばかりに、娘は今にも泣きそうな顔をして向かいの塀にもたれかかっている。諦めてさっさと帰ればいいものを。こういう馬鹿はからかいがあるが、時折面倒な行動をするから厄介だ。馬鹿が自ら決定できないのは、それ相応の責任を負いたくないからだ。
――刹那、ずずっ、と鼻を啜る音が聞こえてくる。おまけに娘が目を擦る動作が見えて、幻太郎は体から力がふっと抜ける。筆を机に叩きつけ、玄関に引き戸をガラガラと開けた。
「ああああああのっ! 私、決して怪しい者では――ッ」
「小生が夢野幻太郎です」
「え゙」
幻太郎は先ほど若槻と名乗った娘を冷たく見下ろす。小動物のような丸い目に小さな顔、詐欺被害に千回騙されました、とふっくらした頬に大きく書いてあった。嘘である。しかし、そんなお人好しで馬鹿正直なオーラがぱあっと醸し出されているのは事実だ。
こんな小娘に、家事など任せられるはずがない。すぐに解雇してやると意気込んだが、まあ……少しは、ほんの少しなら小説のネタになるかもしれないと、幻太郎はこの娘に少しは興味を持ってやってもいいと思っていた。遊んですり減っねこじゃらしは、野原に放るだけ。辞めさせるのは、それからでも遅くないだろう。
「あ、あのう。さっきこちらの家のインターホンを鳴らしたら、おじいちゃんの声が聞こえたんですけど……」
「ここに住んでいるのは小生一人だけですよ。……ああ、そういえば、以前この家に住んでいた老人が孤独死して、未だこの家を徘徊していると不動産屋が言ってましたね」
「はッ、徘徊……っ!?」
「まあ嘘ですけど」
「えッ」
搾り取れるだけネタを搾り取って、一週間と経たずに解約するつもりだった。
しかし、若槻という女はなかなかの曲者で、幻太郎が今までに会ったことのない人種だった。いくら日を重ねても、彼女の新たな一面がどんどん出てくる。よって、幻太郎による若槻の人間考察はいっこうに終わりを迎えることがなかった。
てっきりドジっ子家政婦かと思いきや、廊下で転んだりフライパンを焦がしたりという王道のミスはせず、仕事に失敗はない。正直つまらない。そして、さらなる期待を裏切るように、彼女の料理がこれまた美味しい。これでもかと言うくらい美味しい。初めての料理を口にした幻太郎が舌を巻いたほどだ。
「ど、どうでしょうか……?」
「……ふつうですね」
美味しいなどと言ってやるものかと思って出た強がりだったが、は嬉しそうに顔を綻ばせる。ふつうと言われてなぜそんなに笑顔になるのか、甚だ理解できない。そんなふうに笑うな。目が離れなくなる。美味しいということは顔にも口にも出さなかったが、まあ、週二で一食なら食べてやってもいいかというくらいだ。
依頼したのは週二の夕食の調理代行(後々に週三、週四と増やしていくとはその頃の幻太郎は知る由もなかった)と聞いていたのに、たまに部屋が綺麗になっているし、冷蔵庫を覗けば時々朝ご飯らしきおかずも作ってある。
目上の人間に気に入られようとする、王妃の後釜に座る悪女タイプの女かと思うも、彼女は幻太郎が自分のことを快く思っていないのを察しているらしい。家の中で幻太郎と会えば鼠のようにびゃっと逃げていく。失礼な女だ。この家の主は自分だというのに。うちの近所の人間に会った時はあんな愛想良く世間話をしていたのに、この差はなんだ。幻太郎は娘がする言動ひとつひとつが気になって、気に入らなかった。
いつからか、いっこうに掴めないこの娘の本質を知ろうとヤケになっている自分がいた。しかし、幻太郎は何一つ分からなかった。彼女と話す会話の内容も、タイミングも。所詮、娘とはビジネスパートナー。家族や恋人のような深い繋がりも、ましてや友人のような心が近い距離にあるわけでもない。幻太郎はもどかしかった。胸の中に芽生え始めた若葉の名前も摘み取り方も分からないまま、時間だけがゆっくりと過ぎていった。
そして、彼女がこの家に来て三ヶ月経ったある日のこと。幻太郎は食後にお茶でも飲もうと、離れを出て母屋に続く廊下を歩いていた。
すると、そのど真ん中で外の様子を伺っているがいる。サボりですか解雇しますよ。ひねくれ者の自分が用意した言葉をごくっと飲み込み、幻太郎は震える唇をなんとか誤魔化して、口を開いた。
「……そこに突っ立っていられると邪魔なんですが」
声を、かけただけ。なのに、彼女はびくっと肩を揺らしてキラー・クラウンを見るような眼差しでこちらを見上げる。まだ何もしていないのに、そんな目を向けられるといらっとしてしまう。なんで自分にだけこういう態度なんだ。
その気配を感じとったは「あっ、その、えーっと……」と、しどろもどろになり、幻太郎の視線から逃げるようにちらっと縁側に目をやった。
「この庭は、先生が整地されてるのかなーって……」
おそるおそる差し出された言葉に、幻太郎もまた、庭を見る。雑草が好き勝手伸びているほど荒れてはないが、これといって目立った植物もない。人の目についてもお目汚しにならない程度に、ほどよく整えられていた。
「まさか。たまに庭師を雇う程度です」
なぜそんなことを聞きたがるのか分からないが、は「そうなんですかぁ……」と空返事で、自分ではなく庭を見るばかりだった。幻太郎はお気に入りのおもちゃを取られた気分になって、胸の中がひどくもやもやとする。
だから……きっと、そのせいだ。普段なら思いもしない言葉が口から飛び出したのは。
「……暇なら、空いた時間にいじっても構いませんよ」
嘘ですけど。瞬時にそう言おうと思ったが、それよりも早く、「ほんとうですか!?」とが目を輝かせて言うものだから、幻太郎はタイミングを逃し、すっと口を閉ざした。
「私、ガーデニングとかやってみたかったんです!」
言葉は言い様である。所詮庭いじりだろう。それも、他人の家の。何が楽しいのか全く理解できない。しかしまあ……いいか。どうせすぐ飽きるだろうと、子犬に骨を与えた感覚で、幻太郎はの後ろについているはずもない尻尾が振られているのを幻覚として垣間見たのだった。
うだる夏、色鮮やかな秋、凍てつく冬を見送り――早くも次の春がやってこようとしていた。
相変わらず、幻太郎はに対して素っ気なかった。ご飯ができるまで部屋から出ないし、部屋の外で彼女に声をかけられてようやく初めて顔を合わせる。
「夢野先生ー! ご飯できましたよ~!」
ああ、今日もうるさい笑顔だ。怪訝そうな顔で応じるまでがセット。幻太郎は今日も、彼女に声をかけられるのをじっと待っているのだ。
その日は、昼の調理代行を臨時で依頼していた。幻太郎が居間でご飯を食べている間、彼女がどこにいるのかというと、大概は庭である。いつからどこから持ち込んだのか、スコップや鎌などが庭の隅に置いてあり、雑草以外の植物が日に日に増えていく。ただの風景として空間にぽつりとあっただけの庭が、彼女の手によって徐々に変わりつつある。おかげで、幻太郎は食べるのをわざと遅くしなければならなかったし、に気づかれないように離れに戻って、自室から作業をしているの様子を盗み見るスキルばかり上がっていく。そうしたら、彼女がこの家にいる時間が長くなると知ったのだ。
「先生!! 夢野先生っ!!」
桜の花びらが縁側に遊びに来るようになった、四月のある日。バタバタバタッ、と廊下を駆ける音に、幻太郎は筆を置いた。彼女のために筆を置くなど、もう日常茶飯事になってしまった。しかし、不思議と以前のような苛立ちはなく、むしろ心臓が高なっている感じがした。しかし、幻太郎はその衝動をぐっと耐えて、不機嫌な表情をつくった後、部屋からすっと顔を出した。
かれこれ、もう一年の付き合いになる。顔を合わせるたびに震えていたは、仏頂面の幻太郎と対面しても笑顔が崩れることはなく、むしろ今回は幻太郎の腕を掴んで母屋に引っ張っていった。
「なッ、んですか急に……!」
「こっち、こっちです! 先生に見ていただきたいものがあるんです!」
さわるな、顔があつい。今こっち振り向いたら目潰ししてやる。自分の腕を掴んだ手のひらが思いのほか小さくて、あたたかくて、首から上に熱が集中する。なぜ今が夏ではないのか、と幻太郎は何の罪もない四季を恨んだ。
に案内されたのは、縁側の前に広がる庭。彼女の暇つぶし場だった。毎日この家にいる幻太郎は、日に日に変わる庭の様子を見守っていた。雑草ではない植物の目が出て、それがみるみる高くなり、蕾を結ぶ。昨日までは、たしかそんな感じではなかったか。
「去年の夏頃に植えたんです! 今日見たらみんな綺麗に咲いてたので、いてもたってもいられなくてですねっ!」
――いつのまに、この庭は、こんなにも色鮮やかな花々が咲き誇るようになったのか。
ジニア、ヒマワリ、ポーチュラカ……殺風景な庭に点描されるように咲いた花は、幻太郎の視界をほのかに彩っていた。きっと、自分一人では、見たつもりでいただけ。彼女がいなければ、この庭がどんなにめかしこんでいようと、ただの風景にしか映らない。一方のは、「一年待った甲斐がありました~!」と暢気に喜んでいる。
ああ、この……表情。今、この一瞬の描写をしようと筆を取るならば、一万文字でも足りない。気恥ずかしさに似た憤りと息苦しさに似た歓喜が複雑に絡み合って、幻太郎の胸の中に棲みついていた。もう、これを飼い始めて丸一年が経つと思うと、途方もなかった。
ほんとうに……うっとうしい。だれか、名無しのこれをどうにかしてくれ。どうですか、と春先の太陽のように目をきらきらとさせてこちらを見上げる彼女を前世で親を殺された殺人鬼と見立てて、幻太郎は冷たく睨んだ。
「花が咲いたくらいで煩いんですよ。夕食ができた時もそうですが、あんな大きな声で呼ばれなくても聞こえます」
「あ……。す、すみません……」
違う。そういう反応を、してほしいわけではなくて。幻太郎は頭の中に仕舞ってある辞書をぱらぱらとめくった。今被るべき仮面を選んで、本音を隠した盾で彼女を押しのけ傷つける夢野幻太郎を、得意の嘘で存在ごと隠した。
「こーんなちっちゃな花ごときでわっちの機嫌が取れるとでも思ったのなら、甚だ滑稽でありんすなあ」
「あ、ありんす?」
「無駄な努力だが、せいぜい余の玩具として今後も励むことだ」
「よのがんぐ……?」
頭の上にクエスチョンマークを浮かべただったが、とりあえず笑っておこう、という心の声が漏れるように、にへら、と笑った。
ああ、そう、この家にいるときは、おまえはずっと、そうしていればいい。なにも考えず、自分が作りあげた虚言に翻弄されればいい。だれの目にも触れさせないよう、摘み取られないよう、ひとりぼっちの広い家で、この小花を育てようと思った。
そこで、幻太郎は初めて、彼女に胃袋どころか心臓すら掴まれていたことを知ったのだ。
「あの、先生ってもしかして……多重人格者だったり、とか?」
「ええ……。実は学生の頃に激しい集団リンチを受けて、これは自分ではないと言い聞かせるうちに吉原の太夫、どこぞの国の王様の人格が生まれたのです」
「ひえッ。せ、先生にそんな壮絶な過去が……っ」
「まあ嘘ですけど」
「えッ」
去年までは、が植えた花の名前が彼女の口からぽんぽんと出てきた(種が入った袋を読んでいるだけだが)。しかし、最近はわざわざそれを言ってこなくなった。なぜなら、の手がなくとも、その花が種を落とし、一年後には同じ名前の花が咲くからだ。
は庭いじりをしなくなった。そもそも、庭の存在すら忘れているにちがいなかった。だから、不要な草の除去や水やりや新しい植物を植えるのは、家主である幻太郎の仕事になった。正直面倒である。
花は勝手に育つと思っているところが、やはり馬鹿の思考だ。の見えないところで自分が手入れしていることも知らずに、彼女は家の玄関をくぐる。ほんとうに脳天気な娘だ。面倒なら止めればいいだけ。簡単な話だ。しかし、彼女のことだ。自分が今まで世話をしていたと言ったら、申し訳ないと言わんばかりにその太陽に分厚い雲が被るだろうし、世話をやめて花が枯れてでもしたら雨が降りそうだ。そういうことを、期待しているわけではない。
それならば、庭の存在を思い出したときにでも、新しい花が咲いていたという話を、どうでもいい話として自分に聞かせてくれれば、幻太郎はそれでよかった。
「そういや、は今日いねーのか?」
「あーっ。それボクも思った~っ」
今日も今日とて突然訪問してきた帝統と乱数が、近所で買ってきたらしいマックのポテトを摘みながら言う。幻太郎は壁にかけられたカレンダーを一瞥して、さも興味なさげにこう言った。
「火、木、日曜は来ませんよ」
「へえー。てっきり毎日来てるのかと思ったぜ」
言われてみれば、帝統が来ていた日にはきまってがいたような、そうでもなかったような。
それよりも、帝統が彼女を気にかけるほど仲良くなったのかと、幻太郎は少しだけ気に入らなかった。
「彼女に何か用事でも?」
「んー? あー、なんだったっけな。なーんか頼んでたことがあるっつーか」
帝統が忘れるのなら、賭け事絡みではないことは明白である。が帝統に誘われるがままに賭け場の恐ろしさをその身で痛感し、負けに負けて一文無しになるのは目に見えているのだから。
金絡みのことはやめろというのに、帝統に土下座をされたらいつまで経っても財布を出すのだ、あの娘は。お人好しが過ぎる彼女は、やはりどこまでいっても目が離せなかった。
「げんたろー、そんなこわーい顔してどうしたの~?」
「なんでもありませんよ」
二人とが絡むとこうなることが目に見えていたから、彼女と対面させるのは気が進まなかったのに。それでも、突然やってくる台風の目を凡人が避けられるわけもないのも承知していた。
最初の頃は二人には散々おちょくられるし、もで、「先生のお友達ですかっ!?」と嬉しそうに聞いてくるし。なんなんだ。自分の周りにはこうも温度差のある人種がきれいに揃うんだろう。というか、に至っては驚くポイントズレている。テレビを見ていないのかあの娘は。
帝統は……この際いい。問題は裏の読めないうちのリーダー。「ふぅーん?」と意味深な笑みを浮かべている乱数の視線から逃げるように、幻太郎は涼しい顔をしながら湯呑に入った茶をずずっと啜る。
「ま、ボクにはカンケーのないことだけどね~っ」
「なんのことですか」
「なんの話だ?」
帝統も帝統で鈍いな。いやその方がありがたいのだが、それはそれで癪にさわるものがある。幻太郎が帝統を哀れみの目で見ていると、乱数は嬉々として口を開く。
「ゲンタローって、オネーサンのことけっこー気に入ってる感じなの?」
「いやだから何の話だって――」
「帝統はぁ~ん。少しの間、その大きなお口は閉じておいておくんなまし~」
「んぐ?」首を傾げながらも、素直に両手で口を塞ぐ帝統を見ながら、幻太郎は思う。自分も、このくらい馬鹿だったら、こんなにも長い時間、余計にあるこの感情を収めておく必要はなかったのだろうか、と。
乱数の言葉が頭の中で円を描いている。いっこうに腹の奥に落ちてこないのは、もう、そんなことはとっくに分かっているからだ。
素直を通り越して馬鹿正直、こちらがどれだけ素っ気なくしてもご飯は美味しいし、ほんのちょっと意識を傾けただけで、ご褒美ですと言わんばかりにぱあっと笑う。きらきらぴかぴかと、うっとうしい。眩しくて、かなり目の毒だ。
それでも、その光景を収めておきたいと思うのは、このうっとうしさすらも悦と感じてしまうくらい、彼女は自分の人生の中ですでに主要人物と化しているのだと自覚せざるを得なかった。
別に、彼女に何かを言うつもりはない。かと言って、今の関係以上の繋がりを絶とうとも思えない。毎回のように“ふつう”と評してしまう夕食と、彼女の口から零れる至極どうでもいい話。そして、絶対的光度を放つ笑顔が自分の手元にくるのであれば、それでいい。幸い、彼女がここへ来る理由は自分が握っている。だから、幻太郎が来るなと言わない限り、今の関係の最終章は書けないままだ。
しかし最近、歯止めが効かなくなっているのも、また事実。読み切りを終えても週四の代行契約は継続しているし、何かしら接点を持ちたくて片腹痛い茶番劇を繰り広げた。帝統に大人気なくも嫉妬して、足元がふらつくまで酒を飲み、彼女に触れたいと、一瞬でも血迷った。加えて、初詣になんか誘ったりもして――
自分でもなにがしたいのか、分からない。もで、こちらの気も知らずに好き勝手言うし、酒に酔って抱きついてくるし、正直堪ったものではなかった。
だから――もうこの際、隠していてもナンセンスだ。
「……えぇ。それなりに。だから、余計なことはしないでください」
どっちつかずなこの現状を、どうにかしなければいけない。幻太郎の決意を汲んだのか、乱数は「分かったよん!」と軽く言いのけた。本当に分かったのか疑問だが、おふざけでそんなことを言う男でもないだろうと、幻太郎は裏の読めない彼の表の部分を信じることにした。
「んーッ! んんーッ!!」
「ああ、忘れてました。帝統、もう手を退けてもいいですよ」
「ッ、ぶはあっ。あっ、そういや思い出したぜ! 俺、に大福作ってもらう約束してんだ! 縁起担ぎに“大”きな“福”ってな!」
「ああすみません。やはりその煩い口は閉じておいてくれますか」
「なんでだよ!?」
「あっはは~っ★」
リクエストなんて、自分ですらしたことかないのに、図々しい。しかし、幻太郎が口にあったものは決まって次の夕食にも出してくれるから、そもそもする必要がないのだ。それが彼女の仕事だと分かっているのに、自惚れる。だから嫌なんだ。どうしたって、この気持ちを手放すことができないから。
もうじき、冬を越す。次にやってくるのは、彼女と過ごす三度目の春だ。それにしても、一年を通して幻太郎の中でずっと春が訪れているような気がするのは一体なんだろうと思ってしまい、幻太郎は探しあてた答えにため息をつきたくなった。
……ああ、そうだよ。いつも花が咲いたのように笑う、彼女のせいだ。