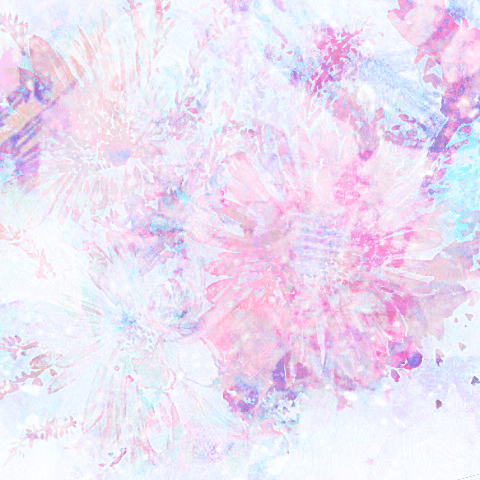Episode.5
外を歩くたびに白い息が踊る。また新たな年が始まり、は心機一転した気持ちで仕事に励んでいた。
去年の今頃、幻太郎の家は雪の中に埋もれてしまったかのように静かで、余計に寒い思いをした記憶がある。お客人もめったにやってこないこの広い家は、去年のの目にはどこか寂しく映ってしまった。
大勢で囲むこたつとか、お鍋とか……そういう光景をいつか見れたらいいなと、口にこそ出さなかったが、そんなことを心の中にこっそりと忍ばせていた。
「“すき焼き”は大人数で食べるのが美味しいってオネーさんから聞いたんだよね~!」
なので、そんな幻太郎の家で鍋奉行を担うなんて、去年のは予想もしていなかった。
人生、何が起こるか分からないものなんだなあ。本日の相棒であるおたまを掲げながら、は各々の小皿にせっせと具を注ぐ。椎茸、葱、白滝……そして、高級霜降り松坂牛三百グラム×四パック様。この肉は乱数の持参物である。聞けば、仕事関係のお得意様から厚意で貰ったとのことだった。
――「ゲンタロ~! 遊びに来たよ~っ!」
乱数の訪問はいつも突然だ。今日も、が台所に立って割烹着を身につけた時にはすでに、彼は幻太郎宅に足を踏み入れていた。
あの声はもしや、とが暖簾から顔を出すと、「あ~っ! オネーサンがいる~っ! ボクってラッキ~!」と流れ星もぎょっとする速さで抱きついてきた乱数をはおぉっと、とその胸で受け止める。乱数との身長差はそれほどなく、顔つきもどちらかというと女顔なので、どこか学生の頃のノリを思い出してしまう。ううん、乱数君も先生に負けじと顔が良い。
パーソナルスペースがゼロどころかマイナスを極める乱数のハグにはもう慣れたものだが、幻太郎が傍にいると節操がないなどと言われてしまうので、せめて声は抑えて頂きたいものだった。こんなところを見られようものなら、幻太郎は鬼の面でもしているんじゃないかと思うほどの凄まじい形相をするのだ。
――「まったく……。乱数、来る時は連絡をしてくださいとあれほど――」
……さて、冒頭に戻る。普段の地味な献立ではお通夜待ったなしのところに、乱数の「すき焼きしよっ?」という一言で、食卓はパーティームードに。主役はなんといってもこのお肉。所々に降っている霜に、思わずの口内に涎が溢れた。ちなみに、乱数のお誘いに加えて幻太郎からお許しもでたので、もその場にあやかることになった。食卓には三人分の皿がきちんと並べられている。
というか、乱数君もすき焼きとか食べるんだなあ。キャンディーが主食でスムージーしか飲みませんみたいな顔してるのに。でもそうだよね。乱数君も男の子だもんね。可愛い顔して一枚の松坂牛を丸々食べる姿ももはやインスタ映え。タピオカもバナナジュースも引けを取らない。……さすがにちょっと言い過ぎかな。
「せ、先生、まだお肉たくさんありますよ? 取りましょうか?」
「自分で取るのでお構いなく」
そんなことおっしゃらずに。乱数とのハグを見られて以来、幻太郎はずっとこんな感じである。いつもより態度が七割増で素っ気ない。白滝ばかりちまちま食べる幻太郎が、はとても心配だった。せっかくのお肉なのに食べなければもったいない。この機に、先生にはたくさんのお肉を食べて頂かなければ。
しかし、今の幻太郎の好感度は今までと比較にならないくらい最底辺。シーラカンスが泳いでいるのが見える。は別のお皿にお肉を乗せて、そそ、と幻太郎の手元に滑らせるが、彼はそれを一瞬見ただけですぐにそっぽ向いてしまった。こ、こんなにもお汁がきらきら光ってるのに……! お肉誘惑作戦は失敗に終わった。地味にショックである。野良猫に餌をあげてもいっこうに懐かれない敗北感にどこか似ていた。
「あーっ。幻太郎だけずる~い! オネーさん、ボクにもちょーだい?」
「えっ? あ、うん! 乱数君、何がいい?」
「えぇ~っとねえ」乱数の可愛い口からぽんぽんと跳ねて飛んでくる具材を、は慣れた手つきでさっさと注ぐ。そして、鍋の中でふよふよと浮いているお残りの野菜や幻太郎が食べずに冷めきってしまったお肉を自分の皿に移して、空いたスペースに新たな具を投入した。煮立つまで、またしばらく待機の時間である。
「そういえば、帝統君は?」
「新しく見つけたカジノにでも行ってるんじゃないかなあ~? あっ、でも負けたらきっと来ると思うよっ」
「そっかあ」
勝ってほしいような、負けてほしいような。勝っても負けても来てくれることを祈りつつ、は一番の食べ盛りである帝統のお肉を取り置きしておく。
「そーいえば、オネーさんにお願いごとがあるんだけどぉ~。聞いてくれるかなぁ?」
乱数の言葉にがこてん、と首を傾げると、彼は待ってましたとばかりに、バッグから一枚のパンフレットを取り出した。
そこに映っているのは純白ウエディングドレス。上半身はタイト、スカートにふんわりとしたボリュームを持たせた形のプリンセスラインだった。モデルでもマネキンでもなく、トルソーに着せられているだけのものだが、そのドレス一着だけで、美術館に飾ってもおかしくないような煌びやかさを放っている。
「す、すごい……!」
「知り合いのデザイナーがこんな感じのウエディングドレスを制作しててねっ。今度コンペがあるんだけど、今回のコンセプト的にオネーさんが一番ぴったりなんだよね~!」
乱数の話を要約すると、どうやら友人が作ったウエディングドレスのモデルになってほしいとのこと。それを聞いたは「ひぇッ……」と、思わず変な悲鳴を上げてしまった。モデルなんて生まれてこの方一度もやったことがない。ルームメイトと町を歩いていても、読モやカットモデルの声をかけられるのは専ら彼女の方である。容姿も中身も平々凡々なは側近であるマネージャー役が精々だった。
しかしまあ、こんなにもオシャンティーなウエディングドレスに興味がないというわけではない。の幼少期の将来の夢はお嫁さんという王道を走っており、正直今でもその夢は密かに継続中である。しかし、それなりの夢を描いているわりには行動に移しきれていない。学生の頃にやったことといえば、恋愛よりも友達と部活に励むこと。学生を終えた今も、仕事が充実していて恋人を作るどころの話ではないのだ。
あれ。これって私、かなり枯れた生活を送っているのでは? そろそろ彼氏がほしいと今更乞食のような感想を抱いた。
「ねっ? いいよねいいよねっ?」
「駄目です」
唐突に聞こえてきた幻太郎の声で、はたと現実に戻ってくる。あれだけ白滝と椎茸しか食べていなかった幻太郎が、今ではこれでもかと松坂牛を頬張っている。おかげですかすかになった鍋の中を覗いてぎょっとしたは、慌てて新しいお肉のパックの封を切った。
「むぅー。ボクはオネーさんと話してるのっ。幻太郎には聞いてないんだけどなあ~っ」
「無関係というわけではないので。その日、彼女は小生の家で雑務があります。うちの家政婦を他事に使わないで頂きたいですね」
「この日だけ貸してくれたっていいじゃ~ん!」
「彼女はものではありません」
やいのやいのと言い合う二人をよそに、は菜箸で新たなお肉を鍋の中にそうっと泳がせる。先生、まだ椎茸食べるかな。もし食べるなら台所に戻って切ってこないと。あと白菜も。
二人が話し合いを終えるまで鍋に専念しようと思ったが、むに、と耳を引っ張られる感覚がして、は急遽鍋奉行の任から離脱せざるを得なかった。
「して、当人であるあなたがなぜ他人事ですみたいな顔をしているんですか」
「あっ、たたたたたぁッ!? 先生っ! 汁っ! 汁落ちちゃいますッ!」
「畳の上に落としてシミでもつけたら弁償して頂きますからね」
耳たぶを引っ張りながら、なんて肝が縮むことを言うのだろうこのお方は。なんとか菜箸を皿の上に着地させて、は幻太郎の腕をがしりと掴むと、案外すぐに手が離されたのでよかった。しかし、耳は痛い。おそらくぷっくりと真っ赤に腫れていることだろう。
「ねえねえ、オネーさんもウエディングドレス着たいよねっ? ねっ? ねっ?」
「え、えーっと……ッ」
きゅるるん、とポメラニアンのような目で見つめてくる乱数。その一方で、鬼神のお面の如く顔を顰めている幻太郎の板挟みになり、今度こそは焦った。
乱数を見て、幻太郎を見て、乱数を見て、そして再び幻太郎を見たその時、気のせいかもしれない……それでも一瞬だけ、目尻をきゅっと絞って、どこかくるしげに、なにかを乞うようにこちらを見つめる幻太郎の表情が、の目の奥に焼けるように刻み込まれたのだ。
それからまもなくして、帝統が幻太郎宅の門をくぐった。
いつもの二人だけでは広すぎてしまう家の中はいっそう賑やかになり、不思議と狭いとさえ思えた。以前酒に呑まれたこともあって、幻太郎は今回あまりお酒は飲まなかったが、乱数と帝統は程よく酔ったようで、最後は幻太郎とハグをして帰っていった(一方で、幻太郎はやり場のない両手を宙に浮かせていた)。
も誘われるがままごくごくと飲んでいたが、すこぶる弱いわけではない。はっきりと意識を保ったまま、引き続き職務を全うしている。台所は来た時と同様にまっさらな状態にして、本日も大活躍だった卓袱台を拭いていたところだった。
「……よかったんですか」
「えっ?」
「モデルの件」壁にもたれかかって酔いを覚ましている幻太郎がぼそりと呟く。うぅん、と少し思案した後、はへら、と苦笑した。
「たしかに、ウエディングドレスはちょっとは魅力的でしたけど……。少し恥ずかしいというか、周りの雰囲気に呑まれちゃいそうで、モデルどころじゃないというか……」
「あっ。先生は普段から和装ですし、結婚式はやっぱり神社とかお寺派なんですかー?」もでお酒が入っているからか、普段よりも少し突っ込んだ質問をしてしまう。すると、妙な顔をした幻太郎はふいっと顔を背けて、口の先だけでぽつんと言った。
「……小生はそういうけったいなことはよく分からないので、未来の家内に合わせます」
わあ。なんてお嫁さん思いの先生なんだろう。さすがだ。はじわじわと感激している。「先生のお嫁さんになる人は幸せ者ですね~」でろん、と顔を緩ませると、「あほ面」という鋭いお言葉が飛んできた。あれ、なんだろう。胸の中で魚の小骨がつっかえたようだ。「そんなことよりも、」
「知ってますか。乱数は小生と同い年なんですよ」
「えっ! そうなんですか!?」
それは知らなかった。は「へえ~っ。先生の方がお兄さんに見えますね!」そう言うと、幻太郎にどこか腑に落ちない顔をされてしまい、は目をぱちくりとする。こふん、と咳払いをした幻太郎は宙を仰ぎながらこんなことを言う。
「嫁入り前のお前さんが、将来を誓いあってもない男に易々と懐を許すのはどうかと思うがのう?」
「あ……。そ、それはその……お見苦しいところを見せてしまい申し訳ございませんというか……」
「若槻は痴女なのじゃ~」
「ちっ、ちじょ……!? ち、違いますッ! 誤解ですっ!」
「なら、金輪際ああいうことは止めていただけますか。自分の家で不純異性交遊なんて見たくありませんので」
ハグ一つで大袈裟である。しかし、たしかに人様の家ではしゃぎすぎてしまったと思う。ああ、また叱られてしまった。最近はそうでもなかったんだけどなあ。しゅん、とは肩を落としながらいったん居間を出て、台拭きを水でゆすいでシンクにかけた。火の用心をした後、やや駆け足で部屋に戻ると、幻太郎はまだ壁際にいた。ほ、と息をついて、は部屋の隅に置いておいた鞄を肩に下げ、ぺこ、と頭を下げる。
「じゃあ先生、私そろそろお暇――」
突然、目の前がちかっと白く光る。
あれれ。ぐわん、と頭が揺れて、なんだかジェットコースターに振り回されている気分だった。きもちわるい。時間差でアルコールが回るなんて聞いてない。頭がふわっと宙に舞ったようで、の体は四方八方に傾いたのち、前のめりに倒れていく。
何かが畳を打ちつける音を聞いて、素早く視界を覆った黒い影。あたたかくも硬い壁がの顔面にごつんと当たった。あ……おばあちゃんのにおいだ。今年も夏になったら会いに行きたいなあ。
すんすん、とその匂いを堪能していたは、しばらく時間が経ってようやく意識がはっきりとしてくる。目の前も真っ白からモノクロモザイク、色付き始めた視界に瞬きを数回。というか、おばあちゃんやけに心臓の音早くない? 大丈夫? がふっと顔を上げると、そこには容姿端麗を極めた幻太郎の御尊顔があった。
あれ。おばあちゃんじゃない。えっ、じゃあ、私、いま、せんせいの匂い、嗅いで――?
「ごッ……!! ごごごごごごごめんなさいッ!! ちょっとふらついちゃいまして……!! えと、わざとじゃなくてッ、いやわざじゃなかったら何してもいいとか思ってるわけでもないんですけどッ! 不可抗力というかお酒の効力に抗えなかったというかああぁぁッ……!!」
数メートル飛び離れて、は畳の上で綺麗な土下座を決めた。お酒とは別の意味で顔が熱い。
これでは、このあいだのお酒騒動と何も変わらない。なぜだろう、今年にかけて幻太郎との距離が縮まりすぎている気がする。いや、それはとてもいいことだ。いいことなのだろうが、こんな破廉恥なことはいけない。仕事上、あってはならないのだ。
顔を、上げられない。編まれた藺草の目の数ばかりひたすら数えてしまう。そんなことをしているうちに、微かに襖を開ける音がして、は小さな隙間からひっそり覗き見るように上目遣いで幻太郎の様子を伺った。すると、なんと幻太郎の体半分がもうすでにこの部屋から出てしまっていた。はばっと上半身を持ち上げる。
「あのっ、せ、先生……?」
「もう寝ます。出ていく時、鍵はかけておいてください」
こちらを振り返りもせず、たんっ、と襖を閉める幻太郎。廊下を歩く足音すら聞こえなくて、ひとりがこの家で留守を任されている気分だった。
これは、もう、誰の目からみても、完全にお怒りだ。いや、幻太郎の機嫌を損ねることは何度もあったが、こればかりはいけない。一度入ったこの亀裂は強力接着剤でくっつけたとしても、くっついた部分からまた亀裂が生まれるレベルの修繕困難案件である。は頭を抱えた。
「や、やってしまったぁ~……っ」
は撃沈し、再び上半身を前に倒す。ぷしゅー、と頭上から蒸気を出しながら、今から数分前に戻りたいと念じながら後悔する。タイムマシンを探す旅に出たい。それか、先生の記憶を消す秘密道具が欲しい。翌日、セクハラ疑惑で自宅に記者達が押しかける妄想すら広げてしまい、は舌もお腹も満足に浸ってしまった過去の自分すらに憎らしく思った。