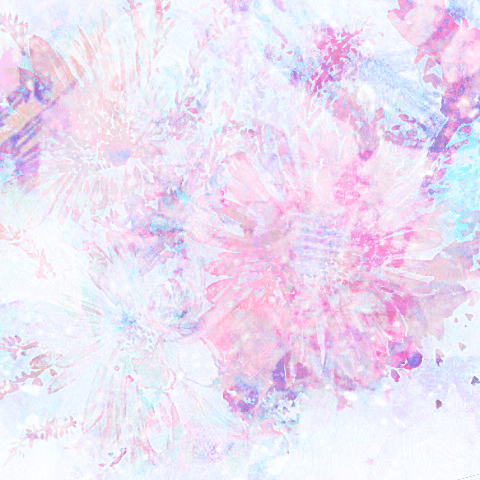Episode.4
早朝。霜が降りる季節になり、もう年の瀬も近い頃だ。夏だろうと冬だろうと、の寝起きは良い方である。毎日のルーティンに沿って、朝五時に起床し、二枚のトーストをトースターの中に入れる。ジジジッ……とタイマーが鳴いている間に、は昨日詰めたルームメイトのお弁当をナフキンに包み始めた。
手はてきぱきと動くも、の頭の中は寝起きのようにぼんやりとしていた。というのも、幻太郎の顔が曖昧になるくらいにはしばらく彼の顔を見ていない。もちろん、家には行っているし、ご飯も作るし、洗い物もする。しかし、幻太郎の部屋のドアに“何人たりとも部屋に入るべからず”という張り紙があって、あの日の夜から彼と一度も会っていなかった。
こういうことは初めてではない。原稿の締切間近に開催される、いわば“缶詰”。張り紙がある時は食事が出来ても呼ばなくていい、というメッセージだ。その言葉通り、は冷めても美味しいように作った夕食を冷蔵庫に入れて、一人ひっそりと家を出ていくことが常だった。
「……」
しかし、今はその状況に少なからず救われている。そう、あの酔いどれ夢野先生が、の頭の中で未だに千鳥足で歩き回っているのだ。酔っ払っていたとはいえ、あんなことを言われて、どんな顔をして会えばいいか分からなかった。幻太郎の顔を見るだけで、あの夜のことを意識してしまうことは必至。これだからイケメンは。オプションに酔っぱらいがついても、何をしても様になるのだからずるい。
はそれなりに乙女である。少しだけ……ほんの少しだけ、平常心を取り戻すために時間と距離が必要だった。先生は、きっと何も思ってないはず。そもそも記憶があるかどうかも分からないし。そう、すべては私の心の整理がつき次第――
「」
「えっ」はっとは我に返る。いつの間に起きてきたのか、ルームメイトである彼女が隣に立っていた。
ルームメイトはトースターとを見比べながら「焦げてる」とだけ言う。はおそるおそるトースターの中を視界に映した。
「ぎゃあ!?」
は悲鳴を上げて、慌ててトースターの電源をチン、と落とす。こんがり黄金色に仕上がるはずだったトーストは黒い野原になっていた。
や、やってしまったぁ……。一斤八百円の食パンがぁ……。が落胆している中、「真っ黒ね」と、ルームメイトが他意のない感想をぽつりと落とした。のメンタルはすでに瀕死である。
「ご、ごめん……! 新しいの焼くからちょっと待っててっ!」
この二枚は責任もって自分で食べようとすると、ルームメイトはその内の一枚のひょいと取った。「焦げていても平気よ」「だめだよ癌になっちゃうよっ!」せめて焦げたところ削って! そう言って、ルームメイトに素早くフォークを渡すと、彼女は素直に頷いて、席につくやいなやその焦げた部分をがりがりと削り出した。
せっかく美味しい食パンだったのにもったいないことしちゃったなあ……。とほほ、と肩を落としながら、も彼女の向かいに着席して、焦げた黒い部分をフォークで地道に削り始めた。
朝のニュースをBGMに、黒が目立たくなったトーストを二人で齧るが、(バターを塗ったら焦げた味が緩和されてそれなりに美味しくなった)、の頭は幻太郎のことで大忙し。テレビの奥では不審者情報が流れているが、それをただ流し見るばかりだった。
「最近、なにかあった?」
「えっ」
ふと、は幻太郎のことから意識を離す。「元気、ないから」とルームメイトのやや片言ぎみの日本語がの耳に入ってくる。自分の分の牛乳を注いでくれている彼女に、は条件反射で首を横に振った。
「な、なにも、ないよ……?」
「うそ」
見事な即レス。うぐ、と言葉を詰まらせると、「、噓つくの下手だから。すぐに分かる」そう言って、ルームメイトはトーストを早々に食べきってしまい、手を合わせた。トーストの下に敷いていたキッチンペーパーを片付けて、自分のとの分の水筒にお茶をいれながら、彼女は静かにこちらを一瞥する。
「言いづらいことなら、いい」
「そ、そういうわけでもないんだけど……」
話しづらかったわけでも、話す必要がないと思っていたわけではない。すぐに解決すると思ったら、案外そうでもなかっただけで。
それに元々、シブヤに引っ越してきてから、仕事のことは家に持ち込まないと決めていたのだ。ルームメイトにいらない心配をかけたくない。しかし、あの日のことがいつまでも心に張り付いて取れず、今までも無意識のうちに態度に出てしまっていたのかもしれなかった。
私としたことがとんだ失態。そうと決まれば、そろそろけじめをつけようか。「帰ってきたら……話しても、いいかな」はセメントで固めたような声でそう言うと、ルームメイトは満足そうに笑って頷いた。
ルームメイトは水筒の蓋をきゅっ、と閉めたあと、壁にかけてあったロングコートを羽織った。時計を見れば、もうすでに七時前。が最後のみみの部分までサクサクと齧って口に詰め込んだ後、玄関前まで早足で向かう。もうすでに靴を履いて準備をしている彼女は、四駅先にある工場で働いていた。
「いってらっしゃい。今日は早いんだね?」
「最近、なんだか忙しいから。夜も、少し遅くなる」
「そっかあ。帰りは気をつけてねー?」
ルームメイトはこくん、と頷く。「も、気をつけて。いってきます」そう言ってドアを開け、彼女は寒空の下に飛び込んで行った。ドアの隙間から入り込む凍てつく風にぶるっ、と両腕を抱く。がちゃん、と閉められたドアを見送り、さてと、と心を入れ替える。
今日は全国的に金曜日。午後から待ち受けている試練に向けて、今のうちにありとあらゆるシチュエーションを予想しておく。ルームメイトに良い報告ができるように、は「よしっ!」と一人になった2DKで気合いを入れたのだった。
昔から、自意識過剰気味に物事を考える癖があった。だから、周りよりも損をした生き方をしているのだと気づいてから、鈍いくらいでちょうどいいのだと思ってきた。しかし、最近は大きさ問わず色々なことが気になって仕方がない。特に、幻太郎のことで。にとって、彼は自分の雇い主というだけだというのに。
こんなこと、先生に知られたら気味悪がられるなあ。柚子こしょうをまぶした鯖をフライパンから皿の上に移動させながら、はぼんやりと考え事をする。においが強い鯖で食欲を誘う作戦に出たものの、いつでも食べられる鯖よりも待ってくれない締切の方が優先順位が高いのではないかと思えてきて、は今になって自身の浅はかさを呪った。
幻太郎の顔を最後に見てからひと月経つのではないかと思う。冷蔵庫に入れた夕食は次の訪問時にはなくなっているので、さすがに飲まず食わずというわけではないだろうが、やはり心配なものは心配だ。
そして、は意を決する。今日は、幻太郎の部屋に訪問しようと忍び足で廊下を滑る。ノックはしない。少しだけ……人の気配がするか窺うだけだ。部屋の前に着いたはさっそく、神経をドアの向こうに張り巡らせる。というかあれ? いつのまに張り紙が取れて――
「人の部屋の前で何やってるんですか」
「ひいぃッ……!?」
雷でも浴びたかのように、の体は天井に向かって跳ね上がる。勢い余ってバランスを崩し、硬い土壁にごんッ、と後頭部と背中をぶつけて、彼女は声にならない痛みに悶えた。
「せ、先生……っ。おッ、おつかれ……さま、です……っ」
口角を上げてなんとか明るく振る舞うが、心の中では号泣していた。振り絞って出した声はかなり情けないもので、どこの漫画の世界なんだろうと自分がみじめに思えた。
それ以上にのことを惨めに思っているであろう幻太郎はこちらを一瞥し、「今日は、食べますから」そう言い残して、を置いてすたすたと去ってしまった。えっ、待って、まだ頭ぐらぐらしてるのに……! は立ち上がって、ごつん、ごつん、とあちこちの壁にぶつかりながら、台所に戻って慌てて配膳を始めた。
居間の卓袱台に鎮座した幻太郎は、いつものようにが配膳している様を黙って見つめている。うわあ……先生とご飯だなんて久々すぎて緊張する。思わず手が震えてしまうが、せめてけんちん汁だけは零さないようにと、は全神経を指先に注いだ。
いただきます。二人で手を合わせる、いつも通りの食卓。鯖作戦が案外上手くいったのかな……。鯖ってすごい。明日の夕食も鯖にしよう。は骨を取り除きながらちまちまと鯖を口の中に運ぶが、正直ご飯を味わうところではない。沈黙に耐えられなくなったおしゃべりなは、やはり今回も気づいたら口を開いていた。
「げっ、原稿はどうですか?」
「今しがた脱稿しました。だからこうして出てきたんでしょう」
「そ、そうですよねぇー……」
だめだ。会話が続かない。それに、鯖の匂いは強いのにも拘わらず、味が全くしなかった。まるで、初めて先生とご飯を食べた時みたいだ。あの頃も食べた心地がしなかったなあ……。箸の持ち方や噛んだ回数を意識しすぎて、早食いのが生まれて初めて、「食べるの遅くないですか?」と言われた日でもある。あれ、私、この間まで、先生とどんな話してたっけ……。
「……居心地が悪いのなら、契約解消しても構いませんよ」
「へっ?」
唐突に耳に入ってきた言葉に、は顔を上げる。声の主である幻太郎は、ほうれん草の漬物を箸でひょいとつまみながら、そのまま言葉を続けた。
「先日、小生が変な絡み方をしたでしょう。今のあなたが蛇に睨まれた蛙のようになっているのは、それが原因では?」
「へ、ヘビに睨まれたカエル……」
「正直、あなたに何を言ったか覚えていないので、何か粗相をしたのであれば謝罪します」
「そっ、粗相だなんてそんな……! というか先生、何も覚えていらっしゃらないって……?」
少女漫画もびっくりして飛び出してきてしまうくらいのことをして……覚えていない? 本当に? は目を大きく見開くが、幻太郎は涼しい顔をしてけんちん汁の具を綺麗な所作で口に運ぶだけだった。
……なら、特に何も問題ないではないか? 予想もしていなかった事実は、の腹の中にすとん、と落ちてきた。あの件は、このまま自分の中に秘めておけばいい。それこそ墓まで持っていく所存だ。幻太郎があのことを覚えていたらお互いに居心地が悪くなってしまうのではと気が気でなかったが、彼が何も存じていないと言うのなら、話は簡単だ。自分が忘れればいいだけのこと。そう思ったは、幻太郎に向かって声高らかに言った。
「先生が社会的に訴えられることは何もしていないので安心してください! それに私は、先生が嫌でなければ、これからも先生にご飯を作って差し上げたいなと常日頃から思って――」
かしゃん。幻太郎が持っていた箸が落ちて、食器の上を跳ねる。ひえっ、先生の首ががくんと下がっておられる。さすがに引かれてしまっただろうか。顔を伏せたまま一向に頭が上がらない幻太郎をが焦りながら見守っていると、ゆらりと箸を拾い上げた幻太郎は大きく……それはもう大きくため息をついた。
「よくもまあ、創作上のキャラクターのような台詞をのうのうと……」
「は、はい?」
「なんでもありません」そう言って、幻太郎は今日初めて鯖を一口。彼の箸がぴた、と止まって、少しだけ瞳孔が開いたのをは見逃さなかった。
「今日の鯖どうですかっ? いつもの塩焼きにちょっとだけ柚子こしょうを入れてみました! あと、そこにある大根の煮物もいつもお醤油ばっかりなので今回は味噌ベースで仕上げてみたんです!」
「水を得た魚ですかあなたは」
「鯖はまあ……普通ですよ」はやった、と心の中でガッツポーズをする。幻太郎の口から“普通”以上のお褒め言葉をもらったことがないので、最上級のものだと勝手に思っていた。
物静かな幻太郎からなにかアクションがあるととても嬉しい。はえへえへ、とだらける頬を放置して、箸を動かした。鯖がさっきよりも濃厚に感じられる。あれ、今日のご飯すごく美味しい。えっ、もしかして私天才では? の心が吸い物に浮かぶ麩のように軽くなって、ふわふわと舞い踊る。数分前まで頭が爆発するくらい悩んでいたことが、今ではきれいさっぱり消え失せていた。という人間は極めて単純にできている。
基本的に、夢野先生宅は食事中にテレビを付けない。なので、が喋らなければ、途端に無言の時間がやってくる。しかし、今はもう意識しなくても言葉なんて無限にポップコーンのようにぽんぽんと湧いて出るので問題ない。はこれまでにないくらい有頂天だった。
「もうすぐ年の瀬ですねえ」
「そうですね」
「先生、今年のシフトはどうしますか? ご家庭によっては年末年始だけは依頼しないところもあるんですけど――」
「曜日通りで」
ぶれないなあ先生は。まあしかし、も年末年始にこれと言った予定はないので快く承った。おそらく、実家に帰っても何もすることがないし、仕事をしていた方が体が弛まなくていいので一石二鳥だった。
「ところで、先生は年末年始に何かご予定でも?」
「近所の神社に詣でようと思っていますが、いかんせん朝は弱いもので」
「あーあ。誰か暇な人が起こしてくれたらありがたいんですがねえ」と幻太郎がぼやいた。
「そうですよねえ……。あっ、じゃあ帝統君とか乱数君とかはどうですか?」
幻太郎のところで何回かフルタイムの家事代行を承った際に、彼の寝起きの悪さを知っている。善意百パーセントでそう提案するが、幻太郎はむすっと顔を顰めた。あ、あれ、私、また地雷踏んじゃったかな。
「せ、先生?」
「あなた、年末年始忙しいんですか」
「えっ? いえ、暇ですけど……」
しん、と謎の沈黙が降りる。一体なんなのだろう。幻太郎と話すのは久々なので勝手が掴めない。こちらから距離を縮めようとすると、三歩後ろに跳ねるようなお方だ。時には猫を扱うようにしなければ、気難しい幻太郎と良好な関係は築けない。
しかし、はエスパーではない。今の幻太郎がどんなことを思っているのかまでは分かりかねる。表情からして、何か快く思っていないことがあるのは薄々察せるのだが。
「……元旦に、フルタイムの家事代行を依頼します」
「えぇっ。どうしたんですか急に」
「何か不都合でも?」
「不都合だなんてそんな!」
「では決まりですね」幻太郎はいつでも突拍子にものを言う。は頭の中のスケジュール帳にささっと予定を書き込みながら、もしかして、と思う。先生は、私に依頼するタイミングを伺っていたのかもしれない。年末年始だし。いつもとちょっと頼みづらいだろうし。だからあんな百面相をしていたのではないか。
そんな気遣いのいいのになあ、と心なしか嬉しく思いながら、ふと頭に過ったことがあって、「あっ」とは声を上げた。
「でも、神社にお出かけされるんですよね? お戻りって何時頃になりますか? お昼前に食材の調達に行きたいんですけど、人様のおうちを留守にするのはちょっと……」
「未定です」
「えっ」
「そこまで言うなら、あなたも神社に来ればいいのでは? 帰りに買い物も済ませば手間もありませんし」
「あ、そっかぁ」
頭がいいなあ先生は。今のうちに何作るか考えておこう。それに、年明けてすぐに先生にご挨拶ができるなんて光栄だ。そう思っていたところで、はふと湧いた疑問を幻太郎にぽんと投げかけた。「ところで、」
「お出かけ……いわば初詣みたいな感じだと思うんですけど、私もご一緒していいんですか?」
変なことは言っていないつもりだった。しかし、その時の幻太郎の顔は今年一番と言えるくらい、それはもう圧が凄くて、は体をかちんこちんに固まらせた。それ以上喋るな、と言わんばかりに睨みつけられてしまい、あれえー……? とは首を傾げる。やはり、幻太郎の地雷はどこに埋まっているか分からない。元々掴みどころのない人ではあるが、そんな先生がこんなちんちくりんとよく契約してくれているなあ、と逆に感心してしまう。とにもかくにも、今この瞬間から、のすべきことがたった一つに絞られた。
「デ、デザート食べます?」
「機嫌の取り方があからさま過ぎるんですよ」