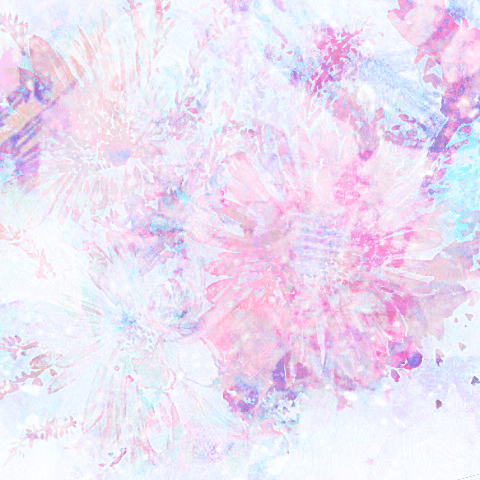Episode.3
手作りのタレでじっくり浸した唐揚げも、きらきらと光る炊きたてご飯も、瞬きよりも早く彼の口の中に消えていく。ピンク色の丸いものを連想させるその食べっぷりは、いつ見てもは圧倒されてしまう。
ご飯の三杯目を次いだのを最後に、彼は綺麗に箸を揃えて、ぱちんっ、と手を合わせる。「ごちそうさまでした!」まさに、生きとし生きる命を頂いた後の模範姿勢だった。
「っはー! 今日も美味かったあ!」
そうそうこれだよ~。この反応が見たかったんだよ~っ
「おそまつさまでした~」力の抜けた顔をしながら、は綺麗に空になった食器を盆の上にかちゃかちゃと置いていく。彼ほど美味しそうに食べてくれる人なんてそういない。この眩しい笑顔で「おかわりっ!」なんて言われてしまったら、ついついおかわりを注いでしまうのも無理ないだろう。ご飯、五合分炊いておいてよかった。
幻太郎の友人である帝統は、不定期でこの家を訪問してくる。時にはパンツ一丁で、時にはこの上なく幸せに満ちたオーラを纏って。今日は服こそ着ているものの、しぼんだ風船のようなげっそりとした顔をしていたので、は条件反射で自分の夕飯を彼の前に差し出した。
――「て、天使様ぁ……!」
冬の尻尾が見えてきたこの季節に体を震わせて、拝むようにこちらを見上げる帝統。彼と同い年でありながらも、はその瞬間母性を覚えたのだった。
「いやー! はすげーなぁ! こういうの、誰かに教えてもらったのか?」
「えへへー。ほとんど独学だよー」
帝統は純粋無垢な目をきらきらとさせて「すげーなあ!」と、のことを言葉でよいしょと持ち上げる。まるで神輿でわっしょいわっしょいと担がされている気分だ。うぅん、悪くない。は褒められるとぐんぐん伸びるタイプだ。
「なあ、……。実は、折入って頼みがあるんだけどよ……」
急にしおらしくなった帝統は、胡座をかいていた足をすす、と丁寧に折り始める。股を四十五度に開き、肘も綺麗な角度で曲げられて、その手は膝の上にお行儀よく置かれていた。まるで、新年のご挨拶でもするかのようだ。幻覚だと分かっていても、袴姿の帝統が目の前に見える。
帝統君って、こういう所作とか整ってるよなあ。勢いはすごいけど、箸の持ち方とか食べ方も綺麗だし……。ほう、とが感心するやいなや、ゴンッ、と畳の上に頭を擦り付けた帝統。は目が点になる。
あれれ。これ、初めて会った時にも見たような? は思わず自分の鞄をすす、と手元にやって、その中をごそごそと漁る。するとその途中で、帝統の頭上にできた影。「あっ」声を上げたの目には、今まさに彼を公開処刑にしようとしている断罪人が映っていた。
「五万……いや、三万貸し――ッ!」
「おおっと手が滑ったぁ~」
陽気な口調で帝統の頭上に辞書を落とす幻太郎。こんなにピンポイントで当たる手の滑り方とは一体。いや違う。明らかに狙いを定めていた幻太郎の眼差しを、はこの目でしっかり見ていた。
帝統の頭頂部と広辞苑が正面衝突する直前、は思わず目を瞑った。「いッ……てええぇぇええッ!!」響き渡る悲鳴。ああ、あれは痛い。例えるならば、棚の角に足の小指をぶつけるくらいの痛みだ。たぶん。も、帝統の痛みを半分味わったかのように顔をぐっとゆがめた。
「さすがは広辞苑。殺傷力も中々ですねえ」
「幻太郎っ! 人がお願いしてる途中で邪魔すんじゃねえよっ!」
「お願いだなんて易しいものじゃないでしょう。我々だけではなく女性にまでお金をたかるなんて……あなたには人並みのプライドはないんですか」
「そんなもん金と一緒に溶かしちまったぜ」
「そんな決め顔で言われましても」
幻太郎は重々しく溜息をつく。そして、すぐに目の色が変わって、その温度の下がった冷たい眼差しはに向けられた。明らかに人間を見る目じゃない。先生、私にもご慈悲をください。
「あなたも、毎度毎度帝統の口車に乗るなんて学習能力がないんですか? ほら、出した財布は仕舞いなさい」
「あ、えと……。はい……」
「おっ、俺の賭場代がぁ~……っ」
泣きそうになっている帝統を見て、少しばかり心が痛む。でもたしかに、お金の貸し借りってあんまりよろしくないよね……。ご、ご飯ならいくらでも作るからねっ。心の中でそう呟いて、は財布と帝統を見比べた。
「ギャンブラーにお金を貸すなんて、野良猫にエサをあげるようなものですよ。気まぐれに一度あげたら、二度目も期待して色目を使うんですから」
「い、色目って……。でも、見知らぬ人ならともかく、先生のお友達ですし……。それに、この前は三日と経たずちゃんと返してくれましたよ?」
「お友達……。帝統に何を吹き込まれたか知りませんが、その時は奇跡でも起きたんでしょう。今、帝統が小生に借りている額、教えてあげましょうか」
ちょいちょい、と指で招かれて、は幻太郎に素直に耳を貸す。吐息たっぷりの、ハートマークすら付きそうな口調とは裏腹に、唇を彩ったその金額はかなり暴力的だった。
さああぁぁっ、との顔が青ざめる。「分かりましたか?」と聞かれ、はこくこくと頷く他なかった。それは、が幻太郎の家で代行家業を半年勤めあげた金額をゆうに超えていた。
「それはそれとして……家主のご飯を他人に食べさせるなんて、立派な契約違反じゃないですか?」
「だ、大丈夫ですっ! 元々私が食べるものだったので! 先生の分はちゃんと取ってあります!」
「唐揚げもまだあつあつですよっ」は証拠だと言わんばかりに大皿の上に乗っている唐揚げを皿ごと持ち上げる。しかし、幻太郎はそれを見下ろすだけで、表情はむすっとしている。なぜかご機嫌ななめだ。家にお邪魔した時は普通だったんだけど……おかしいな。お仕事の最中、帝統君とお喋りしていて煩くしちゃったのかな。
今日、すごく上手く揚げられたんだけどなあ……。今日こそ美味しいって言ってもらいたかったんだけどなあ……。はしゅん、と肩を落として、大皿を卓袱台の上に戻す。先生、もしかして今夜は食べてくれないのかな。面倒くさい、お腹が空いていないと理由をつける日はたまにあるので(そんな日もサンドイッチかおにぎりを作って無理矢理夕食の道に誘うのだが)、今日はそういう気分なのだろうか。一食抜いても平気、という思想をもった幻太郎に対して、は胸に渦巻く不安を払拭できないでいた。
「……ああ、そういえば帝統。代わりといってはなんですが、台所に小生のへそくりが隠してあるので、見つけたら持っていっていいですよ」
「マジか!!」
その速さ、まさに光が如く。台所に駆けていった帝統の後ろ姿を見送って、はこの気まずい空気の餌食になった。待って帝統君。行かないで。美味しそうな唐揚げも、今は胃もたれの原因になってしまっている。
壁時計の秒針音がやけに耳に入ってくる中、幻太郎は静かに座布団の上に座って、手を合わせた。あ、食べてくれるんだ……。よかった~……。の中にあった不安の種がひとつ取り除かれる。しかし、居心地の悪さは変わらないもので、手持ち無沙汰の指をもぞもぞと動かしながら、所々趣深いしみのある壁をひたすら見つめていた。
「……随分と、仲良くなったようですね」
幻太郎の声が刺繍針のように細くなって、の皮膚をちくりと刺した。顔を上げれば、幻太郎はまるで何も言っていないというような顔をして、湯呑みをずず、と啜っている。主語がなくともなんとなく意味を察したは、こくこくと首を縦に振った。
が帝統と出会ったのは、幻太郎宅にて代行業を始めてから数ヶ月が経った頃だった。
――「お前、誰だ?」
――「えっ? せ、先生のおうちで代行業をしている者ですが……」
――「ふーん。そうやって待ってんのはいいけどよ。幻太郎、しばらく自分の部屋から出てこないぜ。このあいだ会った時に、今書いてるやつの締切が近いとかなんとかって言ってたし」
――「えぇっ!? じゃあ、ご飯も食べないんですかねっ?」
「まー。しばらくすれば出てくるんじゃねーの? つかお前、幻太郎待ってるあいだ、暇だろ? 時間つぶしがてら、俺とゲームしようぜ!」
――「ゲーム? あ、でも私、一応仕事中ですし……」
――「だーいじょうぶだって! 俺から幻太郎に言っておくからよ! つかタメ語でいいぜ。俺は有栖川帝統な。お前は?」
どこから出したか分からないトランプを持って、なにする? なに賭ける? わくわくしている彼の目がそれはもう眩しくて……というか帝統君もお顔が整っていらっしゃる。た、たしかに、食器を全部片さないと洗い物できないしなぁ……と思い、は帝統の約束にひょいと乗ったのが最初だった。あの時から、帝統はフレンドリーで勝負好きだった。ちなみに、初めて彼とやったスピードはが勝利した。
それ以降、タイミングさえ合えばは帝統とトランプゲームに興じることがある。が勝つ時もあれば、帝統が勝つ時もある。勝敗はおそらく五分五分だ。ギャンブラーでもゲームがはちゃめちゃに強いってわけじゃないんだなあ。帝統と神経衰弱をしながら、は密かにそう思った。
しかし、帝統が重要視しているものはそこではないらしい。彼とやっているのはトランプゲームという名の賭博。が賭けるものはきまって手持ちの飴とか自分にと用意した夕食だが、帝統は基本的に金銭を賭ける。(賭けるものがない時は上着とか靴下をくれる。ベルトを持っていた時は幻太郎に凄まじい目で見られた)。もちろん、トランプのゲームに勝ってもらったお金など使えるはずがないので、最近では『帝統君貯金』と銘打って、素寒貧の帝統が勝った時は、そこからお金を出して彼に返すことがしばしばあった。
――「……何をやっているんですか」
――「あっ。せ、先生っ。おつかれさまです!」
――「仕事中に遊ぶなんて契約違反ではないんですか」
――「え。あ、いえ、これは、その……」
――「あなたがそこまで不真面目だったとは……。家政婦としての意識が低いんじゃないですか? そういうことなら、お給料から相応の額を差し引いても問題ないですよね?」
――「んだよ幻太郎ー。混ざりたいならそう言えばいいだろー」
――「そういう意味ではありません」
どうして火に油を注ぐことを言っちゃうの帝統君。あとで怒られるの私なんだよ。幻太郎にごもっともな言葉でビシバシと叩かれて、解雇の二文字が脳裏に過ぎった。しかし、帝統との緩い会話の流れで減給も解雇も何事もなく終わったのでびっくりした。さすがは先生のお友達である。
――閑話休題。えっと、なんの話してたんだったっけ。……あ、そうだ。帝統君と仲良くやってるって話だった。
「はいっ。先生のことを待ってるあいだに色々な話をするので。あっ、このあいだは花札のルールを教えてもらいました!」
「花札なんてやる予定あるんですか」
「えっ? ないですけど、今後のためにも社会勉強……的な?」
「あなた、チラシを配る人間を邪険に出来なくて、大通りを過ぎる頃には鞄の中が紙くずだらけになっているタイプですよね」
「か、紙くずって……」
「あーあ。ああいう人懐っこくて、騒がしくて、ノリが軽い男に、世の女性は簡単にころっといってしまうんでしょうねえ」
ん? 今なんだか大半悪口に聞こえたような。なぜか幻太郎は、友人であるはずの帝統の評価がかなり低い。たしかに性格は真反対だし、相性の問題もあるだろうけれども、それにしてもあんまりな言い様だ。帝統はあまり気にしていないようだが。
……も、もしかすると先生、男としての尊厳を気にしていらっしゃる? たしかに先生はなんというか、いい意味で女々しいし、いい意味で小言が多いし、いい意味でみみっちい(は“いい意味”と付ければなんでも褒め言葉になると思っている)かもしれない。男女偏見はあまりよろしくないが、細かいことを気にしない帝統が傍にいると、比較してしまうのは仕方がないというか、なんというか。
しかし、先生はとてもかわいいのである。主に顔が。サブで顔が。漢というより美男子という言葉を首にかけてあげたい。いいじゃないか。かわいい男子にだって、世の女性はメロメロになるのだ。先生は自分の魅力に全然気づいていない。
は前のめりになって未だ茶を啜っている幻太郎にこう物申した。
「私は先生みたいに美青年でミステリアスでユーモアのある男性も素敵だと思いますよ!?」
「ごふッ……っ」
少しだけ茶を噴き出した幻太郎。は慌ててエプロンの中にあったハンカチを彼に渡した。
間違えた。今のは完全に間違えた。幻太郎が口元に付いた水分を拭いながらこちらを睨んでいる。こ、怖い。たしかに、軽率な発言だったことは認める。中高一貫の女子校で青春を謳歌していたに、男女のあれそれなど到底分かりはしなかったのだ。怖い。そんな親の仇のような目で見ないで頂きたい。こわい。
しばらくしてようやく落ち着いた幻太郎は、こふん、と小さな咳を零す。ちょいちょい、と人差し指で招かれるが、正直行きたくない。行きたくないが、の足裏はすでに畳の上を滑っている。
ああ、この一年とちょっとの時間で、私の体は先生の言うことに素直に従ってしまうようになってしまった。ちょこん、と正座をして、幻太郎の前に座り直した。本日一番の辛辣な言葉を受け入れる心の準備を整え、肩をぎゅっと窄めていた。
――黒い影が落ちる。ぐっ、と挟まれた頭に「へ、」と気抜けた声がの口から漏れた。
「っ、あいたたたたたたッ!?」
「わっちは吉原一の大太夫。落としたい男なんて星の数ほどいるでありんす~」
ぐりごりぐりごり。頭の左右を拳骨でこねくり回される。頭蓋骨マッサージにしては拷問的な痛みであるそれを、は悲鳴を上げながら受け入れるしかなかった。あれ、幻覚かな。楽しそうに微笑んでいる先生が見える。
頭が解放される頃には、ひいひいと情けない声を上げるばかりになった。水分の足りなくなった植物のようにへなへなと体を萎ませていくと、「……この馬鹿」と小さな罵倒が聞こえる。小声で言ったのは、きっと幻太郎なりの優しさだろう。しかし、の心はトドメを刺されたように砕け散った。もうあんなことは二度と言わない。言うもんか。は胸の中で粉々になった欠片を拾い集めながら静かに泣いた。
「げんたろ~っ! へそくりどこにあんだよ~ッ!」
「おや。意外と音をあげるのが早かったですねえ」
「コンロの下も食器棚の後ろも全部探したぞ! ……あ、も、もしかしてまた――」
「お察しの通り。もちろん嘘ですよ」
「こッ……こんにゃろ~~ッ!!」
家が賑やかだと、時間が過ぎるのがとても早い。
「じゃあな~!」額まで顔を赤くさせた帝統がぶんぶんと手を振っている。それがまるで犬の尻尾のようで、はついついにこやかになる表情を隠さずに、彼を玄関までお見送りした。随分とハイペースでお酒を飲んでいたので、本日の寝床に無事たどり着けるといいが。
引き戸を閉めて、も帰る支度をすることにした。残業なんて久々だ。しかも、まさか先生宅でだなんて夢にも思わなかった。時間ぴったりで帰っていた頃が懐かしい。
卓袱台に残っていた食器は片して洗い終わったし、酔いつぶれてしまった幻太郎は寝室に引っ張っていった。翌日、幻太郎が二日酔いで悩まされることがないように、薬と水だけ居間に置いて帰ろう。は玄関から居間に続く廊下を抜き足差し足忍び足でそおっと――
「かえるんですか」
かたん、と廊下に響く小さな音。は肩を小さく跳ねさせて、おそるおそる暗闇に目を凝らす。ゆっくりとこちらに近づく白装束……ではなく、着流し。ゆらり、ゆらり、と体を揺らして、距離を縮めてくる様はまさにホラーだ。壁を伝ってずるずると体を引きづり、足取りも覚束無い幻太郎を見て、は慌ててそれを制した。
「だっ、だめですよ先生! そんなべろんべろんのまま起きたら――」
「おくります」
「えっ」
先生、今なんておっしゃった? が驚いているうちに、幻太郎は玄関に向かって靴を履こうとするので、はさらにぎょっとした。
「こんな夜更けに女性を一人あるかせるほど、小生は鬼畜ではありません」
「だ、大丈夫です……!! 駅まで近いですし、あっ、なんならジョギングして――」
「なら、今日はとまりますか」
へ。が呆然とする中、色濃い影が近づく。
とん、と優しく肩に手を添えられて、耳に髪をかけられる。アルコールの匂いがつん、とにおう中、幻太郎の生暖かい息がほう、と首筋にかかった。
「僕と一緒に帰るか、うちに一泊するか……選んで」
悲鳴すら上げられなかった。鼓膜を直接振れるように届いた声と、輪郭にかかる細い髪の毛。どちらも、自分のものではない。心臓が煩い。幻太郎のお情けでもらった唐揚げと一緒に口から出てしまいそうだった。
か、かなり……酔っていらっしゃる。だって、こんなこと、普段の先生なら絶対にしない。したら、熱でもあるのかとまず疑う。あとは創作世界と現実世界が区別つかなくなったのかと心配する。帝統を呼んで肩を揺さぶってもらうかしてバグを治してもらう。とにかく、今の幻太郎は正気ではないことを念頭に、はごくりと喉元まできた心臓を飲み込む。上手くかわして、布団の上にスリーピング願おう。
自身の肩にぴっとり張り付いた幻太郎の体を両手で押す――押すが、動かない。えっ、重っ。酔っ払っているとはいえ、成人男性恐るべし。ぐっ、ぐっ、と前に押してもびくともしない幻太郎に対して、はついに声を上げる。
「せっ、せんせ――」
唐突にくんっ、と肩を前に倒されて、首に何か生ぬるいものが当たる。「ひえぇぇっ……!?」なに!? 今何か虫みたいなの這った!? の頭の中は大パニックだった。交通整理が行き届いていない事故現場のように、頭の至る所でクラクションがひっきりなしに鳴っている。怖いというよりも、なんというのだろう、どうしていいか、分からない。訳が分からなくて、指先にすら力が入らなくなってしまった。
「……冗談ですよ」
ふ、と熱が消える。ついでに、アルコールのにおいも。引き戸の透け硝子から差し込んできた月光に幻太郎の眼差しが反射して、は思わず生唾を呑んだ。もしかしたら、かぐや姫が帰ってしまう時、おじいさんとおばあさんはこんな気持ちだったのかもしれない、なんて思った。
淡い幸せの中に、一点の深い悲しみを見つけたような、せつない表情。幻太郎がなぜそんな顔をしているのかも分からなかったから、分からないことだらけで、すべてまやかしで片付けられるんじゃないかと、そんな逃避に走ってしまった。
「タクシーを呼んでおいたので、今夜はそれで帰ってください。お金はこの中に入っています。帰ったら連絡を入れること。あなたに何かあった時、小生のせいにされても困りますからね」
「えっ。あ、あの先生――ッ」
すとん。幻太郎は奥の部屋に引っ込んでしまって、音のない家に戻ってしまった。の手の中にあるのは、小さながま口財布。うんともすんとも言わないつめたいお金を見下げて、なんだかむなしくなってしまった。
――「……冗談ですよ」
どうして、先生はあんな顔をしたんだろう。口角は上がっているのに、悲しそうに眉は下がっていた。今にも雫が溢れそうな瞳なのに、目元はやわく細められていた。
なにが本当で、なにが嘘なのか。幻太郎の存在は、形も大きさも違うピースを日替わりで当てはめているようだった。加えて、毎日異なる絵柄が描いているパズルを、はいつまで経っても解けないでいた。完成の一歩手前……幻太郎の本質が見抜けると思った時には、目の前のピースはすでにバラバラに分かれてしまっている。
……“冗談”と“嘘”って、なにが違うんだろう。
ふと、が壁時計を見ると、もう零時を回っている。タイムオーバーだ。今日の幻太郎には二度と会えないことを悟って、は空虚になった心を埋めるように、がま口財布をぎゅうっと強く握りしめた。