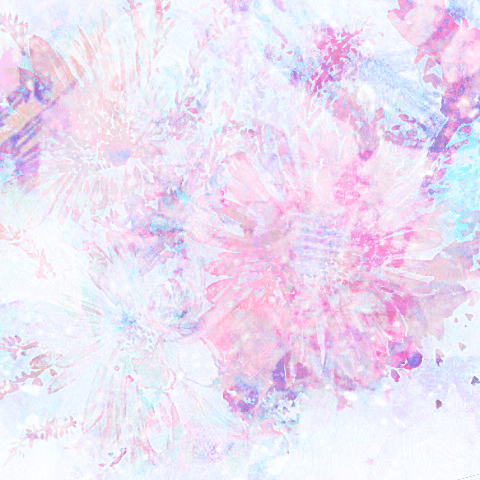Episode.2
は家事代行サービス会社に勤めている、いわゆる出張家政婦である。
小学生の頃に母親を亡くし、仕事で忙しい父親の代わりに、家のことはが率先して行っていた。掃除や洗濯はもちろん、ランドセルを背負いながらスーパーに寄って、買った食材で朝夕のご飯を作るのが日課だった。
高校在学時に家事代行会社の存在を知って、はそこに就職を見据えて進路希望調査の紙を提出した。部活に明け暮れていて、特にやりたいことがなかったということもそうだが、人のために得意分野が生かせるのなら願ってもないことではないか――楽観的にそう思っていた学生時代を経て、今のがある。
もちろん楽しいことばかりではないし、休みも不定期だ。そろそろルームメイトと駅前に出来た台湾発祥のタピオカのジュースが飲みたい今日この頃だ。しかし、総合的にみても、は今の仕事がとても好きだ。実際、仕事場に向かうの足はとても軽い。今日の目玉である梨がとても安かったのもその理由の一つである。幻太郎の財布もにっこりだ。そして、その梨をゆくゆくは寒天ゼリーに化かすも同じくにっこり笑顔だった。
そうこう思っているうちに夢野幻太郎先生宅、着。秋の足音も日に日に近づいてきて、椛がじわじわと暖かい色に色付く季節になった。どこからか香ってくる金木犀の匂いに顔を綻ばせながら、は幻太郎から渡されたお金で買った食材を使って、今夜も素敵な夕食を振る舞うのである。
「先生、遅いなあ……」
数時間後――作り終えたものを配膳したが卓袱台の前に待機していても、幻太郎の足音はちっとも聞こえてこなかった。いつもならのっそりと出てきてくれるのに。
ご飯、冷めちゃうなあ。ほくほくと湯気を上げる肉じゃがを一瞥して、数分悩んだは、意を決して幻太郎の自室へと足を運ぶことにした。
――「この部屋には絶対立ち入らないでください」
幻太郎がまだ雪の女王のように塩対応だった頃、そう冷たく言い放たれた思い出がの脳裏に過ぎる。あの頃の先生の目、人間を見てる感じじゃなかった。道に捨てられてた残飯を見るような目だった。しかし、幻太郎のそんな対応もある日を境に変わる。
あれはそう……去年の夏にが熱中症で倒れた時のことだ。目が覚めたら、はちゃっかり幻太郎の部屋で横になっていたことがある。きっと彼が運んでくれたのだろう。体調が回復してから、申し訳ない気持ちで畳に額を擦り付けて謝罪したのだが、「顔色が良くなったかと思えば、第一声がそれですか」「そんな余裕があるくらいなら水を飲みなさい」そう吐き捨てるように言われて渡されたペットボトルの水は、まるで買いたてのように冷たくて、からからだったの喉を一気に潤した。
あれから、幻太郎の部屋には一度も足を踏み入れていない。そもそも、掃除代行ならともかく、ここでのの仕事は調理代行が主体。基本的な行動範囲は玄関と台所と居間に限られる。必要外のことをしている罪悪感を抱えつつ、は廊下の床にすりすりと足の裏を滑らせていった。
離れにある幻太郎の仕事部屋は、ドアの前に立った時点でどこか重々しい雰囲気を感じざるを得ない。がそう錯覚しているだけかもしれないが、開かずの間というのか、踏み入ってはいけない異世界への入口のような感じがして、の全身の毛がごわごわと逆立ち始める。
そして不運なことに、がノックをしようかどうか躊躇しているあいだに、目の前のドアが無慈悲にも開かれてしまう。そこに立っているのは、いつもの書生の格好をした幻太郎。随分と座った目をしていらっしゃる彼を見て、は猫のようにびゃっ! と体を震わせた。
「すっ、すみませんお仕事中に……ッ! ご飯できたんですけど、まだ食べないなら冷蔵庫に入れておこうかと思ってっ――」
ひどく重たそうに瞼を持ち上げている幻太郎。「ああ……もうそんな時間ですか」そう言って、色素の薄い茶髪を片手でくしゃりと握った。声もどこか枯れているし、今まで寝ていたのだろうか。不機嫌そうには見えないが、もしかして睡眠中に起こしてしまったかとは内心ひやひやしていた。視線をおどおどと彷徨わせながら幻太郎の反応を窺っていると、逆になぜか頭の上からつま先まで舐めるように彼に見られる。その後、幻太郎は部屋の奥にある椅子にぎしりと座った。
「そこの娘、近う寄れ~」
えっ。なにごと?
は思わず周りを見渡して、自分以外に誰もいないことを確認する。わ、私ですか? と言わんばかりには自分のことを指差した。「そち以外に誰がおるのじゃ~。阿呆なのかえ~」かなり辛辣な殿様である。幻太郎はこちらに向かって手を招いているので、おそらく部屋に入れと言っているのだろう。
一度は出入りを禁止されていた部屋。はごくん、と生唾を呑む。まるで、地雷源が埋もれている地面を歩くかのように、そろりと部屋に侵入した。部屋に置いてあるのは、机の他に箪笥と本棚だけ。その本棚に敷き詰められている本はどれも分厚く、おそらくでは理解のできないものばかりだと思われた。
……だめだめ。人様の部屋をまじまじと見たら。は俯きながらちょこちょこと小股で歩を進める。そして、視界の端に幻太郎の足袋が入ってきたところでぴたりと止まった。
がゆっくりと顔を上げると、幻太郎は顎に指を添えながら何か思案しているようだった。改めて見ると、先生ってほんとにお顔が整っていらっしゃる……。がぼんやりと俳優泣かせな幻太郎の顔面を見つめていると、彼は椅子からすくっと立ち上がって、部屋をぐるりと一周するようにゆっくりと歩き出した。
「……あなたは前世、右側が水晶、左側が砂の星で生まれた一人の娘。砂漠が広がる地域で、小さな料亭を営んでいました」
「へ?」
唐突に始まった夢野名作劇場。いきなり自分の前世の話をされて、の頭の上はクエスチョンマークで溢れた。あれ、先生って小説家じゃなかったっけ。いつから占い師に転職したんだろう。
「ある日、砂漠のど真ん中で倒れていた男を見つけたあなたは、彼に料理を振る舞いました。しかし後に、その男について分かったことがあります。なんと、彼はその星では名高い盗賊だったのです」
何が何だかさっぱり分からない。やはり、ここは異世界の入口だったのかもしれない。どこか酔ったように宙に向かって語る幻太郎が、の手を引いてどこか別の世界に連れ出そうとしているようだった。
胡麻のようになった目で、唖然呆然としている。すると、幻太郎は生き生きとした表情から途端に色をなくした。あ、いつもの先生だ。
「……今書いている原稿が行き詰まったので、少し趣向を変えてみようかと。小説家には、時折こういうインスピレーションが必要なんですよ」
「な、なるほど……?」
全然なるほどと思っていないが、雰囲気でそう言わざるを得なかった。とりあえず分かったことは、今語られたものは幻太郎の次作となる物語ということだけだ。
「今から小生がその盗賊役をやるので、あなたは料亭の娘になりきってください」
「えっ!? なっ、なんでですか!?」
「言ったでしょう。インスピレーションが必要だと。ものの数分、小生の創作活動に付き合ってください」
「むっ、無茶ですよっ! 私、演技とかめちゃくちゃ下手くそですし! なんなら文化祭の時とかも衣装作る係とかでしたしッ!」
「ああ、そのまま壁際に立ってくれます?」
「せめて聞いてくださいよう!!」
「悲し悲し……。あなたが言うこと聞いてくれなければ、小生は夕食にありつけず、空っぽになった腹をさすりながら朝までこの机に縛りつけられることに――」「やりますっ! ぜひやらせてください!!」空腹ダメ絶対。の体は瞬時に壁際に寄った。これがいわゆる職業病なのだろうか。いや、なんか違う気がする。こんな風変わりな依頼なんて、おそらくどのご家庭に行ってもないだろう。
すると、幻太郎も壁際にそそ、と寄って、を壁とサンドさせるように向かい合う。まるで値踏みするような眼差しを送られて、はどこかぎこちなさそうに両手の指をもぞもぞと交差させた。
「え、えぇーと……。ちなみに、これはどういうシチュエーションで……?」
「言ったらリアリティに欠けるので雰囲気で察してください。……ああ、無理して見るに堪えない演技をしなくていいですよ。あなたが思ったことをそのまま言ってくれれば結構です」
それなら私でなくてもいいのでは……? 思わずそう口走りそうになったが、はこういう芸術面についてはさっぱり分からないので――自慢ではないが体育と家庭科以外の成績は凄まじいものだった――口は災いの元、この唇は固いチャックで閉めておく。
先生は盗賊、そして私は先生を助けた娘……話のあらすじを頭の中でぐるぐると回していると、突然、幻太郎がの頭上の壁を強く殴った。ドンッ、と鋭く怒ったような音に、は肩をぎゅうッとすぼめる。
おそるおそる幻太郎を見上げると、そこには殺気に満ちた目で見下ろす幻太郎――いや、一人の盗賊がいた。
「……俺の懐から財宝を盗むなんざ、いい度胸してるじゃねえか」
「いきなりド修羅場!?」
のメタ発言甚だしい叫びも聞こえていない……いや、聞こえていないふりをしているようで、彼は訝しげな目でこちらを見つめている。そして、の首元に当てられた一本の万年筆。あ、これ絶対ナイフだ。だってペン先すごく鋭いもん。黒いインクが猛毒と言わんばかりに光ってるもん。すっかりその気になってしまったは見も知らぬ娘になりきって、ドラマから得た知識で必死に言葉を探した。
「え、えぇっと……ッ。ご、誤解です……っ! 私があなたの財宝を盗むわけないじゃないですか……!!」
「へえ? なら、お前のカバンに入ってたこのスカーレットの宝石はどう言い訳するんだ? 俺に近づいたのも、どうせ俺が持ってる財宝目当てだったんだろ」
違います。反射的にそう言おうとしたら、少し物憂げに伏せられた幻太郎の目。その瞳の中で薄紫と翡翠の色がマーブル状に交じっていく。その様を、は一種の芸術を鑑賞するように見惚れしまった。え、あの、先生、実は子役とかやってらっしゃいましたか。むしろ今現役でいらっしゃいますか。
「互いの夢を語り合いながら、一緒に月を眺め、口付けを交わしたことも……俺じゃなくて、すべて金目のものが目的だったって?」
「くッ、くくくくく口づけッ!?」
口づけだなんてハレンチな! 二十歳になったばかりの私には刺激が強すぎるのではないか。というか、盗賊さんと娘って、も、もしかして、そういう関係……? の思考回路はすでにショート寸前である。このままではバッドエンド待ったなし。恋愛遍歴が絶望的なは、架空の世界からそれらしい台詞をなんとか引っ張り出して、喉を震わせた。
「わ、私はッ、あなたの大切にしてるものは盗めませんし、あなたを騙そうとも思ってないですし……! その宝石だって、きっと誰かが勝手に――ッ」
「入れたってか? 誰かってなんだ? 鼠か? 蛇か? 蠍か? そもそも、そんな嘘話を俺が信じると思うか? 盗賊の俺を弄んで、今までさぞかし面白かっただろうなァ」
あまりにも救いのない展開に泣きたくなってきた。私って、本当は家政婦じゃなくて料亭の娘だったのかな。盗賊の財宝を盗む度胸なんてないのに、本当は知らないところで盗んでいたのかな。
……いいや、違う。きっと違うぞ。娘はそんなことしない。いや、万が一していたとしても、胸に秘めている心だけは本物のはずだ。
すっかり娘が憑依していたは勢い余って、盗賊の胸倉を両手でぐっと握りしめる。すると、マーブル状だった彼の瞳の色が分離して、目の奥に一人の女の顔が映った。あ……娘がいる。そんなことを胸の隅で思いながら、ひどく驚いた表情をしている彼の端正な顔に、はこう言い放った。
「私が何を言ってもあなたはきっと信じないでしょうが、私があなたをお慕いしている事実は本物ですっ! これはっ、目に見える財宝と違って誰の手にも触れられないし、私以外の誰かでは変えられないものですッ!」
しん、とやり場のない沈黙が落ちる。幻太郎の眼光が途端に緩やかになって、なぜか呆然とした顔でを見下ろしていた。あれ、私、何か間違えた……? 首を傾げたが幻太郎の顔を覗きこもうとするも、彼は黙ったまま動かない。
「あ、あの、せんせ――」
「ていッ!」
唐突に飛んできたチョップ。じりじりと焼けるような鈍痛には頭を抑えた。
「あいっ、たぁッ!?」
「まったく……。なぜあなたの方が熱くなってるんですか」
「だっ、だって先生がやれって……!」
「いくら演技とはいえ、いい歳してあんなこと言って恥ずかしくないんですか? はーやだやだ」
「理不尽の極み!!」
一生懸命演じたものを馬鹿にされて、これ以上にない羞恥で顔から火が出そうだった。ひどい、ひどすぎる。
「本当にあなたという人は……」きっと、聞いていた幻太郎も赤くなるほど恥ずかしかったのだろう。彼は口元を袖で覆って、こちらを見ないように目を逸らしている。悲しい。は非常に悲しい。穴があったら入って一晩中泣いていたい。
じんじんと痛む頭を抑えながら、「早くしないとご飯冷めちゃいますよう……」と雨に濡れた子犬のような佇まいで、は幻太郎を居間に誘導した。
卓袱台の前に着席した幻太郎と一緒に、はちまっと手を合わせる。頼まれたこととはいえ、数分前の自分はきっとどうかしていた。自分がこの口で言ったことを思い出すだけで、両手足をじたばたさせて暴れたくなってしまう。いっそ口の中を大火傷したかったのに、熱々にしたはずの肉じゃがは時間が経ち、程よくぬるくなって食べやすくなってしまった。「ああちなみに……」
「誤解があっては嫌なので言っておきますが、この二人は恋仲ではありませんので」
「えっ! あれ、恋愛小説じゃないんですか!?」
「そんな体が痒くなるような話を小生が書くわけないでしょう。別々の星に住む男達が同じ船に乗って旅をする冒険譚ですよ。さっきのものは、内一人の外伝です」
そんなことをさらっと言われて、は拍子抜けだった。それではさっきのプチ劇場は、てっきり恋愛ものかと思って、あんな恥ずかしい台詞を言った自分の完全にひとり遊びだったということになる。
「も、もう二度とやりませんからねっ!」「小生もあんな心臓に悪いこと、二度と頼みません」先生にそう言われてしまうと、なんだか私が悪いことをしたみたいだ。ちがう、被害者は絶対私だ、とは保守的になりながら暗示をかける。
「ちなみにあの後、二人はどうなるんですか?」
「さあ」
「さ、さあって……」
「気になるなら書店で買えばいいでしょう」
まさに正論。腑に落ちない胸を沈めるように、は胡麻とほうれん草のおひたしをちまちまと口に運ぶ。ピリ辛にしようと入れた鷹の爪が、の胸をちくちくと刺した。
一ヶ月後、はさっそく出版された例の本を書店で購入した。普段は料理本しか捲らない。文学に肥えていない目には、その本の内容は少々難しく映った。
しかし、断片ながら物語の概要は把握できる。特に、盗賊の彼は娘に対して特別な感情を抱いていたらしい。しかし、それが親愛なのかなんなのか、作中で一度も明かされることなく、さらに言えば、彼自身もその感情に名前を付けられないまま、砂の星を旅立ってしまった。
娘とのあの一悶着は、砂の星を旅立つ際に一切の未練を残すことのないようにするための、彼が娘についた嘘。スカーレットの宝石は、彼自ら彼女のカバンに入れたものだったのだ。
メインが三人の男の話なだけであって、やはりその他のキャラクターは個性があるも、それぞれの別れのシーンはどこか殺伐としている。まさに一期一会。主要の三人は一緒の船に乗っていても、隣り合わないジグゾーパズルのようにばらばらで、協力というより利害の一致で今この時だけ一緒にいるような印象を受けた。なのに、三人以外の誰かをその船に近づけようとはせず、彼らだけでどこか不思議な形をした縁を描いているようで、こんなにも不思議な繋がりもあるんだなあ、とはページを捲りながらしみじみ思った。
途中から地の文を読み飛ばしながら、台詞だけで物語の大筋を把握していく。ただ、盗賊と娘のシーンだけは一文字一文字舐めるように読んだ。というか、あれ? この台詞、私が前に言ったことそのまま――
「まだ読んでいるんですか」
背後から聞こえた声にぎく、とは体を揺らす。今はちょうど夕食が終わって片づけも済ませた頃。自由時間として幻太郎に与えられたひとときだった。
「それ、もう随分と前から読んでますよね」まだ読破できてないんですか、と言いたげな顔で、幻太郎が呆れたように温度の低い眼差しでこちらを見下ろしている。遅読なのは謝罪するが、そんな冷たい眼差しで見下ろさなくてもいいのではないか。は本を庇うようにして、それを胸の中にぎゅっと収めた。
「私、普段は漫画とか雑誌くらいしか読まないんです。こういう本を読むのだって、高校の課題以来ですし……」
「今回の話は比較的易しく書いたつもりでしたが……。やはりお子様には難しすぎましたかねえ」
うぐ、とは言葉を詰まらせる。幻太郎の言っていることはごもっともなのでその件については何も言うまい。ただ、せっかく目の前に著者がいるのに感想の一つも言えないことがくやしかった。
素敵な話ですよ。すごく感動しました――どれも語彙力皆無の陳腐な言葉だ。これでは幻太郎に鼻で笑われて終わってしまう。どうにかして、彼を一泡吹かせられるような言い方はできないものか。は頭の中にある薄い辞書をペラペラとめくって、パズルのように拙い言葉を次々と組み合わせていった。
「で、でもっ! 大切なものばかり失ってきた盗賊さんが、王様の手を取って、いろんな星を巡ろうとするシーンはすごく感動しました!」
私のバカ。どうしてもうちょっと頭良さげな気の利いたこと言えないのかなあ!
しかし、これもまたの本心である。盗賊である彼の過去は凄まじいものだったせいもあって、生まれ育った砂の星も、自分を守るために鍛えてきた生き方も何もかもを捨て、彼は新しい世界につま先を向けた。はつい感情輸入してしまって、物語はまだ中盤に差し掛かったところだが、つい涙ぐんでしまったのである。
というか、王様すごくいい人。盗賊さんを見つけてくれてありがとう。科学者さんも盗賊さんのこと気にかけてくれてありがとう。そんな母親目線になりながらじーん、と思っていると、幻太郎は出会った当初のように顔をぐっと歪めて、絶対零度にまで冷えた目線をに刺した。えっ、どうして。
「あれだけ娘になりきっておいて、娘本人のことはかなりぞんざいな扱いではないですか」
「そ、それは、その……。たしかに、娘は報われないかもしれませんけど……彼が選んだ道ですし、物語の展開的に必要だったんじゃないかと……」
物語は三人の男を軸に動く。娘は、その歯車達を塞き止める異物のような気がして、読んでいてどこか違和感があった。しかし、その異物が外れた時、従来よりも歯車に勢いがついてより早く回り出した。
きっと、娘の存在は料理でいう隠し味のようなものなのだろう。名も知られない、ただ一縷の時に生きた存在だったとしても、ないよりはいい。そんな彼女のおかげで、盗賊の彼は一際輝く主人公になれたのではないか。
しかし、思うことがあるとすれば……一つだけ。はこの本の世界の神様である幻太郎を眩しそうに見上げた。「先生、」
「娘さんは本当に……最後まで彼の嘘に気づかなかったんでしょうか」
娘は、盗賊の彼に何度も騙されていた。ある時は無害の植物を猛毒だと言って怯えさせたり、ある時は料理に虫が入っていたといちゃもんをつけて謝らせたり……それでも、娘は盗賊の彼を慕っていたし(やはり、彼女の方も恋に落ちただとか、そういう描写はなかった)、そんな彼の変化を見逃すほど、娘が抱いていた彼への想いは軽薄なものだったのだろうかと、読者であるは不思議でならなかった。
にとっては純粋な疑問だったのだが、一方、幻太郎の態度はどこか素っ気なかった。ふっと軽く息をついて、耳元で飛ぶ小バエを払うかのように、こう言い捨てた。
「……あなたが気づかなければ、彼女もまた、本の中でそうやって生きていくでしょう」
彼が抱いていた感情も……何もかも知らないまま
幻太郎が言うことは、時々難しい。質問には答えてくれたが、結局、にはその言葉の意味を汲み取ることができなかった。帰路の途中、は幻太郎が言ったことを頭の上でくるくると巡らせながら、首を捻る。
つまり、物語は想像の上で成り立つもの。紙の上に散りばめた言葉の意味も、行き止まりになった文字の先にある結末も……すべて読者の自由ということなのかもしれない。読者の数だけ物語は四方八方に展開し、それこそ、作者である幻太郎でさえ分からない方向に行くのだと。
あの物語の神様である先生も分からないなんて、なんだか切ないなあ。センチメンタルになった気持ちを秋のせいにしながら、は夜空に浮かぶ光の中で、彼らが次に降り立つ星を探していた。