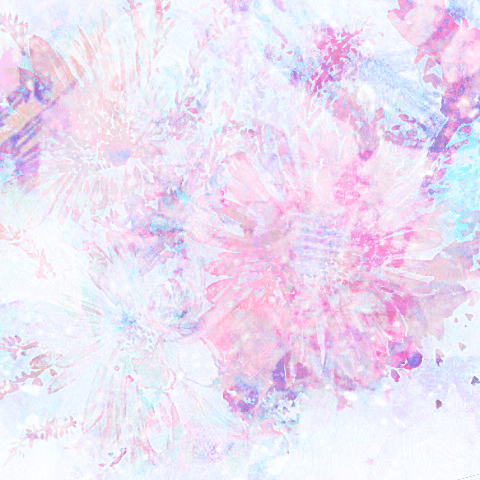Episode.1
乾いた蝉の声がいくつも重なっている。彼らの大合唱ステージを通り過ぎたのはこれで何度目だろう。耳がそろそろおかしくなりそうだ。加えて、本日のラストスパートと言わんばかりに、うだるような熱気が頭上からじわじわと襲いかかってきて、は首筋に伝う汗を何度も見送った。
ふと顔を上げれば、半熟の黄身のような色をした夕日が、飴色の空にくっきりと浮かび上がっている。美味しそうだ。今日の戦利品が入ったエコバッグをがさがさと揺らしながら、は急くように一際大きな一歩を踏み出した。
一軒の日本家屋の前に到着すると、は家主から渡されている鍵を穴に差し込む。もう何百回と繰り返してきたことだ。
思えば、この家に初めて訪れた時は驚いたものだった。会社の代表から小説家のお宅だと聞いていたので、てっきり四十代くらいの気難しそうなおじさんが出てくると思って心の準備をしていたら、インターホンの奥から聞こえたのは六十代くらいの老人のしゃがれた声。おまけに、「はて……。この家にはユメノという人間はおらんがのう」と言われたので、は初出勤早々家を間違えたと顔を青ざめたのだ。
「しっ、失礼しましたっ!」慌ててインターホン越しに謝罪をした後、は代表から送られたメールに記載してある住所を見比べた。それからぐるぐるとご近所を歩き回ったが、やはりどうあっても先ほどの家に辿り着いてしまう。迷いに迷ってかれこれ一時間。花粉がかなり辛くなってきて、鼻も目もぐずぐずになる。万事休すのがその家の前で途方もくれていると、玄関から不機嫌な顔をしたイケメンのお兄さんが出てきたので、かなり驚いた。さっきのおじいちゃんのお孫さんだろうか。は非常に焦った。この近辺を徘徊している不審者だと思われたに違いない、と。
――「ああああああのっ! 私、決して怪しい者では――ッ」
――「小生が夢野幻太郎です」
――「え゙」
悲鳴に似た声を上げたの目玉は地面にぽろりと落ちて、ビー玉のようにころころ転がった。
あれから約一年半――引き戸をカラカラと開けると、白檀の匂いがぶわんと顔に向かって飛び込んでくる。いつ来てもおばあちゃん家のような匂いがして夏休みの学生気分になれるので、はとても好きだった。
「おじゃましまーす……」
家主の気が散らないように声を潜めながら、サンダルをごそごそと脱ぐ。家に上がってからもその足はこそこそと忍んでいたが、方向に迷いはなかった。
長い廊下を進み、右に曲がって、申し訳程度の段差を下りたところがの仕事場という名の台所である。日本家屋でもさすがに釜戸ではなく、一般家庭でよく使われるガスコンロが設置されている。雇われたばかりの頃のはそれを知ってほっとしたものだった。飯盒の炊き方は知っているが、さすがに釜戸の使い方までは存じてなかったのだ。
手を洗った後、はまるで出店でも開くかのように、買ってきた食材をエコバッグから次々と出しては机に並べていく。今夜使う食材だけを残して、後は冷蔵庫に保存。棚にかけてあった戦闘服ならぬ割烹着を装着し(自前ではなく、幻太郎の好意で貸し出してくれている)、はふんす、と腕を捲って、仕事に取りかかった。今の時刻は十七時。目指すタイムリミットは二十時前だ。
しゃかしゃかと三合分の白米を研ぎ、鍋に投入(炊飯器もあるが、鍋の方が時間がかからないしなんとなく美味しい気がするので、は普段から鍋炊き派である)。火加減を調節した後、本日の主役である豚ロース肉としその葉っぱを手に取った。塩こしょうの味付けをした肉の上に葉っぱを置き、棒状にくるくると丸める。あとは塩こしょうの味が肉全体に浸透するまで放置。そのあいだに、主菜と汁物、そして副菜の食材をひたすらザクザクと切っていった。
調理がひと段落ついた頃。洗い物を終えたはようやくほっとひと息。休憩ついでに、ちょうど炊けた米をしゃもじでぐるぐると混ぜていると、足の裏からギシギシという振動を感じる。はたとしたは、台所の出入口に顔を向ける。そして、暖簾の下から覗いた足袋を見るやいなや、ぱあっと顔を綻ばせたはしゃもじから一度手を離した。
「夢野先生! おつかれさまです!」
「ご飯、もうすぐできますよ~!」は暖簾から顔を覗かせて、台所を通り過ぎた後の背中に声をかける。ほんの少しだけこちらに首を傾けた幻太郎の目は、先日調理した真鱈のようにぬぼーっとしていた。案の定、彼は一言も発さず、前を向いてよたよたとした足取りで廊下の突き当たりへと歩いていく。
これはまた……。今回もかなりの修羅場だったようだ。は心の中で再度彼を労いながら、暖簾から顔を引っ込めて仕事に戻った。
雇われて間もない頃は、よく大声を出しては幻太郎に顔を顰められたものだが、最近はそういうこともぱったりなくなった。というのも、あまりにも挨拶する度に不機嫌そうに顔をゆがめられることが多かったので、は必要最低限の音量で……いわゆる省エネモードで仕事に取り掛かっていた。
すると、とある日の食事の最中――幻太郎にこう言われたのだ。
――「……あなた」
――「はいっ」
――「体調が悪いのならここに来ないで頂きたい」
――「へ?」
――「わざわざ病原菌をこの家に持ってきて、小生に移したいのですか」
はきょとんとした。そして、そんな彼女を見た幻太郎もきょとんとしていた。いつもより大人しくしている理由を話したら、幻太郎は狐に化かされたような顔をして、いつも騒がしい人間が静かだと落ち着かないと吐き捨てるように言ったのだ。
――「……では、気分が悪いわけではないんですね」
――「全然ですよ~! これでも私、小中高と無遅刻無欠席だったんです!」
幻太郎の言葉に、はうんうんと頷く。すると、顔を隠すように片手で覆った彼はそれきり何も話さなくなった(心なしか、耳が腫れたように赤くなっていた気もする)。かなりお堅い人柄かと思っていたが、こちらの体調を意識してくれているということは、案外そうでもないかもしれない。はその一件で、少しだけ彼の印象を改めたのだった。
――閑話休題。ほかほかと湯気を立てた料理を盆に乗せて配膳。居間に足を踏み入れると、もうすでに幻太郎は卓袱台の前に着席していた。卓袱台の上に慎重に盆を置いたは、あるべき位置にきちんと皿をせかせかと置いて、彼に箸を渡す。
こういう場合、雇われ主の夕食は余った食材をまかないとして食べたり、家主と一緒に食べたりと各家庭によりけりだが、彼はどちらでもいいとのことだった。いつぞやに、普段夕食はどうしているのかと聞かれて、先生にお出しする前に台所でちゃっちゃと食べてますよー、と伝えたら、「わざわざそんなことしなくても一緒に食べればいいじゃないですか」と言われて、はそれはもう驚いた。だって、そういうことを許してくれなさそうな人に見えたものだから。そして、なぜかそれを言ってから彼自身も驚いていたようだった。言った本人なのに、どうしてあんなに目を見開いていたのか分からないが、それ以降、はこうして幻太郎と同じ食卓で夕ご飯を食べている。やはり、一人で食べるよりもご飯の味がより美味しく感じられて、はとても嬉しく思った。
幻太郎との食事は、しばらく無言で食べるのが暗黙の了解だ。ご飯の時は喋りたい派のだが、幻太郎との関係は雇用人と契約者であり、一緒に食べさせてもらっている身……そこは家主のペースに合わせるのが定石である。
茶碗蒸し風のたまごスープ、今日はちょっと薄味だったかな。でも先生は薄味がお好きだしちょうどいいかな――黙っている間、はこんな風に一人反省会を開く。そして、幻太郎がすべての料理に少しずつ口を付けた後、なんとなく、彼の周りに張り巡らされていた固いオーラがふつりと解かれる時がある。雑談許可の合図だ。そのタイミングが分かったのは、がここに来て一年が過ぎた頃だった。
「八月も終わるとはいえ、まだ残暑が厳しいですねー」
「ええ……。おかげで蒸し暑くて敵いません」
相変わらず視線は合わないが、返してくれる言葉は幾分穏やかだ。は次々とご飯を口に運びながら、胸に秘めていた話題をぽんぽんと口にした。
「そういえば今年、羽のない扇風機を買ったんですよー。わざわざ分解してお掃除しなくてもいいですし、来年から先生のところも一台どうですか?」
「原稿が飛ぶので、小生はエアコン一択です」
確かにそうだ。はふむふむと納得する。それからもの口から生まれる話題は尽きることなく、幻太郎に話をし続けた。ここに来る途中で子猫が伸びをしているところを見て癒されたこと、落ちていた蝉が鼠花火のように突然動き出してダッシュで逃げてきたこと、すれ違った小学生が背負っていたカラフルなランドセルにとても驚いたこと――幻太郎は聞いているのか聞いていないか分からない表情で、黙々とご飯を食べているが、話を途中で止めたりすると、「……それで?」と、こちらの様子を一瞬窺うのだ。少し分かりにくくて誤解されやすいだけで、の知る彼はとても優しい人なのである。
すると不意に、食事の途中で幻太郎が珍しく顔を上げた。なんだろう、とは首を傾げる。彼は、「……これはなんですか」と目の前に置かれている小さなお皿に視線を落とした。
「かつおときゅうりの甘醤油あえです。アクセントで胡麻もまぶしてみました! 他のお宅で振る舞ったら、結構好評だったんですよ~」
「ふぅん……」と小さく声を漏らした幻太郎は、それをまた一口運ぶ。そういえば、彼の家でこの品をお披露目するのは初めてだった。
「ど、どうですか……?」
思わず慎重に聞いてしまう。特に、幻太郎は表情が読み取りにくい。はどぎまぎとしながら幻太郎が咀嚼している様子を見守っていると、彼は箸を置き、裾で口元を隠しながらこう言った。
「んん~。麿の舌が踊るようでおじゃる~。褒めて遣わすぞよ。明日の夕餉にも出してくれたもう~」
「本当ですかっ? やった~!」
普段はめったに褒められないため、うっかり大袈裟に喜んでしまう。はさっそく脳内の料理ノートの該当メニューのページに夢野先生おすすめ、という意味で紫の丸を大きく描いた。
ごちそうさまでした。二人で手を合わせて、は食器の片付けと洗い物に取り掛かる。それが終わる頃には、決まって二十時を過ぎている。初期の頃は二時間契約で、洗い物を終えて時間になったらそそくさと帰っていたのだが、最近は二十一時まで彼の家に厄介になっている(帰ろうとすると、いつからか幻太郎がこちらに話を振ってくれるようになったのだ。その面白おかしい話の大半は語尾に嘘ですよ、とつくのだが)。
そして、気がついたら契約更新時に三時間契約になっていた。それだけでなく、更新前の給与も一時間分割増になっていた。ただ雑談をしているだけなのにこんなのは契約違反だ。雇用側に利益がある違反なんて聞いたことないけど。
その旨を雇い主である幻太郎に抗議すると、「王である余の暇話に付き合うのも、臣下の役目とは思わんか?」とのこと。それからも口調をころころと変えられて上手く丸め込まれてしまい、もよく分からないまま、最終的に幻太郎の言葉になるほど最もだ、と頷いてしまった。今でも薄々罪悪感を抱いているが、話そうとする度にくどいという顔で睨みつけられてしまうので、は黙るしかなかった。
仕事を終えたは居間に戻り、本日の幻太郎の暇話を聞く(今まで聞いてきた中で似たような話は一つもないし、彼の口から紡ぎだされる話はファンタジックかつエキサイティングだ。さすがは作家というべきか)。
そして、本日の定時である二十一時が近づくと、幻太郎はおもむろに箪笥から一枚の封筒を差し出した。
「今月分です」
は彼から渡された封筒の中身を確認すると、そこには週三、三時間の夕ご飯代行の料金が入っていた。ひい、ふう、みい、とお札を数えて、最後にぴしっとお札を揃えた後、は封筒を鞄の中に丁寧に仕舞った。
「はいっ。たしかに! 今月もありがとうございました!」
基本、支払い方法は口座引き落としの家庭が多いが、幻太郎は毎月手渡しである(大正時代のイメージをとことん裏切らない)。それでは今日はこれでお暇しようと、が玄関に向かう途中、「ああそれと、」と幻太郎が言葉を漏らしたので、はくるりと振り返った。
「来月から週四でお願いしたいんですが」
「週四ですか? 曜日によっては大丈夫ですけど……」
は鞄の中からスケジュール帳を出す。今が契約しているお宅は幻太郎の家と合わせて三軒。一軒は平日午前のハウスクリーニング、もう一軒は火、木の午後の家事代行。そして、先生宅は月、水、土の夕食時の料理代行である。
「先生は何曜日がいいですか?」
「逆に、あなたはいつ都合がつくんですか」
「えっ? えぇーと、金曜日ですかね?」
「ではそれで。後ほどあなたの会社の方に申請しておきますので」
こんなにもスピーディーな契約変更は初めてだった。帰ったらルームメイトにお夕飯いらない曜日が増えたこと言わなくちゃ。
それにしても、日数を増やしたいだなんて何かあるのかな。聞いてもいいかな。いやでも人様の家庭の事情に口挟んだら規約違反だし……。でも世間話的な感じで、なにかあるんですかー? って聞くのはありなんじゃ……? いやでも――がそんなことを悶々と考えていると、幻太郎の声が上から落ちてきた。
「……読み切りの仕事が新しく入ったので、今以上に家のことに手が回らないんです」
「あっ。そ、そうなんですねっ!」
まるで、心に思っていたことを幻太郎に見透かされたようだ。気恥ずかしくなったは、目線を他のところに泳がせた。
それにしても、やっぱり先生はすごいお方なんだなあ、と改めて思う。は漫画や雑誌くらいしか本を読まないので、小説業界のことはよく分からない。ここに来るまでは幻太郎の名前すら知らなかったくらいだ。しかし今では、本屋の文学コーナーを通り過ぎる時、夢野幻太郎著の作品を確認するようになった。表紙のイラストが綺麗なものを一冊購入して何ページか読んでみたが、やはり文学のセンスは恵まれなかったようで読破はできず、それは家の棚に大切に保管してある。
視線をうろうろとさせて次に言う言葉を探していると、幻太郎の口からふ、とため息が漏れた。あ、この感じ、知ってる。先生が呆れてる時に出るやつだ。
「あなた、相変わらず言いたいことがすぐ顔に出ますね」
「す、すみません……。よく言われます……」
「別に、謝らなくてもいいですが」どうでもいい、という感じで幻太郎はそれきり黙りこくってしまった。
の足はそのまま玄関に向かって、その後を幻太郎もひたひたと付いてきてくれる。最初の頃はなかったけど、やっぱり見送りがあると嬉しいなあ、などと一人でしみじみとしていると、ふと思い出したことがあった。
「あっ、先生。ご飯は小分けして冷凍庫に入れておいたので、よかったら朝とお昼に食べてくださいねっ。おかずは少ないんですけど、だし巻き卵とひじきと大豆の煮物を作っておいたので!」
「はいはい。分かりました」
これに限っては個人のサービスである。は以前、廊下で水死体のように伏した幻太郎を目撃してから、こうした作り置きを始めたのである(後から聞いたことだが、あの時は三日間飲まず食わずで、ようやく脱稿できたところで台所に行くまでに力尽きたとのことだ。空腹は非常によろしくない)。
が引き戸を開けると、外の世界はすっかり夜色に染められていた。最後に幻太郎に挨拶しようと振り返ると、彼はどこか物言いたげな顔をしてこちらを見下ろしていた。「先生?」がそう問いかけると、はたとした幻太郎は翡翠の瞳を揺らして、その色をそっと伏せた。
「……いえ。なんでもありません。今日もご苦労様でした」
最近、こういうことがよくある。暑さのせいだろうか。きっと、仕事でお疲れなのだ。学生だったが夏休み課題をこなす時に苦しみながら書いていたあの原稿用紙を、幻太郎は一日に何十枚と書いている。その苦労や努力は、では到底計り知れないものだ。
「それでは先生、おやすみなさい!」
次回はデザートも作ってみよう。ベースのフルーツは涼しげな柑橘系がいいかな。先生、文旦とかお好きかな。そんなことを思案しながら、は幻太郎宅を後にする。
空を見上げると、もうすでに星がちらほらと出ている。電灯の少ない暗い夜道で少し心細い気分になりながらも、は気を紛らわすように、先生が好きそうな果物を思い浮かべながら我が家までの帰路を辿ったのだった。