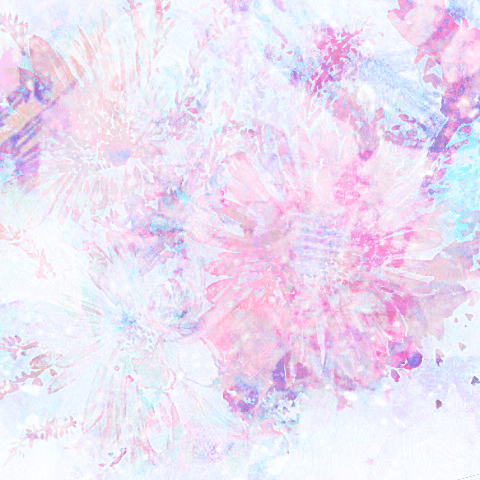やさしい陽ざしにかこまれて
怠い
それも、布団の中にずっと篭っていたいタイプの怠さだ。幻太郎は枕元に手を這わせて、スマホを手繰り寄せる。画面を開くと、ブルーライトが目に刺さってひどく痛んだ。時刻は十八時前。そうだ……夜明けに原稿を書き終えて編集者に連絡した後、あのまま落ちるように眠ったのだった。しかし、半日寝ただけでこの怠さは明らかにおかしい。
体温計を探すまでもなかった。“風邪”――その二文字が幻太郎の頭に過ぎる。不幸なことに、今日は金曜だ。あと一時間もしないうちにやってくる訪問者の存在に、幻太郎は重々しくため息をつく。
鉛のような体が許す限り、早急にスマホの連絡帳を開いた。A社編集者、B社編集者……以下略。数少ない連絡先に“家政婦”という三文字を見つけて、タップ。数回咳払いをして、声の調子を整える。声が枯れていなかったのが唯一の救いだった。
画面に“接続中”と表示されると、ハンドフリーに切り替え、スマホを敷布団の上にぽすんと置く。編集者に連絡する時とは微塵も現れない動悸と緊張が、病気に侵された幻太郎に追い打ちをかける。こうなるのもきっと風邪だからだ――そう言い聞かせていると、ニコール目で“通話中”の画面に切り替わった。
《はいっ。です!》
声が大きい。幻太郎は眉をひそめて、音量のボリュームを下げる。二言くらい文句を言いたいところだが、今回はそんな余裕も時間もない。幻太郎はゆるゆると熱っぽい息を吐き出した。
「夢野です。今日の代行の件ですが急遽休みに――ッ、ごほッ……」
喉から込み上げてきた衝動に逆らえなかった。しばらくは止みそうにない咳に、幻太郎は背中を丸めて体を震わせる。
《先生? 先生っ?》《どうかしたんですか先生っ!》《家にいますよねっ? 私も今玄関の前についたのでもうちょっと待っててくださいねッ》――待て、今なんて言った。涙目になりながら、ようやく発作の止まった幻太郎は画面を見るが、すでに通話は切断されていた。せっかくこちらが気を利かせて休みにしようとしたのに、まさか先手を打たれていたとは。
ガラガラッ!
ピシャン……バタバタバタッ……
「あいたッ」
――戸を開けて、閉めて、廊下を走り、おそらく一昨日受け取った宅配のダンボールにつまづいた。音だけでその光景がありありと浮かぶ。幻太郎はもぞもぞと布団の中に潜って、顔の半分だけ出し、数秒後には開くであろう襖の隙間をじとっと睨んでいた。
……なぜ、頬が緩む。どうしてこんなにも心臓が煩い。幻太郎が眉間に皺を寄せながら、口角にぐっと力を入れる。風邪なんかなるものじゃない。普段被っている仮面も今は取っ払われて、理性総動員で体内の修復に務めている。最悪だ。これでは、いつボロがでるか分かったものじゃない。
……いや、ボロってなんだ。別に、彼女に対して隠しているものなどなにもない。なにもないのだ。
「先生っ!! 大丈夫ですか!?」
「開口一番うるさいんですよ……。頭に響くからもう少し声量を落とし――ッ、げほッ、ごほっ……!」
「先生!? 先生っ、夢野先生っ、死なないでください先生いぃぃ~~っ!!」
……ああ、本当に、最悪だ。
「先生、何か食べたいものありますか?」
「ステーキ、ラーメン、お寿司」
「そんな病人が食べちゃいけないものばかり言わないでくださいよう……」
嘘ですよ。そんなこと言えないくらい、幻太郎は疲弊しきっていた。が来ただけで、ただでさえ少ない体力の六割を奪われた。一瞬にして気が緩んで、呼吸以外何もしたくなくなる。ぜんぶぜんぶ、彼女のせいだ。
「でもよかったです~……。ふつうの風邪で」
胸を撫で下ろすに、どこがだ、という意志を込めて睨む。それを察した彼女は両手をわたわたと振って言葉を探している。その仕草やめろ。寝る時まで頭について離れなくなる。
「ほ、ほらっ、昔、有名な作家さんとかよく結核になるって聞いたので、先生もそうなっちゃったのかと」
「いつの時代の話ですか……。それに、今は結核の治療薬も出ていますよ」
「えっ。そうだったんですか」
料理しか取り柄のない娘。頭の方は帝統と同レベルだった。会話を合わせるのも、今は億劫でしかない。
幻太郎は未だ布団の脇で正座をして動かないをじっと見上げる。初めて、彼女のことを下から見た気がする。その顔で首を傾げるな。心臓が痛む。
「……あなた、いつまでここにいるんですか。僕の連絡が遅れたのもありますが、ここにいても何もすることはありませんよ」
「えっ? えっと……先生がご飯食べてお薬飲んで、眠るまではいようかと……」
「はあ……?」
幻太郎が眉を顰めると、「だって……」とが自信なさげに呟いた。
「先生、市販のお薬も飲まないで布団に篭もってそうですし……。それに、病気の人を一軒家に一人にしておくわけにいかないじゃないですか」
うぐ、と言葉が詰まる。自分の行動が見破られている。なぜこういう時だけ妙に冴えているのか。若槻のくせに生意気だ。
それでも、だ。長時間他人が家にいるのは我慢ならない。それも自分が弱っている時に。というか、いつの間に自室に入ってきたんだこの娘は。彼女の行動範囲は基本玄関と台所と居間、そしてその間を繋ぐ廊下のみである。一体いつ誰が入室を許可したと――
――「先生!? 先生っ、夢野先生っ、死なないでください先生いぃぃ~~っ!!」
――「……なんで入口で固まってるんですか。あなたにしか見えないバリアでもあるんですか」
――「へっ? だ、だって先生の自室ですし……。勝手に入ったらいけないかなと……」
――「別に入ればいいでしょう。どうでもいいですが、そこ、早く閉めてもらえますか。風が入ってきて寒いので」
――「え、あ、す、すみません……。じゃあ、失礼しまーす……」
「……くそ」
「え? あの、先生、今“くそ”って――」
「なんでもありません」どうしたものかと、幻太郎は瀕死の脳内をぐるんぐるん回す。風邪の時はどうもやけになっていけない。いつの間にか、自分のパーソナルスペースに彼女用の座布団が存在している。病院にいる彼以外、心許した人間はいないというのに。誰が置いたこんなもの。幻太郎は心の中で座布団をけっとばした。
一方、もじもじとしながらこちらの様子を伺う。だからその捨て犬のような目はやめろ。
「食欲なくて、お邪魔で、お節介で、ご迷惑なら、このままお暇しますけど……」
……なるほど
帰るのか。そうか、それは、いい。とてもいいことだ。別に、今日は元々休ませるつもりだったし、来たら来たで追い返す予定だった。そうだとも。願ったり叶ったりじゃないか。
ところが、内なる自分はこれっぽっちも思っていないらしい。ただ声が煩くて、視線が痛くて、彼女がこの部屋にいるだけで全身がざわついてしまうくらいで、彼女が言ったものと照らし合わせても、自身の心中に当てはまるものは一個もなかった。
帰れ。別に迷惑じゃない。お節介だ。邪魔だ。目障りだ。おまえの存在が、とても――
「……うどん」
「へ?」
「うどん……が、たべたい」
何を言ってるんだ僕は
口から出たものを消しゴムで消せたらどれだけいいことか。しかし、すでに幻太郎の声が届いてしまったは、ぱあぁっとその顔に花を咲かせる。幻太郎の心臓にクリティカルヒット。思わず顔を歪めて、布団の中で胸を鷲づかんだ。
「うどんですねっ。何か入れて欲しいものとかありますか?」
「……油揚げと、かまぼこは必須。ネギは多め。鰹節と生姜があればなお良い」
「任せてくださいっ。あ、かまぼこはないので、今から行ってきますね!」
「やっぱりかまぼこはなくてもいいです」
「えっ」
「でも、さっき必須って――」「いいからさっさと作ってきなさい」お前が出ていったらここに留めた意味がなくなるだろう。馬鹿か。前世を呪いたくなるほどの鈍感さだ。幻太郎はしっし、と言わんばかりにに背を向けて、改めて布団を上に引きずった。
それから、が二言か三言くらい述べた後、ようやく襖が閉じる音がする。この部屋にいても、彼女がたてる足音や物音がよく聞こえる。一人の時は他人が奏でる物音なんて聞こえないから、余計に敏感になっているのだろう。無音に耳を澄ましていた方が心地良いのに、どうして、一人の時よりもこの胸は満たされているのだろう。
さっきよりも布団の重さがずしりと増した気がする。冷気が入ってこなくて、ひどく温かい。頭に薄ぼんやりと靄かかって、ああ、眠るな、と。すでに寝ぼけかけている脳内で呟いた。
――先生、せんせー……
どろっとした睡魔を追い払う声。ぱち、と薄ら眼を瞬きさせて、意識を覚醒させていく。の輪郭を捉え始めた幻太郎は、しばらく放心状態で彼女を見つめる。
「おうどんできましたよ~……。たべれますか?」
ひそひそと内緒話をするように声を潜める。幻太郎は鉛のような怠さと死闘を繰り広げながら、上半身をゆるゆると起こした。
熱っぽい息を吐き出して、盆に乗ったうどんを受け取る。枕元に置いてある別の盆の存在は気づかないふりをした。薄い出汁は湯気をたてて、太くて白い麺は光沢を帯びて光っている。生姜も入っている。盆に添えられているのは箸とフォーク。こんな状態でも失せないプライドが勝って、幻太郎はしばらく迷って箸を手に取った。
「……味がない」
「完璧に風邪の症状ですね~。本当は柚子風味にしたかったんですけど――」
「もったいない……」
「え?」
ちゅるちゅる。一本ずつ箸で掴んでくちに運ぶのが精一杯だ。だがまあ、食べられないほどではなかったので、幻太郎は無心で麺をすする。すするというより、唇で食んで舌で喉奥に追いやるというのが正しい。啜ってもすぐ咳き込む未来がここからでもよく見えた。
いつもより、少しだけ麺が柔らかく感じる。ネギの風味も感じない。これだから風邪というものは。最近は至って健康体だったから油断した。今後は徹夜する時は無理しない範囲ですることにしようと静かに心に誓う。
なんだかんだで、は幻太郎がうどんを食べ終えるまでそこに居座っていた。食べている途中で、出ていけ、と言うのも面倒だったので、の好きにさせる。
手持ち無沙汰、加えて視線が余っていたが物珍しそうに背の高い本棚を見上げていたものだから、見たければ勝手に見ればいいのでは、と言った。すると、好奇心旺盛な子どものように目を輝かせた#name1は、本棚に近づいて何冊かの本を手に取ってパラパラとめくり始める。しかし、十秒もたたない間にそれは閉じられてすぐに別の本に移る。そこにあるのは、彼女では理解し難い難易度の本ばかりだ。犬が玩具で遊んでいる感覚でその光景を横目に、幻太郎は残りのうどんを食んでいく。
ごちそうさまでした。控えめに手を合わせると、が本棚からこちらを振り返って「お粗末さまでした~」と盆を回収する。麺が浮いていない丼ぶりを見て、彼女はにこやかに笑った。
「先生、お風呂どうしますか? 風邪の時に熱いお湯に入って汗をかくのもいいそうですよ」
「いえ……。体を拭くだけにします」
「じゃあ、お皿片付けるついでにタオル作ってきますね~。あ、先生のおうちのタオル、お借りしても……?」
「最初に許可からでしょうが……。脱衣所の衣装箪笥の右上の引き出しに入っているので、勝手にどうぞ」
「ありがとうございます!」
盆を持ったが再び出ていって、やれやれ、と肩をすくめる。今のうちに、枕元に置かれた“物”をゴミ箱へ処分する。
すぐに、ぱたぱたと忙しない足音がして、ハウスダストをたてる勢いで布団を被る。あつあつのうどんを食べたばかりのせいか、内側から風邪とは違う熱がぽやぽやと浮き足立っていた。
一言断りが入り、ゆっくりと襖が開かれる。盆に乗せられているのは大量のタオル。分厚い湯気が天井へ登っていくのをぼんやり見つめていると、がその一枚を手に取って、熱気を逃がすようにぱたぱたと広げ始めた。
……この小娘は、一体何をしようとしている
「先生、どうかしましたか?」
「あなたが何をやってるんですか」
「お体を拭こうかと?」
「あなたが?」
「はいっ」
「僕の体を?」
「はい!」
何か問題でも? と顔に書いて首を傾げられる。いやいやいや。問題しかなくて、幻太郎の頭の中で警報機を鳴らしまくる。はというと、腕まくりをし、再度折りたたんだタオルを手のひらに乗せて、幻太郎に起き上がるようさあさあと急かし始めている。
いや、なぜだ。この娘は何を考えている。幻太郎が怪訝そうな顔をしているのを見て何を思ったのか、は合点いった顔でこう言った。
「大丈夫です! 昔、寝たきりの祖父の体もよく拭いてたので慣れてますよ!」
「僕をご老人と一緒にしないでくれますか……」
何も分かっていないに怒りを通り越して呆れ返る。こんなのは逆セクハラだ。しかし、完全に仕事モードに入っているには指摘でもしない限り、自分の言動の愚かさに気づかないだろう。
気づかせてもいいが、まあ、少し……ほんの少しだけ、下心が顔を出した幻太郎はのそのそと起き上がって、に対してゆっくりと背中を向けた。
「……背中だけ、お願いします。あとは、僕一人でもできますから」
「おまかせくださいっ!」
「やかましい」
「すみません……」
しゅん、と肩を竦めているであろうの気配に、幻太郎は溜息をつく。先ほどから雑用しかしていないというのに、それが心底楽しいとばかりに嬉々としている。こんな性根の曲がった人間の世話を焼いて、何がそんなに楽しいのか。いや、真面目で素直な彼女は仕事をしているだけ。そうでなければ、赤の他人である幻太郎と関わることも、体に触れることも一生ない。そう、すべてはお金の関係。そこに、幻太郎の求めている情は一切ない。
――ずぐん。腹の奥に溜まった泥のような不純物。ああしてほしい、こうしてほしい、自分の思うままに動いて、振り回されて、少しでも、仕事の枠から彼女の意識を遠ざけたくて。本当に、嫌になる。自己嫌悪が過ぎて、胸の中にあるそれを掻きむしりたくなってしまった。
幻太郎は後ろ向きのまま、着流しの帯を緩める。肩から腰へ汗ばんだ布を下ろすと、「失礼します~」と暢気な声が届く。タオルは熱くないか、と聞かれて、幻太郎は短く「はい」とだけ返事をした。昔とは思えないくらい手馴れた動作に、幻太郎は顔を伏せながら口を開く。
「……あなた、普段もこういう仕事もするんですか」
「介護代行ですか? 先生と契約する前は研修でいくつか入ってましたよー。でも、介護となると資格が必要になるので、私がやってたのは資格持ってる先輩の補佐中の補佐みたいな感じですね」
「へぇ……」
「でも、元々の得意分野はご飯作りなので、今は調理代行オンリーです」
興味の失せたの言葉を、幻太郎は右から左へ流していく。一瞬触れたの指先にじわっと熱が集中して、幻太郎は読みかけている本のあらすじを頭の中で辿っていた。
……数字ではおそらく一分もかからなかったが、体感的には夕食を食べている時よりもとても長い時間を過ごしたと思う。に着替えとタオルを置いてもらい、いったん部屋を出ていってもらう。その間に幻太郎は早着替え。洗濯は明日まとめてするとして、あとはこのまま眠って朝を迎えるだけだ。
再び近づいてくる足音。先ほどよりも小走り気味なのが少し気になった。今度はなんだ。すす、と控えめに襖が開けられて、が意味深な表情で入室する。背中を向けておかなかったことを後悔しつつ、幻太郎はぱちんと目を閉じる。目を合わせたら負けだ。
「……先生、枕元にあるお薬飲みました?」
「飲みました」
「にしてはお薬のゴミが出てないんですけど……」
「もう捨てました」
「先生?」
いっこうに引き下がらない。いつの間にか枕元に正座して、盆の上に新たな天敵を乗せる。余計なことを。この小娘、今日はやけに強気だ。盆に乗っていた黄色の粉は、今頃自分の胃の中で吸収されている……と、無理矢理そう思い込んだ。作家の想像力は世界を創るのである。
失礼します。囁きにも似た声で、は部屋の隅にあるゴミ箱を覗き込んだ。あまりにも素早い動きかつ予想外のものだったので、プライバシーの侵害だ、と指さす暇がなかった。
……お察し、というべきか。ゴミ箱からこちらへ視線を向けたの顔は、少々哀れみを帯びていた。なんとなく癪に障る。小学生を見るようなその目はなんだ。
「先生、もしかして苦手ですか? お薬」
「薬くらい飲めます。馬鹿にしてないでくれますか」
「あっ。じゃあ粉タイプが苦手とか?」
心の中の幻太郎が肩を震わせる。しかしすぐさま、くだらない、という色を含めながら、幻太郎は深く溜息をついた。
「……あんなもの、うちになかったはずですが」
「実は、先生が寝ている間にこっそり近くの薬局に行ってきて、あのお薬買ってきたんです。薬箱の場所聞こうとしたんですけど、先生よく眠ってたので起こすのも申し訳なくて……。ちなみに、おうちにお薬あるんですか?」
「……ちょうど切らしてますね」
「じゃあ、これ飲むしかないですねぇ」
「そもそも、普通は飲みやすい錠剤タイプ買ってくるのでは? 起きるのもだるい病人に負担をかけるなんてどうかしてますよ」
「それはほんとすみません……。錠剤タイプが全部売り切れで……。で、でも、薬剤師さんはこれが一番効くよ~って言ってましたよっ」
「まんまと営業トークのドツボに嵌ってることに気づかないんですか」
「うぐ……。あッ、その代わり、オブラートも買ってきましたし――」
「オブラートなんて余計飲みにくくするだけですよ。口の中で破れて苦味が分散するだけです」
「気持ちは分からなくもないですけど……」
もごもごと口ごもるを見て、幻太郎はふふん、と鼻でせせら笑う。勝った。若槻が自分に口で勝とうなど一億年早いのだ。あとは観念してこの部屋から出ていってもらうだけ。時刻はなんだかんだで二十時前。少し生意気だったが、今日は色々尽くしてくれたので、タクシーくらいは呼んでやろうかと、幻太郎が枕元のスマホに手を伸ばした……その時だった。
勢いよく畳を滑る音。布団に影が落ちたと思えば、「首元失礼しますっ!」と早口で言われる。幻太郎が応答するより前に、ズボッ、と首と布団の間に細い何かが入り込んで、幻太郎は身を硬くさせた。
ぐるんっ、と視界が回る。幻太郎はによって抱き起こされていた。どこにそんな腕力が。柔らかい二の腕の弾力が首の後ろからじわじわと伝わる。というか近い。顔が近すぎる。せっかく拭いてくれた背中に汗が滲んで、幻太郎ははく、と中身のない息を吐いた。
「な、にを――」
「先生、お口開けてください」
の真顔を見たのは、これが初めてかもしれなかった。
すでにオブラートに包まれていた粉末薬を片手で持ち、はそれを幻太郎の口元に持ってきている。漢方の一種だろうか、鼻腔に踊り入ってきた匂いが刺激的すぎて、幻太郎は顔を歪める。そして、の言葉をようやく飲み込み、喉から蛙のような声を出してしまった。
「はあ……ッ!?」
「だって飲まなきゃ治りません! なんのためにおうどん食べたのかわからないです!」
「空腹を満たすため」
「違います。お薬を飲むためです」
「そんなつもりで味のないうどんを食べたわけではありません」
「お腹に入れば結果は同じです! はいっ、あーん! おーくーちーあーけーてーくーだーさーいーっ!」
「やめッ……っ、離せッ! 病人に近づくな……!!」
「小中高と皆勤賞を勝ち取った私からすればただの風邪菌なんてなんのそのです! そんなに嫌ならお鼻も摘みましょうか!? それとも今からお子さん向けのおくすり飲めたねゼリー買ってきましょうか!?」
「自分で飲むから貸しなさいッ!!」
「ありがとうございます!!」
天秤は容易に傾いた。の手から無理矢理薬をぶん取った幻太郎は、喉奥に粉末を流しこむ。味覚がはたらかないうちにコップ一杯の水ですべて腹の中に収めた。二十四にもなった男が二十そこそこの女性に薬を飲まされるという黒歴史がこの地球上に生まれなくてよかった。
幻太郎がゆるゆると一息つく頃には、はいつもの気の抜けた顔に戻っていた。
「えへへ。これできっと明日には全快ですよ~」
「治っていなかったら台所にある道具の収納場所すべて替えますから」
「嫌がらせがえげつないです先生……」
へへ。それでも、はまた笑う。幻太郎は彼女をひと睨みして、布団の中に潜り込んだ。もう二度とここから出るものか。自分で作り出した温もりだけが、自身の苦労を察してくれて、安心して身を委ねることができた。
徐々に、意識が重くなっていく。いつの間にか眠っていたことも分からなかった。ただ、遠くから襖の閉める音がして、幻太郎はうっすらと口を開くが、開いただけで、その喉が震えることはなかった。に何を言いたかったのかも、睡魔と共に溶けて消えてなくなってしまった。
【
夢野先生へ
おはようございます。体調はどうでしょうか? 朝ごはんということで、昨日のうちに胃にやさしい茶わんむしとやさいスープを作っておきました。茶わんむしは冷蔵庫、スープはコンロの上にあるので、食欲があったらあたためて食べてくださいね。おくすりもぜったい飲んでくださいね。ぜったいですよ。やくそくですよ!
より
P.S 契約どおり、今日もうかがわせてもらいます。よろしくお願いします!
】
平仮名の目立つメモ書きを、幻太郎は無言で見下ろし、丁寧に折りたたむ。いったん裾に入れて、幻太郎はコンロに火を入れ、冷蔵庫からラップのかかった手のひらサイズの陶器を取り出した。
今朝目が覚めると、体の怠さもなくなっており、本当にただの風邪だったのだと自覚する。もしかすると、あれは引き始めだったのかもしれない。決して、あの苦い粉末のおかげではないと言い聞かせたかった。
こんなにも甲斐甲斐しく世話を焼かれたのは、久々かもしれない。だから、らしくもなく調子が狂った。そもそも、電話中に少し噎せただけで、自分からは風邪とは一言も言っていないし、あんなことは彼女の仕事ではない。昨夜のことは、の心そのものを象った行為だったのだろうとぼんやり思う。
……本当に、嫌になる。万人に向けるであろう優しさも、その優しさを受けるに相応しく、価値のある人間であると自惚れる、自分自身にも。
――時は移ろい、夕暮れのこと。
いつもの決まった時間、は夢野宅の玄関をくぐった。しかし、台所に響き渡るのは悲鳴ばかり。「先生、おたまどこですかっ!?」「フライパンが棚の一番上に!?」「先生~っ!」自室に篭る自分に泣きついてきたを見て、いつもの高揚感が心に波を打った幻太郎は、本当の意味で快調に向かったのだった。